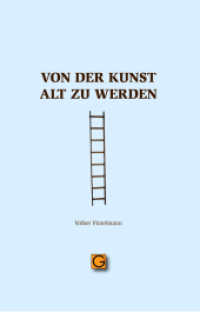- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
コロナ禍による「ステイホーム」が認知症パンデミックを引き起こしている。コロナと、それに伴う過剰な反応による「自発的ロックダウン」が認知症を引き起こしているのだ。対策としては生活習慣の改善を図り、また早期発見を進めるしかない。薬の服用と運動習慣改善の併用を提案するとともに、認知症の本質に迫り、脳の理想的なあり方を考える。早期発見のためのAIによる顔写真・脳のスキャン画像による画像診断などの最新研究も紹介。認知症の蔓延を克服する道を提示する。
目次
はじめに
第1章 ポストコロナは認知症パンデミック
1 2025年に認知症患者700万人──衝撃的予測と「新オレンジプラン」
日本の高齢化率は世界一
認知症発症率55%の衝撃と中国・韓国・米国の状況
2 認知症は生活の自立を障害
認知症特有の記憶障害
認知機能の低下による深刻な生活障害・BPSD
3 地域医療介護連携による認知症予防対策は機能していた
「オレンジプラン」とは
「新オレンジプラン」とは
認知症患者とその家族の視点の重視
地域ぐるみでの支援の強化
4 地域医療介護連携の構築──東京都北多摩北部地域の場合
「北多摩認知症を考える会」の活動
地域連携に向けた活発な動き
5 コロナ禍で崩れたプラン
感染への恐怖から絶たれた「つながり」
コロナ禍以前・以後の受診者数の変化
6 全国に及ぶコロナ禍の影響
コロナ禍による全国的なシステムの機能不全
介護の現場における大きな変化と厳しい現状
第2章 コロナ禍で切断された緊密な「つながり」
1 ソーシャル・ディスタンスvs心のディスタンス──距離と連帯の二律背反
「ソーシャル・ディスタンス」がもたらす孤独と不安
「心のディスタンス」は広げない
フレイルの危険性
コロナ禍における認知症患者とその家族──Aさんの場合
Bさんの場合
Cさんの場合
Dさんの場合
介護に第三者が介入することの重要性
感染予防のための正しい知識
2 80‐50問題はさらに深刻化している
子どもの自立を妨げるコロナ禍の不況
Eさんの場合
Fさんの場合
3 医療・介護連携への影響──緊密な連携は「3密」で醸成された
困難事例を克服するために
「心のディスタンス」を縮めるためのオンラインの活用
第3章 「ステイホーム」が認知症を増やす
1 過剰な反応による「自発的ロックダウン」
日本人の感染に対する強い恐怖
デイサービスに対する消極的な姿勢
2 海外のロックダウン報告から
南米3カ国・スペイン・イタリアで起きたこと
フランス・中国で起きたこと
コロナ禍で浮き彫りとなる国民性の違い
3 社会的な不活発による認知機能の低下と生活障害の加速化
コロナ禍による行動の変化と不安の増加
脳の血流に現れる変化
海外の2つの研究成果
4 隔絶された環境では脳が萎縮する
極地の長期滞在が及ぼす心身への影響
社会的孤立による脳の機能低下
5 対策は「つながり」の修復から
コロナ禍の認知症予防対策における4つの主要テーマ
感染予防と症状の進行防止のはざまで
第4章 脳への直接的影響
1 急性期の脳障害
新型コロナウイルス感染と神経症状
神経症状のメカニズム
いかにして脳に感染するのか
知られざる脳感染の恐怖
2 脳の霧──長期にわたる後遺症
高確率で起きる記憶障害と認知機能障害
感染後の治療形態による違い
感染が脳に及ぼす深刻な影響
3 アルツハイマー病との奇妙な関係
細胞のレベルで起きていること
遺伝子発現パターンにおける重複
OASI遺伝子と新型コロナウイルスとの関係
バイオマーカーから見た共通点
今後の研究成果への期待
第5章 認知症の本質とは何か?
1 人類がもつ高度の知能と脳の脆弱性
人類の脳の拡張とシワの形成
大脳皮質構築のプロセス
ヒト特有の脳を拡大させる遺伝子
βアミロイドの2つの側面
ヒトの脳の血流量の著しい増加
2 社会性が脳を大きくする
ダンバーの「社会脳仮説」
集団における社交の重要性
コミュニティとソーシャル・ネットワーク
3 最も新しく人間らしい部位から障害されるアルツハイマー病
アルツハイマー病の診断とメカニズム
脆弱な部位と好気性解糖の類似性
4 認知症は脳のエネルギー不全
認知症に先行する糖代謝の異常
インスリン抵抗性の脳容積への影響
特徴的な糖代謝低下のパターン
5 老化を感じさせないSuper Agerの存在
人とのよい付き合いが脳に及ぼす影響
多趣味であることの重要性
生きがいをもつこと
第6章 役に立つ早期診断
1 予防も治療も生活改善から
早期発見により進行を先延ばしに
「脳を守るための10カ条」
脳に栄養を与えて健康に
「呆けないための10カ条」も健在
2 運動習慣は海馬を大きくする
アルツハイマー病と海馬の神経細胞との関係
認知機能の低下を防ぐ運動の効果
身体活動の重要性
3 認知症治療薬は効く薬ではなく効かせる薬
認知症治療薬の処方と生活指導
医師と患者・家族とのコミュニケーションの重要性
第7章 AI時代の認知症対策
1 AIとどう向き合うか
AIは優秀で勤勉な「子ども」?
AIにできること・できないこと
2 AIによる脳画像や顔写真からの早期診断
画像識別能力の活用
さらに簡便な検査の実用化に向けて
3 脳とAIをつなげる
医療現場でのAIの活用
認知リハビリテーションと身体活動・社会活動
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ようはん
takao
garyou
ベータケ(betake)
豆苗🌱
-
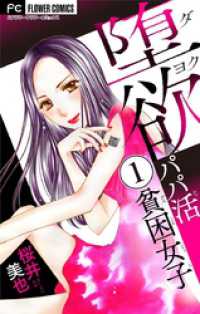
- 電子書籍
- 堕欲~パパ活貧困女子~【マイクロ】(1…