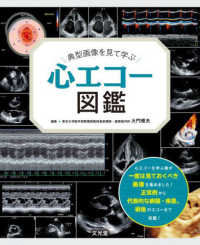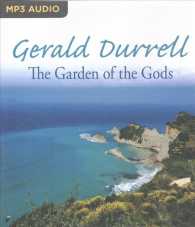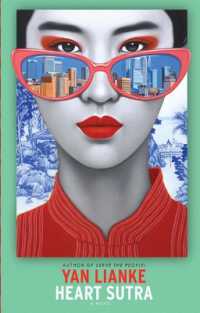- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
旧君を裏切り、親友を見捨てた「冷酷なリアリスト」という評価は正当なのか? 富国強兵と殖産興業に突き進んだ強権的指導者像の裏には、人の才を見出して繋ぎ、地方からの国づくりを目指した、もう一つの素顔が隠されていた。膨大な史料を読み解き、「知の政治家」としての新たなイメージを浮かび上がらせる、大久保論の決定版。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
105
情を排する冷徹な権力者とされてきた従来の大久保像を一変させ、幼児の如き近代日本を欧米列強に伍する国に育て上げようと苦心する父親を思わせる政治家の姿を提示する。父は子を慈しむだけでなく、わがままを叱り間違いを正したり進むべき方角を指示するが、物事に動じず国造りに邁進する大久保は新政府の基盤が固まらぬ混乱期にあって自然と誰もが仰ぎ見る指導者となったのだ。そのため彼の政治は理を優先した開発独裁にならざるを得ず、日本的な情を優先する者とは相容れなくなっていく。大久保の暗殺は理と情の必然的な衝突の第一歩といえよう。2022/09/05
kk
24
図書館本。ご存じ大久保利通の評伝。独裁的な強権を振るって富国強兵路線をゴリゴリ進めていった男という一般的なイメージに挑戦。すなはち、『大久保日記』などの一次史料を博捜することにより、知的なネットワーキングと公理公論と重んじ、民力涵養を旨として漸進主義的な殖産興業を目指した、言わば哲人的な政治家としての大久保像を提示。著者が引用された史料以外に著者のご主張を打ち消すものがないのか否か確認の仕様がないので、その当否は判断できませんが、いずれにしても大久保、少なくとも誤解されやすい男だったってことでしょうか。2026/01/12
seki
23
冷徹、独裁的と評されてきた大久保利通の人物像を覆そうとする意欲作。同じ薩摩藩出身の西郷隆盛が情で生きたとすると、大久保は「非情」に生きたと比較されがち。明治維新という革命の中、大久保は国家を深く考えていた。幕末の荒れ狂う時代を冷静に見つめ、日本の近代化を漸進的に進めてきたことが、日本が植民地化されなかった理由だと本書から伝わってくる。大久保は下野した西郷を冷たく見放したとの論もあるが、本書は二人には強く結ばれたものがあったと。人の良さの故に散っていった西郷に大久保は歯がゆさを感じていたのだろう。2023/12/09
鮫島英一
23
兎角悪役や黒幕的存在として描かれがちな大久保の実像に迫ろうとした作品で、彼の政策の意味や経歴が詳しく描かれている。僕が面白いと感じたのは前半部分。島津久光の度重なる率兵上京の意図や寺田屋事件の意味や、『王政復古の大号令』の復古とはなにを指すかは興味深かった。これらの意味を知ることで、幕末の流れがより深く理解できた。その意味で良書であると言える。 1/22022/09/29
ジュンジュン
18
爾来、幾多の大久保像が提示されてきた。曰く、主君や盟友を切り捨ててきた冷酷な指導者、曰く、有司専制を築いた強権的なリーダー。著者のスタンスはこれだ、”羊飼い”としての指導者。「羊飼いは群れの後ろにいて、賢い羊を先頭に行かせる。後の羊たちはそれについていくが、全体の動きに目を配っているのは、後ろにいる羊飼いなのだ」(ネルソンマンデラ)。オーガナイザー・大久保利通伝を読み終えて思う、彼を語ることは明治維新を語るに等しいと。2022/08/24
-
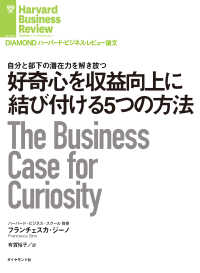
- 電子書籍
- 好奇心を収益向上に結び付ける5つの方法…
-
- 洋書
- Heart Sutra