内容説明
物語、台詞、歌で構成される舞台、ミュージカル。ヨーロッパの歌劇と大衆的な娯楽ショーをルーツに、一九世紀アメリカで誕生した。本書はその本質を音楽に注目して探る。ティン・パン・アレーのブロードウェイへの音楽供給から、一九二〇年代のラジオの流行、統合ミュージカルの成立、六〇年代のロックの影響、八〇年代に隆盛するメガ・ミュージカル、そして2.5次元へ。歴史を辿りつつ「なぜ突然歌いだすのか」という最大の謎に迫る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
126
NHKのミュージカル仕立ての人形劇を見ていたので、本物の舞台を観るようになっても突然歌いだすことに違和感はなかった。しかし改めてその歴史を辿ると、オペラからオペレッタを経て音楽の大衆化が進んだアメリカで音楽劇が成立するまで様々な要素が絡み合って「統合」され成熟していくプロセスは、それ自体が一編のミュージカルのようにドラマチックだ。ロックなど新しい音楽や音響技術の発展がさらに革新を進め、何でもありの商業演劇に振り切ったことで活性化している。人にもエンタメにも歴史があって発展しているのだと再認識させてくれる。2022/09/03
zero1
41
ミュージカルとオペラの違いは何?まずオペラはマイクを使わない(後述)。🎵舞台装置も【メガ・ミュージカル】になると大規模に。本書にもある「ミス・サイゴン」のヘリコプターや「レ・ミゼラブル」のバリケードは圧巻。🎵【何故、歌い出すのか?】という疑問はタモリが源?私は【舞台が非日常だから】と理解している(後述)。🎵【台詞か音楽か】というより、【台詞も音楽も】だろう。曲は言葉より情報量が少ない。逆に【想いの深さ】を観客に残す。🎵本書は歴史など情報満載だが、ある程度の知識が無いと理解しにくいかも💦。2025/03/07
Shun
39
サブタイトルの”なぜ突然歌いだすのか”に対する純粋な興味から読んでみました。舞台芸術の一つとして古くはヨーロッパの歌劇をルーツとして、現代アメリカで興ったロック音楽 や大衆向けのショーといった要素が絡み合って誕生したとされる。演目のベースとなるのは小説や詩といった物語ですが、舞台上の演者たちが台詞と歌でその喜怒哀楽を観客の視覚と感情にダイレクトに伝え大衆向けに広まっていった。演劇の途中で突然歌い出すという一見不自然な形式についての解説の他、その歴史と人気を博す契機となった作品解説などが充実していました。2023/03/07
ヨーイチ
34
ミュージカルは結構好き。何せ70から80年代の演劇評論では「もっとミュージカルと笑を」って主張する先生方が多かった。あと「歌って踊れる俳優の養成」とかも目標の様になっていた様に思う。結果つかこうへいを尖兵とした小劇場では質はともかくとして笑で満たされることになった。同じくミュージカルの敷居も大分低くなって今に至る。「キャッツ」の定着はエポックだったと思う。東宝も頑張って「レミゼ」のロングランでいい評判を聞く。多分今の人は歌も踊りも格段に上手くなっているのだろう。大スターが生まれて居ないのが寂しいけれど。2022/10/10
yyrn
32
親戚に宝塚歌劇が大好きな叔父さんがいたが、普段の印象と全然違うので、申し訳ないが、少し気持ち悪く感じていたw。だから一番好きな映画は「サウンド・オブ・ミュージック」65だと他人に話したことはないw。▼私は、突然歌い出すことは感情の発露、舞台表現の一種だと感覚的に受け止めていたので、何の違和感も抱かずに演劇や映画を鑑賞してきたが、なぜ突然歌い出すのか?というウマイ副題に釣られて読んでみると、韻をふむ詞や台詞の表現が古代演劇からあって(それがオペラにつながって)その後、ある理由から日常使いの言葉があとから⇒2023/01/14
-

- 電子書籍
- これが最後の×××かも 2巻 バンチコ…
-

- 電子書籍
- 悪党の愛娘になりました【タテヨミ】第1…
-
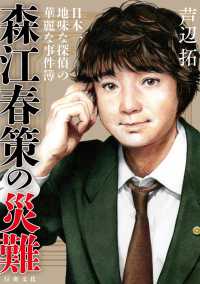
- 電子書籍
- 森江春策の災難 - 日本一地味な探偵の…
-
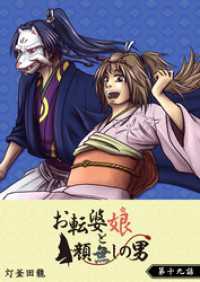
- 電子書籍
- お転婆娘と顔無しの男【単話版】(19)…
-

- 電子書籍
- 【フルカラー】柳原くんはセックス依存症…




