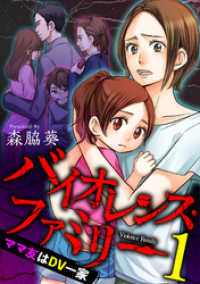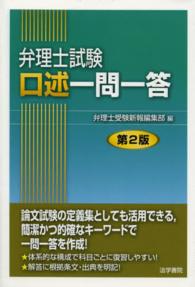- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
なぜ危機を伝える言葉は人々の心に響かず、平静を呼びかけるメッセージがかえって混乱を招くのか。日々新たなリスクが登場し、その対処に迫られる現代社会にあって、もっとも重要なのはリスクをきちんと伝え、話し合い、共有すること――すなわちリスク・コミュニケーションである。専門家や行政からの一方的な発信でなく、情報公開と透明性に基づく開かれた議論によって初めてリスクは的確に理解され、よりよい社会は可能になる。リスクと共に生きるすべを模索する入門書。
目次
まえがき
第1章 リスクを知る
1 リスクとは何か
身の回りにあふれるリスク
危険、ハザード、クライシス
2 リスクの考え方
期待値としてのリスク
尺度としてのリスク
リスク分析の三要素
リスク分析における恣意性
3 専門家まかせが失敗を招く
間違える専門家
繰り返される政策の失敗
コミュニケーションに関する専門家の誤解
リスク情報を共有する意味
第2章 リスクを伝えるⅠ 基礎編
1 リスク・コミュニケーションの誕生
リスク・コミュニケーションはいつ生まれたか
リスク比較の落とし穴
対等なパートナーとして扱う
クライシス・コミュニケーションとの違い
タイレノール事件
警告しない怠慢と知る権利
意思決定過程への参加
2 コミュニケーションとしてのリスク・コミュニケーション
それは「意見交換会」か?
コミュニケーションとは何か
相互作用としてのコミュニケーション
伝わっているという思いこみ
多様なコミュニケーションのかたち
3 リスク・コミュニケーションを定義する
多様化していく定義
リスク・コミュニケーションの定義
リスクについての議論
新しい用語は考え方を変える
4 リスク・コミュニケーションの実例
身近にあるリスク・コミュニケーション
制度化されたリスク・コミュニケーション
警告しないことの責任
制度を活用する
5 個人のリスクと社会のリスク
個人的選択と社会的論争
合意による問題解決
個人がリスクを避けるためには
社会でリスクを削減するためには
第3章 リスクを認知する
1 リスク認知とは何か
リスク評価とリスク認知
リスク認知の次元
リスク認知のバイアス
専門家にもバイアスはある
社会的・政治的態度による差異
エリート・パニック
さまざまな認知バイアス
2 集合行動への理解
「買い占め」は愚かな行動か?
予言の自己成就
社会的ジレンマとしてのリスク問題
3 安全が油断を招く──リスク・ホメオスタシス
リスクの許容水準は一定
安全な社会を実現するには
第4章 リスクを伝えるⅡ 技術編
1 説得的コミュニケーションの技術
説得的コミュニケーションとは何か
恐怖喚起コミュニケーション
恐怖喚起が効果的でない場合
一面呈示と両面呈示
説得の予防接種理論
自分で考えることの利点
強制的メッセージは逆効果
2 言葉づかいの選び方
誤解を招く言葉
混乱を招く言葉
ほのめかし
人や場所へのラベリング
風評被害という責任転嫁
3 リスクを伝えるときの注意点
悪い情報は伝わりにくい
悪い情報は曖昧に伝えられる
曖昧さが招いたパニック
誤解を避けるために
4 情報を賢く理解する
まずは疑ってかかる
多様な情報源にあたる
自問のためのチェックリスト
第5章 リスクを管理する
1 企業の印象管理
企業のリスク・コミュニケーション
タイレノール事件再考
広報技術としてのクライシス・コミュニケーション
情報への感度
2 印象管理の技術
苦境における印象管理
謝罪の五条件
言い訳と謝罪
さまざまな印象管理
3 緊急時のコミュニケーション
9・11の影響
情報管理は必要なのか
隠蔽と
オオカミ少年効果
4 情報公開、透明性、信頼
情報の信頼性をどう担保するか
情報のスキャンとモニター
第6章 リスクについて話し合う
1 「みんなで決める」はなぜ重要か
集団の意思決定
みんなで決めることはなぜいいのか
手続き公正の重要性
公聴会の罠
誰がコミュニケータか
2 集団の意思決定の落とし穴
集団極性化
集団浅慮
共有情報の優位性
3 合意をいかに形成するか
合意形成は行われているか
より良い集団的意思決定のために
内部告発者の存在
創発的なリーダーシップ
第7章 リスクを共有する
1 拡大するリスク概念
リスク分析は万能ではない
広義のリスク
事前警戒の原則
手遅れ事例からの教訓
「科学的に未確定」の危うさ
2 一般人は無知ではない
パターナリズムの破綻
市民の能力をどうみるか
市民の知恵を活かす
特別な配慮があるべき人への対応
3 「想定外」はなぜ起こるのか
想定外という言い訳
嫌な想定はしない
空想文書
行動が考え方を変える
失敗を記録する
4 リスク・コミュニケーションがつくる未来
「文句を言う」ことの重要性
安全な社会をめざして
あとがき
引用文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まゆまゆ
totuboy
takao
いま あすみ
Go Extreme