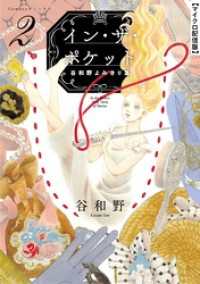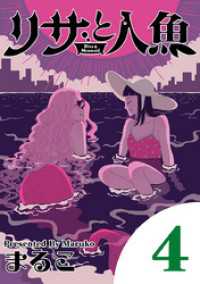内容説明
なぜ彼らは何も言わなかったのか?
1933年、ヒトラーが首相に就任、国会議事堂放火事件を契機に、ヒトラーとナチ党は共産党やユダヤ人への弾圧を強化、国会選挙でナチ党が勝利、全権委任法を可決して、独裁体制が成立した。大きな歴史的転換期となったこの年、海外メディアやその駐在記者たちは、ヒトラーおよび「ナチ台頭」、「ユダヤ人迫害」をどのように報道していたのか? 本書は、フランスのジャーナリスト(メディア批評)が、ナチに批判的で国外追放された記者から従順で妥協的な記者まで、当時の記事や回想録を掘り起こして徹底検証する。
海外メディアやその駐在記者たちが検閲や威嚇に屈せず、欺瞞や宣伝に騙されず、ナチを告発する報道は困難極まりなかった。ナチに目をつけられていたエドガー・マウラーや、ヒトラーに独占インタビューしたドロシー・トンプソンのように辛辣な記者は、すぐに国外追放されてしまう。一方、ナチとは妥協しながら、現場に残ることが重要と考えるルイス・ロッホナーは、批判の対象となる。「トランプ現象」と「報道の自由」が脅かされる現代に警鐘を鳴らす書。三浦俊章氏(朝日新聞編集委員)推薦。〈フランス・ジャーナリズム会議賞〉受賞作品。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
99
礼儀正しく恥を知る人間ほど、相手も同じ態度をとるとの前提で動く。文明や法律が発展し、昔のような野蛮人ではないと考えるのなら尚更だ。なので平然と嘘をつき、恥知らずで暴力をも辞さぬ権力者を前にすると思考停止に陥る。特に公正中立な報道を標榜するメディア関係者は、大量に発信される嘘の真偽を指摘するのに疲れて権力に迎合するか危険性を訴え続けるかを迫られる。本書で描かれるヒトラーの手法はトランプに継承され、今またプーチンがウクライナ侵攻で利用している。有効だから何度も使われたのなら、今後も同じ事態が繰り返されるのか。2022/03/15
くらーく
4
あとがきまで含めると500ページ弱。いやー厚い本を久しぶりに。しかも読みにくい。著者はフランスのユダヤ人。フランスのエスプリなのか知らんけど、話があっちこっちに派生したり、時代も前後して、アメリカ大統領選になったりと、なかなかしんどいわ。 ただ、読み応えは十分。エッセンスをまとめれば、と思わない事も無いけど、当時の資料をや該当者の著者を引用したりで、客観的な仕上げになっているようですな。人生の意義を探る年齢でもあったのでしょう。本書は、2019年のフランス・ジャーナリズム会議賞を受賞したそうで。2022/03/31