内容説明
『旅の絵本』『ふしぎなえ』『ABCの本』などが世界中で愛されている画家の、初の自伝。
「自伝のようなものは書くまい」と思っていたが、日本経済新聞の「私の履歴書」欄に原稿を寄せるうちに「記憶のトビラがつぎつぎに開いた」、と大改稿大幅加筆。人情味のある豪傑な義兄、小学校で隣の席だった女の子、朝鮮人の友人、両親、弟……昭和を生きた著者が出会い、別れていった有名無名の人々との思い出をユーモア溢れる文章と柔らかな水彩画で綴る。
「わたしも、冗談が多すぎた。でもまだ空想癖はやまない。しかしこの本に書いたことはみな本当のことで、さしさわりのあることは書かなかっただけである」とは著者の弁だが、炭鉱務め、兵役、教員時代など知られざる一面も。
50点以上描き下ろした絵が、心温まる追憶は時代の空気を浮かび上がらせ、読む者の胸に迫る。楽しく懐かしい、御伽話のような本当のお話。
※この電子書籍は2014年5月刊行の文春文庫を底本としています。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
78
この本のあちこちに、『算私語録』のシリーズで読んだエピソードが出てくるのがなつかしい。もちろん、あれよりは長文であるし、こんなふうに半生記の文脈の中に置かれると、「あれはそういう場面だったのか」と改めて感慨をもたらしてくれる。途中から自伝ではなくなって、時系列にも話題にもこだわらなくなるが、それも安野さんらしい。物故した人々の思い出は切なくなるが、最後はカラッと終わってくれる。森毅先生の「これやねん」の話はすごくいい。全体の中でも、「結婚のこと」に出てくる、子どもへの思いは、本当にその通りだと共鳴したい。2021/05/07
yumiha
52
津和野の安野光雅美術館へ行ったことを思い出した。土蔵のような外観、昔の木造校舎のような室内などなど。ツワブキが咲いていたから、冬だったのだろう。1926年生まれの自叙伝だから、戦争中の様子も描かれていて、「千人力」や「絨毯爆撃」「出征兵士の家」の看板など驚いた。また、「絵は説明ではない」というフレーズにも共感した。絵画展は感じるものなのに、その絵の説明文のところに人だかりがしている様子を苦々しく思っていたから。そして、昨年亡くなられた安野光雅氏の冥福を祈りながら偲んだ。2021/10/14
ぶんこ
49
安野光雅さんと妹尾河童さんとがセットで思い出される。人間としての軸が似ていると思えるのです。この本からも思っていたとおりの安野光雅さんがいらっしゃいました。光雅というお名前をお姉さんたちが名付けられたと知り驚きました。なんと典雅な発想。ABCの本の絵を外国のメーカーが無断で使っていた時も、お金で話をつけようとするメーカーをスルーしてうやむやで終わらせるなど、安野光雅さんらしい。最も心うたれたのは息子さんがお父さんを守ろうとした話。この父にしてこの子あり。冗談で、刑務所から年賀状を出したら大騒ぎが秀逸。2023/03/21
fwhd8325
29
伝は、誰でも書けそうでいて、決してそんなもんじゃないことを感じます。表紙を初め、安野さんの作品が素敵です。絵が語ることを書かれていますが、それを証明している作品だと思います。もちろん、今回は文章がメインです。その中には、人生を語ることができる一だからこその考えもあります。そして、それが押しつけでないことが、まさしく自伝を書くにふさわしいのだとも思うのです。2016/08/26
pirokichi
22
「ほぼ日の學校長だより」に紹介されていて早速購入。娘さん3歳の頃のエピソードは、通勤電車で「ほぼ日の學校長だより」で読んだ時にふふっと笑って、本書を読んだときにけらけら笑って、あまりにおかしくて夫に読んで聞かせながらあははは笑って…3度も笑ってしまった、ハマった。山本虎雄という朝鮮人の子が転校するときに安野さんに送った手紙には「げんきでヘンヨウせいよ」と書かれていた。「勉強」よりも「ヘンヨウ」の方がずっと胸に迫る思いがし、それは今でもそうだ、という安野さんが好きだ。「これやねん」の森毅さんの絵がそっくり。2021/06/15
-
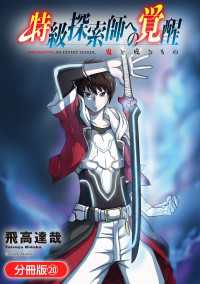
- 電子書籍
- 特級探索師への覚醒【分冊版】 20巻 …
-
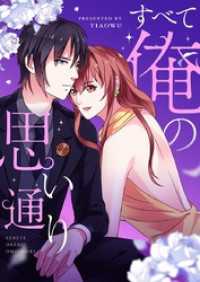
- 電子書籍
- すべて俺の思い通り【タテヨミ】第97話…




