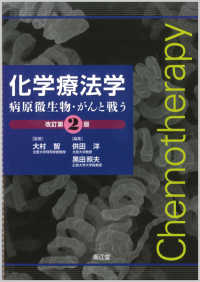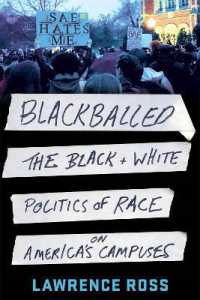内容説明
16世紀中頃、戦国日本に伝来した鉄炮。砲術師・鉄炮鍛冶・武器商人により国内に広まると、長槍や騎馬隊が主力だった戦場の光景を一変させた。さらに織田信長は検地によって巨大兵站システムを整え、鉄炮の大量保有を実現。鉄炮や大砲を活用する新たな戦術を野戦・攻城戦・海戦に導入し、天下統一へと邁進した。軍隊や統治のあり方をも変えたこの「革命」が豊臣秀吉、徳川家康と引き継がれ、近世を到来させるまでを描く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
114
大規模な鉄炮導入を果たした信長は天下統一を目前に倒れたが、後継の秀吉と家康は鉄炮や大砲による強大な軍事力を背景に中央集権体制を樹立した。これにより大名を鉢植え化して中世以来の統治システムを失わせ、曲がりなりにも幕府を中心とした法治国家の形が整えたのだ。明治に匹敵する変革を3百年前に経験していたわけで、しかも江戸期を通じ続いた鉄炮生産の技術進歩が幕末維新での近代化を促した。鉄炮伝来は戦国時代を終わらせただけなく以後の政治や社会を根本から変えたのであり、日本史における存在価値はもっと高く評価されるべきだろう。2022/04/16
HANA
68
鉄砲の伝来。本書はその伝来によって戦場のみならず政治のシステムまでが如何に変貌したかを論じた一冊。それまでの馬が主力である戦ではその生産地である東国が有利であったが、鉄砲の伝来によって硝石と鉛の入手が容易な上方が優位に立った等は目から鱗の指摘。弾丸としての鉛の優位性などは今まで考えた事も無かったなあ。さらにはそれによって兵站の確保やそれを支える織田検地というシステムによって藩の原型が形作られたことまで兎角興味深い事ばかり。鉄砲の伝来によってその後の日本の有様までも変化した事がよくわかる一冊であった。2022/05/18
かごむし
28
織田軍の強さは鉄砲の数だと思っていたけど、弾や火薬の原料になる鉛や硝石をイエズス会などを通じて輸入できたことにあったという。高価な消耗品を使い続けられるのは、強固な家中統制の下、豊富な資金調達を可能にした織田家のみであり、他の戦国大名からは突き抜けた存在だったようだ。室町時代後期、応仁の乱以降ばらばらになった日本が、統一に向かったのは時代の必然に思うのは錯覚で、各大名が自分の国だけ保全できれば満足できたであろう社会を、圧倒的な火力で一つにまとめ上げようとした織田信長はやはり、異端であるし、革命的であった。2022/09/07
ようはん
26
テーマとしては鉄砲伝来による日本の軍事システムの変化、その影響による社会の変化について。平山優著「検証 長篠合戦」で東国の武田に対する畿内を抑えた信長側の鉄砲に使用する弾薬の確保の優位性が語られていたが、弾の原料である鉛がタイの鉱山で生産されていたのが研究で判明し、それがイエズス会を通したルートであり一方で朝鮮からの足利義昭通じてのルートも存在し信長包囲網勢力に流通していたというのが一番興味深い点だった。2022/05/31
coolflat
22
鉄砲導入による軍事革命は石高制に基づく新たな軍隊を創出し、日本国家の集権化の推進剤として機能した。つまり従来の人馬による戦闘では殺戮能力・破壊規模は限定されていたが、鉄砲戦は配備の規模と戦略によって確実に勝利できたばかりか、短期間における地域統合をも可能にしたからだ。検地によって誕生した軍隊は領地権を天下人が諸大名に預け置くことを前提としている。在地制を剥奪された大名軍隊は天下人の命令に服さねば存在し得ない。常に人盗り・物盗りといった略奪を伴う戦国大名の軍隊ではなく、軍隊のみに集中する近世軍隊へと変質した2023/01/10
-

- 電子書籍
- おじさん、この気持ちは何?【タテヨミ】…