内容説明
武家社会を生み、鎌倉幕府を支えた東国武士団の形成と組織構造を、文献と現地の精査を通して解明し、関東平野を疾駆する武士達の実像に迫った中世史研究の先駆的著作。解説=大隅和雄
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
獺祭魚の食客@鯨鯢
62
私の住む地域は武蔵国と相模国にまたがる位置にあります。現在の行政上の地名は古代からの歴史的な伝承に基づいてつけられており、それだけで興味が湧きます。鎌倉時代、有力者はそこにある荘園の管理者「在地領主」となり、場合によって鎌倉幕府の御家人になりました。領主と同じ姓の知人を見るとひょっとしたら末裔かもしれない、と勝手に想いを巡らすのも楽しい。時代劇に登場する人物への親近感が増します。再来年の大河ドラマが鎌倉時代を取り上げると聞き、にわかに郷土愛に目覚めています。2020/01/23
翔亀
35
【中世29】GWはこの本をじっくり味読できてよかったと思う。本物の歴史書とはこんなものをいうのだろうと思った。同じ著者の「中世武士団」が一般向けの書下ろしなのに対して、本書は論文集。「中世武士団」の元となった学会で著名らしい学術論文「中世成立期軍制研究の一視点」を収めるとともに、神奈川県県史編集室編「神奈川県史 通史編1 原始・古代・中世」(1981)の分担執筆分も多くを占める。「〇〇県史」は各県で出されているが、読んでこんなに面白いものとは意外だった。この著者だからこそなのだろうが、その面白さとは↓2022/05/11
獺祭魚の食客@鯨鯢
17
鎌倉武士とはすなわち相模武士でした。源頼朝の旗印の下、平氏であった三浦氏などが寝返って馳せ参じ東国政権の形成に寄与しました。 現在の神奈川県に当たる相模国や武蔵国の一部(現川崎市及び横浜市)には、多くの在地領主が荘園を営みその経営権の保証(安堵)を京の貴族から受けていましたが、搾取に不満を持った者たちは頼朝の東国政権にその解決策を求めました。 荘園の名前を見ると、どの名前も現在まで続く地元有力者の名前になっており、領主が荘園責任者(荘司)から頼朝の家来(御家人)へ鞍替えしたことがわかります。2018/10/01
Satoshi
13
鎌倉殿の13人の放送時に購入し、今まで積読となっていた。かなり硬派な歴史論文であるので、読み進めるのに時間がかかった。平安貴族の地方統治部隊であった関東の武者が戦争を通じて権力を取る。源頼朝亡き後の北条義時を中心とした権力闘争の部分はドラマを思い出しながら読めた。2025/10/24
politics
4
本書は平安末〜鎌倉期までの武士の発生と展開などを中心とした論文集である。源頼信ら「武家の棟梁」と称される武士は、国司となって現地に赴きそこに根を張り中央からの軍事力と地方豪族のとを束ねていき、力を伸ばしていったとされる。そしてドチャクした土地のさらなる経営を目指し、国司や他の武士団との抗争などからさらに軍事力が深められていった。大庭御厨や新見荘などの具体例を交えていて大変勉強になる読書体験だった。2020/09/14
-

- 電子書籍
- 復讐貴族【タテヨミ】 第33話 ミヅキ…
-

- 電子書籍
- 猫の花嫁【タテヨミ】第35話 picc…
-
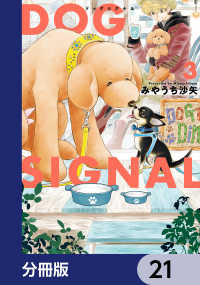
- 電子書籍
- DOG SIGNAL【分冊版】 21 …
-
![お葬式にJ-POP[ばら売り]第2話[黒蜜] 黒蜜](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0941680.jpg)
- 電子書籍
- お葬式にJ-POP[ばら売り]第2話[…





