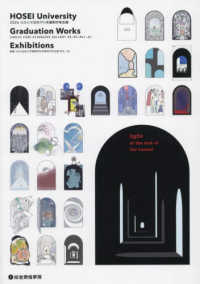内容説明
「定説」も「最新学説」も一から見直そう!
45のクエスチョンで日本史を総ざらい。
人事、経済、組織、リーダー、国際環境――
古代から近世まで「時代を動かす力」がわかる!
【目次より】
日本史は何の役に立つのか
歴史用語を疑え
史実とは何か 史料の使い方、疑い方
流れを押さえる四つの視点
世襲のメリット実力のメリット
史料が少ない古代史を読み解くには
ヤマト王権のフランチャイズ戦略
「日本」をつくった警戒レベルMAXの外圧
律令体制を税金問題として考えてみよう
朝廷は全国を支配できていたか 「面」の支配と「点」の支配
貴族の地方放置が武士を育てた 平将門の乱を再評価する
実はもろかった摂関政治
東国の武士たちはなぜ流人の頼朝を担いだのか?
どうして源氏将軍が絶えたのに鎌倉幕府は続いたのか
元寇は本当は避けられた?
「銭」に負けた得宗専制
鎌倉幕府を倒したのは後醍醐天皇ではない
応仁の乱は尊氏派vs直義派の最終決戦だった
信長最大のライバルは一向宗だった
江戸時代 近代から見るか、中世から見るか
徳川幕府の名君と暗君
「鎖国はなかった」説を外圧理論で考える
江戸幕府を滅ぼした「働かないおじさん」問題 ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とん大西
121
「日本の歴史はぬるい」…もはやキラーワードです。本郷先生の著書を読むのは本書で7か8冊目。内容が重複しててもソフトな語りについつい引き込まれてしまいます。さすがに旬なだけあって鎌倉時代の章は面白かったです。北条義時が権力基盤を固めた執権の座ですが、ステータスとしては北条得宗家の方が上位。ああ、確かにそうか。鎌倉幕府も後半になってくると執権の存在感も薄いもんなぁ(このへんは大河ドラマ太平記が印象深い)。やっぱり色々気づかせてくれます、本郷さん(^^)2022/06/14
きみたけ
78
著者は東京大学史料編纂所教授の本郷和人先生。先日読んだ「歴史のIF(もしも)」が面白かったので別の本もチョイス。史料の読み方、史実の確かめ方、定説や最新哲学の疑い方など、「時代の変化はなぜ起きたのか?」を考えさせる一冊。鎌倉幕府の成立も頼朝の征夷大将軍任命の時(1192年)ではなく、関東の武士たちを率いて鎌倉に軍事政権を樹立した時(1180年)ではないかとのこと。また、ヤマト王権が勢力を拡大したのは地方豪族に大陸の技術指導を施し「古代フランチャイズ制」を敷いた結果と説きます。「多角的な視野」が大事ですね。2022/09/27
kawa
41
著者曰く専門的に歴史学を学ぶとは、作業の1が古文書・古記録を正しく読めること、作業の2がそこからどんな史実を復元できるかのチャレンジ。作業の2では、「大きなホラを吹く練習をせよ」と恩師から教えられた由。本書は、そんな「大きなホラ」を集めた一冊とのこと。「応仁の乱は尊氏派(東軍・細川氏)VS.直義派(西軍・山内氏)の最終決戦だった」等、「へえぇの目から鱗、大ホラ?」的分析が面白い。古代から江戸時代バランスよく記述されていて、歴史を大掴みするのに重宝。間をおかないでの要再読書かな。2022/09/13
Isamash
35
本郷和人・東大史料編纂所教授2022年発行著作。古代から始まり、平安、鎌倉,室町、戦国、江戸時代と話題を色々と振っているのだが、あまり面白くない。どこから何時代とするかなど、自分にとってはどうでも良い。まあ、元寇は外交の不手際が原因で避けられたというのが、唯一興味をひいた話題か。あと義経が頼朝の政策をよくわかっておらず皇室から官位をもらってしまったとの見解は、初耳。まあ全体的に、日本の歴史は「プレイヤー」拡大の歴史と解釈しているが、自分に都合の良いことを並べ立てている様で、マルクス史観の様で、納得できず。2024/05/11
ホークス
33
2022年刊。思い切った説も含め、とにかく分かりやすい。以下自分用メモ。⚫︎戦国期迄の税は基本、民から取れるだけ取って有力者が奪い合う式⚫︎藤原摂関制は当主の娘が天皇の男子を産むことで保たれ、少数の身内で主導する体制が二百年続いた⚫︎旧来の豪族や土着化貴族から成る地方武士は農業振興に努める一方、国司からの搾取を避けるため摂関家や大寺社に「みかじめ料」を上納(=荘園化)。支配のネジれが武士を自立させた⚫︎天皇家は①藤原氏からの外戚奪取②武士の活用によって院政を確立した⚫︎源頼朝は朝廷との外交で才覚を発揮。2025/12/18
-
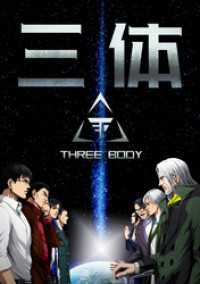
- 電子書籍
- 三体【単話版】(52) Ruby RED