内容説明
大陸から日本列島に伝わった鉄文化は、他の地域で類を見ない進化を遂げた。鉄鉱石資源に乏しい国土において砂鉄原料のたたら吹製鉄という独自の製鉄技術を開発し、切れ味鋭く強靱な日本刀を生み出す素材にもなった。類まれな技術の発展過程、幕末以降の近代製鉄技術を経て八幡製鐵所の創業までの道筋を辿る。古代から近代まで、およそ二千年に及ぶ日本における鉄文化の発展過程を追うことで、鉄がいかに長い時間をかけて私たちにとって身近な金属になってきたかを理解する一冊。
目次
プロローグ
序章 隕鉄利用と人工鉄の出現
人類が最初に出会った鉄は隕鉄
隕鉄から作られた流星刀
人工鉄の出現
人工鉄の生産
二種類の鉄
序章のまとめ
第1章 中国・朝鮮半島の古代鉄文化
中国の古代鉄生産
青銅器文化との関連
美金と悪金
朝鮮半島の古代鉄生産
新羅の製鉄遺跡
百済の製鉄遺跡
古代朝鮮半島の鉄生産の特色
第1章のまとめ
第2章 日本列島の初期鉄器文化
邪馬台国時代の鉄事情
鉄製農工具の出現
鉄製武器の出現
高度な鍛冶技術を裏付ける鉄戈
弥生時代に製鉄は行われていたのか?
鉄
第2章のまとめ
第3章 古代における鉄生産の技術
古墳時代以降の製鉄炉
鍛冶技術の系譜
大鍛冶炉と小鍛冶炉
古代鉄生産をめぐる四つの画期
用語の基礎
第3章のまとめ
第4章 武士の時代の鉄生産──中世
製鉄炉の大形化
製鉄炉の分類
中世の鉄の生産量
明に大量に輸出された日本刀
中世に流通していた鉄素材?
南蛮鉄
鋳物師の活躍
小倉鋳物師の仕事
第4章のまとめ
第5章 たたら吹製鉄炉の完成──江戸時代
「たたら」とは何か
天秤鞴の出現
床釣り
高殿と山内
鉄穴流しの成立
炭窯のこと
鉧押し法と銑押し法
中世の精錬鍛冶炉
大鍛冶炉の成立
たたら吹製鉄炉の完成
金屋子信仰
鉄は中国山地で独占
第5章のまとめ
第6章 幕末の鉄事情──各藩が独自に鉄の生産を試みる
長州藩のたたら吹製鉄
福岡藩のたたら吹製鉄
佐賀藩のたたら吹製鉄
熊本・八代の鉄山
日向飫肥藩の製鉄
薩摩藩の鉄づくり
朝鮮半島の石築型炉との共通点・相違点
石見職人の移動
反射炉の構築
佐賀藩と薩摩藩
韮山と水戸藩
賀来氏の反射炉、萩藩の反射炉
釜石高炉の建設
高炉以前の東北の製鉄
第6章のまとめ
第7章 官営製鉄所の創業へ──明治時代
輸入洋鉄と官営鉄山
近代の高炉製鉄
日清戦争と鉄需要の本格化
官営製鉄所を八幡へ
製鉄事業の本格化
なぜ製鉄所は旧筑前国領内でなければならなかったのか?
たたら吹製鉄の終焉
第7章のまとめ
エピローグ
主要な参考文献
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
AICHAN
スプリント
ケルトリ
ナオ
-

- 電子書籍
- ニューノーマル59 コミックアウル
-
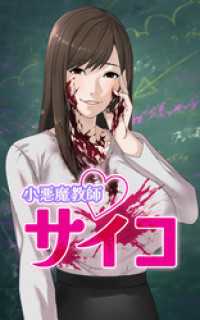
- 電子書籍
- 小悪魔教師サイコ【タテヨミ】第99話 …
-

- 電子書籍
- ブラックナイトパレード【タテヨミ】 4…
-
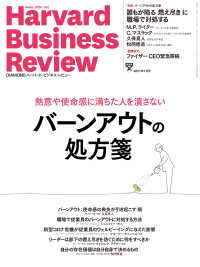
- 電子書籍
- DIAMONDハーバード・ビジネス・レ…
-
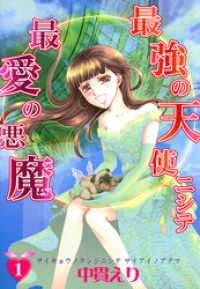
- 電子書籍
- 最強の天使ニシテ最愛の悪魔 1巻




