内容説明
武士も巨大機構の歯車の一つに過ぎなかった。幕府の組織は現代官僚制にも匹敵する高度に発達したものだった。「家格」「上司」「抜擢」「出向」「経費」「利権」「賄賂」「機密」「治安」「告発」「いじめ」から歴史を読み解く、現代人必読の書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
102
国家や企業を運営する組織は、日本では徳川幕府が形成したものが原型となった。鎌倉以来の武家政権にはないほど官僚制が発達し、組織の論理が天下を支配していた実態が見えてくる。出世競争や利権争奪、処世術に実務能力など、組織人に求められる力は今日と変わらない。権力を笠に着たいじめや横暴、面倒な事件をなかったことにする話など、新聞の三面記事を見るようで身につまされる。また高い家格の大名旗本がキャリア組で、それ以下がノンキャリア組なのも、試験で選ぶのを除けば同じだ。徳川流は日本人の心情に適応しすぎたのかと思えてしまう。2022/07/21
きみたけ
49
著者は、元東京大学大学院情報学環教授で日本の歴史学者の山本博文先生。田沼意次・大岡越前・長谷川平蔵などの有名人から無名の同心・御庭番・大奥の女中まで、江戸の幕府組織を事細かに徹底検証した一冊。幕府の組織において、「家格」の上下に泣き笑い、「出世」のために上司にゴマをすり、「経費」削減に明け暮れ、組織の論理の左右されていたようです。特に「不正の隠蔽体質」は現代でも企業のコンプライアンス違反で大問題になっており、現代の官僚制や企業社会に通ずるところがあります。「上司は部下をやる気にさせる必要がある」に✓😅2024/01/27
kk
21
図書館本。老中や勘定奉行から御庭番だの坊主衆に至るまで、江戸幕府の官職のあれこれについて、一般読者向けながら然るべく詳細に教えてくれる一冊。幕府の統治機構やその運営システムが実はかなり精緻・複雑であり、それを支えた柳営の官吏たちも真面目に精励していたってのはかるく意外な発見。だから何だという内容ではなく、いわばトリビア的な事実の提示が中心ではあるものの、逆にそれだからこそ、kkのような一部の歴史ファンには読んで楽しい一冊です。 2022/12/11
fseigojp
17
250年というけれど、最後の15年は幕末というべきで 黄金時代は1600年から1750までの150年で、それ以後の100年は停滞期2022/04/26
hiyu
8
江戸幕府の統治機構をその官職や人物、事件等をもとに紐解いてあり、結構知らなかったことも多く参考になった。そして今とさほど変わりはないのではないかという印象も同時に持った。2022/12/26
-
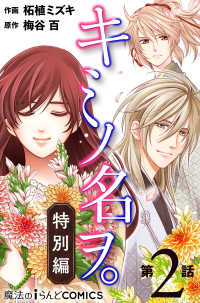
- 電子書籍
- キミノ名ヲ。特別編【第2話】 魔法のi…
-
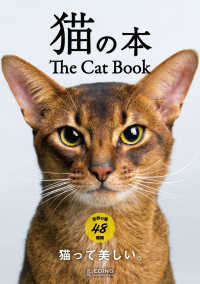
- 電子書籍
- 猫の本







