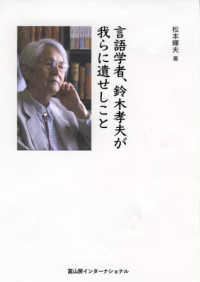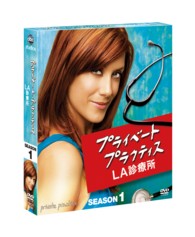- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
戦国時代を知るうえで、戦国大名と同様にその動向が注目される「国衆」とはなにか。「国衆」提唱者が豊富な事例を基に詳細に解説。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
108
戦国時代が大名だけでなく国衆があってこそとは、歴史好きには完全に定着した。しかし各種ある解説書の多くは著者の専門とする地域や大名関連に限定されていたため、全国レベルで発展から終焉までを一般向けに解説してくれる本書は貴重な1冊。国や地域の事情で国衆の形成や大名への従属プロセスが異なり、様々な苦心や工夫があったことがわかる。また毛利氏や徳川氏も国衆から成り上がった大名であり、国衆こそ戦国期を動かすカギであったのだ。最近は国衆を主人公とした歴史物も増えており、手付かずだった分野の新たな発見や可能性を確信させる。2022/05/21
スー
23
73国衆の成り立ちの解説と大名と国衆達の関係や関わり方など興味深い内容でした。国衆が大きく成り大名になる例が沢山あると思っていましたが意外や意外に徳川家・長宗我部家・龍造寺家・毛利家の4家だけだったとは!驚きました。戦国大名達は国衆達を自治を認めある程度の進退の自由を認めながら有力な国衆は婚姻や名前の下賜などで自勢力に取り込んだり外縁部に配して小さな戦闘は国衆達に任せ戦費を減らしたり独自の縁を利用した敵の国衆の取り込みや敵勢力との交渉などに力を発揮させていた。どうすれば少勢力で生き残れるのか手本になりそう2022/08/21
nagoyan
22
優。関東戦国史研究をリードし、国衆論を開拓してきた著者が、初めて、一般向けに「国衆」を解説したもの。国衆は戦国時代に現れた地方領域「国家」の領主とも言うべき存在で、本質的には戦国大名と同じである。戦国大名の勢力圏の境界地帯に多く存在し、戦国大名から庇護を受けると同時に軍役などを負担するが、領内統治の自主性は失わなかった。しかし、国衆から戦国大名へ移行できたのは徳川氏や毛利氏など僅かな例しかなく。戦国大名は守護大名か守護権力の代行者(守護代や守護大名の一族、家宰など)を出自に持つものの方が多かった。2023/01/17
ようはん
21
規模的には戦国大名とは言い難い、むしろある程度独立した統治を認められるも戦国大名に従い軍役等を負担し、時には所属を変えて生き抜いてきた地方豪族達を昔は国人と呼んできたけど今は国衆と呼ぶのが主流。国衆の大スターはやはり本書でも取り上げられる真田昌幸であろうか。巧みに所属を変えながら勢力を拡大していく姿は惚れ惚れするが同じ国衆の出自から戦国大名、天下人となる家康により九度山に追い込まれ、不遇の最期を遂げたのが物悲しい。2025/06/05
MUNEKAZ
21
「国衆」論をリードしてきた著者による一冊。国衆の定義や研究史を語る前半はやや難解だが、横瀬・由良家や真田家など東国の国衆を例にその実態を紹介する後半は読みやすい。排他的な一円支配を行いながらも、軍事・外交面では戦国大名に従属する存在であること。また従属先の決定はあくまで国衆側の選択に拠っており、戦国大名の勢力が衰えれば、他勢力への寝返りが頻発し、ひいては戦国大名家の崩壊に至ることなどが具体的に描かれている。他に国衆から戦国大名へ変化した例も紹介されており、改めて毛利元就の成り上がりの凄さに驚かされる。2022/05/12
-
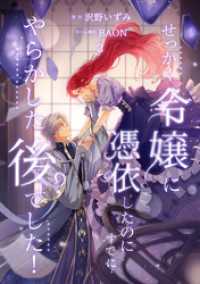
- 電子書籍
- せっかく令嬢に憑依したのにすでにやらか…