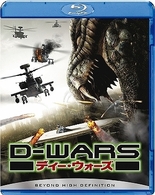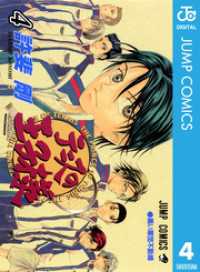- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
日本語の起源は古代中国語にあった。古代中国語音と古代日本語(ヤマトコトバ)の音の対応を、百話にまとめた実例で検証。弥生時代以来の「伝統的造語法」、そして新たに登場した「新型造語法」を考察し、さらに『古事記』の天地初発の話から欠史八代の記事までに現れる神名や地名の語源を探る。これにより日本語の古層は中国語と共通のものだったことが見えてくる。ユーラシア全体の言語への広い視野と、細かい語彙の変遷を跡づける深い知識によって裏打ちされた新説提唱の試み。
目次
上古漢語の特殊な音と音表記
序章 日本語の起源・総論
1 先学たちの日本語系統論
北方起源説
北方語と南方語の重層説
チベット・ビルマ語起源説
タミル語起源説
日本語古層説
2 新しい日本語系統論に向けて
第1章 伝統的造語法
はじめに
一対一対応の漢語と和語
二対一対応の漢語と和語
三対一、四対一対応の漢語と和語
第1話 マチ(町・街・坊)とムラ(村)
第2話 トモ(伴・供・共)とトモ(友)
第3話 マツ(松)とマツ(待つ)
第4話 クスリ(薬)とブス(附子)
第5話 ムカデ(百足)とトカゲ(蜥蜴)
第6話 タヅ(田鶴・鶴)とツル(鶴)
第7話 サギ(鷺)とウサギ(兎)
第8話 ツカサ(高処・阜)とツカサ(首・司・官)
第9話 シカ(鹿)とアシカ(海鹿・葦鹿)
第10話 イモ(妹)とセコ(兄子・夫子・背子)
第11話 イカヅチ(雷)とイナヅマ(稲妻)
第12話 アソブ(遊ぶ)とスサブ(遊ぶ・荒ぶ)
第13話 ムツキ(睦月)とシハス(師走)
第14話 イトド(いとど)とハナハダ(甚)
第15話 ミヅ(水)とソラ(空)
第16話 ナミ(波)とナゴリ(名残)
第17話 マボロシ(幻)とウツツ(現)
第18話 イノチ(命)とウツソミ(うつそみ)
第19話 クジ(籤)とウラナヒ(占ひ)
第20話 キササ( )とシラミ(蝨)
第21話 ツマ(端)とツマ(妻・夫)
第22話 ミミ(耳)とキク(聞く)
第23話 ココロ(心)とタマシヒ(魂)
第24話 サクラ(桜)とサクラマス(桜鱒)
第25話 トフ(問ふ・訪ふ)とコタフ(答ふ・応ふ)
第26話 カタミ(形見)とカタミ(互)
第27話 クフ(食ふ)とクラフ(食らふ)
第28話 ツガフ(継がふ・番ふ)とタグフ(偶ふ)
第29話 ヲサ(長)とヲサ(訳語・通事)
第30話 サヲ(さ青)とサメ(雨)
第31話 キツネ(狐)とワタツミ(海神・海)
第32話 ヲトコ(男)とヲトメ(少女・処女・乙女)
第33話 ミヲビキ(水脈引き)とミヲツクシ(澪標)
第34話 ヤウヤク(漸く)とヤガテ(軈)
第35話 サスラフ(流離ふ)とサマヨフ(彷徨ふ)
第36話 スバル(昴)とユフツヅ(夕星)
第37話 ヤギ(山羊)とヒツジ(羊)
第2章 新型造語法
はじめに
三対一対応の漢語と和語
四対一対応の漢語と和語
第38話 ハラ(腹)とハラム(孕む)
第39話 スコブル(頗)とヒタブル(一向)
第40話 ミチ(道)とチマタ(巷)
第41話 タビ(旅)とタムク(手向く)
第42話 ミモロ(三諸・御諸)とヒモロキ(神籬)
第43話 トシ(年・歳)とサヘク(さへく)
第44話 シシクシロ(宍串ろ)とミスマル(御統)
第45話 トリヰ(鳥居)とシルベ(導・指南)
第46話 ヒバリ(雲雀)とホトトギス(時鳥)
第47話 クヂラ(鯨)とイサナ(勇魚)
第48話 キリギリス(蟋蟀)とコホロギ(蟋蟀)
第49話 コトバ(詞・言葉)とコトワリ(理・断り)
第50話 カタラフ(語らふ)とカザラフ(飾らふ)
第51話 モチ(望)とイサヨヒ(十六夜)
第52話 ナリハヒ(生業)とイトナミ(営み)
第53話 ニヘ(贄)とニヒナヘ(新嘗)
第54話 アキナフ(商ふ)とオコナフ(行なふ)
第55話 ツハモノ(兵)とモノノフ(物部・武士)
第56話 ツブリ(頭)とカタツブリ(蝸)
第57話 サガム(相模)とサネサシ(さねさし)
第58話 サンマ(秋刀魚)とスルメ(鯣)
第59話 ミゾレ(霙)とアラレ(霰)
第60話 カゼ(風)とアラシ(嵐)
第61話 ベニ(紅)とムラサキ(紫)
第62話 トドロク(轟く)とクハバラ(桑原)
第63話 クサカ(草香)とクサカ(日下)
第64話 トコシヘ(永久)とトコシナヘ(永久)
第65話 タヒラ(平)とハラ(原)
第66話 ウチアゲ(打ち上げ)とウタゲ(宴)
第67話 ヲミナヘシ(女郎花)とスミレ(菫)
第68話 ミサト(京)とミヤコ(都)
第69話 イラカ(甍)とハシラ(柱)
第70話 カヌマヅク(かぬまづく)とオタハフ(おたはふ)
第71話 モロミ(醪)とヒシホ(醢・ⅸ)
第72話 ニジ(虹)とニシキ(錦)
第73話 サゴロモ(さ衣)とツバクラメ(燕)
第74話 サワラビ(さ蕨)とツクヅクシ(土筆)
第75話 カモメ( )とウタカタ(泡沫)
第3章 古事記神話の超新型造語法
はじめに
第76話 天地初発の神
第77話 神世七代の神
第78話 オノゴロ島を生む
第79話 ヒルコとアハ島を生む
第80話 大八嶋国を生む①
第81話 大八嶋国を生む②
第82話 六嶋を生む
第83話 神々を生む
第84話 イザナミの死
第85話 脱出するイザナキ
第86話 三貴子の誕生
第87話 天岩屋の出来事
第88話 追放されたスサノヲ
第89話 ヤマタノヲロチの退治
第90話 オホクニヌシの誕生
第91話 稲羽の素兎の話
第92話 ヤソカミの迫害を受ける
第93話 試練を潜り抜ける
第94話 オホクニヌシの国作り
第95話 高/rt>天原の使者たち
第96話 雉のナキメとアメノワカヒコの死
第97話 オホクニヌシの国譲り
第98話 天孫の降臨
第99話 海幸と山幸の話
第100話 作り話は続く
あとがき
主要参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
伝奇羊
mft
takao
Go Extreme