- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
会社を始めとする多くの組織で発生する様々な不正が、毎日のように新聞やテレビで報じられています。
不正をはたらく動機もしくは不正をはたらかなければならないほどのプレッシャーがあり、不正をはたらいても発見されにくい組織体制であり、かつ不正をはたらいても許されるはずだと考えられる素地が組織内にある場合に不正は起きやすいと言われます。
不正には様々なものがありますが、①資産の流用、②不正な報告、③汚職の3 つに類型化した場合、①資産の流用が8 割を超えるといわれます。
資産の流用は、いかなる理由があるにせよ、流用をはたらいた本人はもとより、組織、組織の従業員、社会に損失をもたらします。
資産の流用により、組織は財務的な損失を被るし、従業員が流用をはたらいたことの報道等による組織のイメージダウンによって業績の低迷を招きかねません。
流用をはたらいた従業員が所属する組織の他の従業員は、組織が財務的損失を被ったことにより昇給や賞与の面て抑制を強いられ、世評の悪化により肩身の狭い思いをします。
社会も無縁ではありません。国民の相互信頼の度合いが低下し、組織の新たな統治体制の構築などの社会的費用を負担しなければならない恐れがあります。
本書は資産の流用の事例を取り上げ、それが組織の経営、特に財務面に与える影響を会計思考で見える化したものです。同時にその背景を探り、再発防止の仕組みを提案しています。
本書では資産の流用を、窃盗・横領、不正使用、経費の水増し、不正な財務報告の4 つのカテゴリーに分類しています。不正な財務報告は直接的に資産を流用するものではありませんが、自分の報酬や地位、待遇などを維持するために行うものであり、間接的に資産の流出に結び付くと思われることから、1 つのカテゴリーとしました。
本書が、管理職の皆様方が資産の流用の事例と影響を知り、その再発防止の仕組み作りに必要な知識を習得するきっかけになれば幸いです。
目次
プロローグ
■第1 章 資産の窃盗・横領のカテゴリー
事件1:帳簿と通帳の残高が違う
事件2:破棄された領収書
事件3:簿外資産の売却
事件4:商品の横流し
事件5:辞めた社員の給与を着服
事件6:ニセの銀行口座への送金
■第2 章 資産の不正使用のカテゴリー
事件7:資産・設備の業務外使用
事件8:消えた有価証券
事件9:不動産の転貸で賃料を着服
■第3 章 経費の水増しのカテゴリー
事件10:禁止されたバック・マージンの授受
事件11:キック・バックの要求
事件12:領収書の改ざん
事件13:業務に関係ない支出
■第4 章 不正な財務報告のカテゴリー
事件14:商品在庫情報の改ざん
事件15:商品の含み損の隠ぺい
事件16:回収困難な売掛金を隠す
事件17:帳簿に無い借入金
事件18:ペーパー会社への売上
事件19:架空循環取引の兆候
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Mik.Vicky
ぺす
-
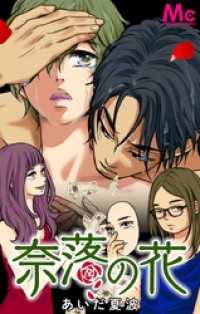
- 電子書籍
- 奈落の花【タテヨミ】 5 マーガレット…
-
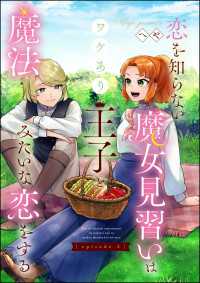
- 電子書籍
- 恋を知らない魔女見習いはワケあり王子と…
-
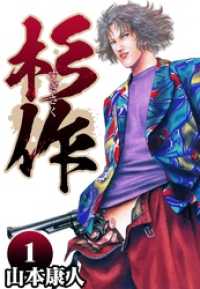
- 電子書籍
- 杉作 1 SMART COMICS
-
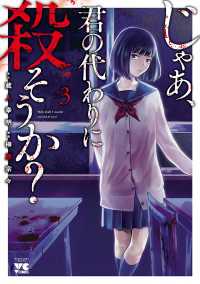
- 電子書籍
- じゃあ、君の代わりに殺そうか?【電子単…





