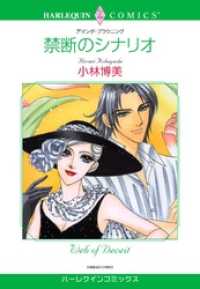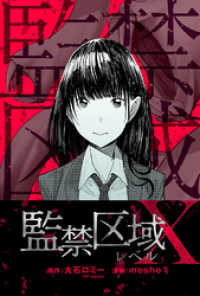内容説明
日本社会が露呈しているほころびとはどのようなものか.どんな方向に軌道修正をしていけばよいのか.教育・仕事・家族という三領域がきわめて強固で一方向的な矢印で結合し,循環していた従来の日本的社会モデルが破綻するまでのプロセスと要因を分析し,それにかわる新しい社会像をうち出す.「社会を結びなおす」ための見取り図.
目次
はじめに┴第1章 相模原事件の波紋┴第2章 障害当事者は事件をどう受けとめたのか┴第3章 ナチス・ドイツの「T4作戦」┴第4章 ヘイトクライムの「拡大・連鎖」の根を絶つために┴おわりに┴資料 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)(抄)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
27
ポイントは明朝太字。 社会の内外にわかりやすい 原因や敵を無理矢理見つけ出して 叩くことでうっぷんを晴らそうと するようなふるまい(3頁)。 産めよ発言、小保方さん問題、 各種Twitter炎上など、枚挙に暇がない。 戦後日本の3つの時期という 時系列データは複合要因の 変容がわかる優れもの(7頁)。 ニートやフリーター問題は 若者の甘え、劣化ではない(13頁)。 今や、SNEP中年無業問題と転化 してきており、これも同様だ。 2014/06/22
koromo
26
今回の提唱で目新しいのは「アクティベーション」。本田さんはこの著書をあくまで社会の見取り図を共有するための議論喚起と位置づけている。だから私もあえて自分の考えを述べるとすれば、やはり「アクティベーション」の段階における行動認知が重要だということ。自らを知覚すること。先日の新幹線の事件もそうだけれど、社会の枠組みから放り出されそうな人にとって、自分の日常行動を合理的に見つめ直すプログラムが必要になってくる。一方で、合理的思考が出来ない人は一定数いることを考えると、やはりベーシックインカムは必要なのだと思う。2015/07/22
shikada
24
現代日本は、戦後の仕事・家族・教育のモデルをアップデートせずに引きずっている。そのために閉塞感が生じている。「戦後日本型循環モデル」=正社員の男性が稼ぎ、専業主婦の女性が家庭を守り、子供は新卒一冊採用で入社するモデル。このモデルは高度経済成長時代に限って成立したもの。バブル崩壊後、低成長で非正規雇用が増えた現代では通用しない。なぜこのモデルが欧米などでは生じず、日本でのみ特異に発達したのか、また世代ごとの比較(団塊・団塊ジュニア・就職氷河期)などが50ページという薄さのなかにすっきり整理されていた。2019/06/29
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
24
【15/11/04】教育→仕事→家庭→と、社会の三領域が一方向のベクトルで資源を循環させていた「戦後日本型循環モデル」が軋んできていることを指摘し、これを双方向で支え合うモデルへと転換させることが急務であるとする、骨太の論考。図書館本であるために駆け足で読んだが、購入してでも再読に値する一書。2015/11/04
シュシュ
23
お父さんが働いてお母さんは専業主婦で子どもが平均二人という、自分が子どもだった1960~1970年代。この時代は、いろいろな条件が揃っていたからこそ安定していたのだということが初めてわかった。現代には、あの頃のような条件はないし、これからもないから、価値観を変えていかないといけない。でも、子育てはお母さんがするもので、お父さんが一家を養うという昔のイメージを捨てきれない人も、私の世代ではまだいる気がする。とても勉強になった。「学校が家族のケアの窓口に」という案がよかった。国はもっと教育費を増やしてほしい。2015/05/24