内容説明
日本ほどものまね芸が好まれた国はない。我が国では、ものまね芸は独自の発展を遂げたうえ、能・狂言・歌舞伎・落語などの芸能や文学の底流となってきた。人間だけでなく、神仏や動物・草木などあらゆるものが巧みにまねされ、こんにちのものまね芸の隆盛にいたる。その源流と展開の歴史を、仏教芸能との関わりに着目して描いた初めての試み。
目次
ものまねと仏教と諸芸能―プロローグ/アジア諸国のものまね(インドのものまね/中国のものまね/韓国のものまね)/古代日本のものまね(伎楽と散楽の伝来/寺院と宮中、そして市中へ)/ものまねの独立と寺院芸能(ものまねの流行/寺院でのものまね)/ものまねから能・狂言へ(延年の盛行/仏菩薩に扮する儀礼/狂言の成立/能の確立/素人の活躍)/花開く江戸の歌舞伎と声色(歌舞伎の流行/ものまね専門の芸人/歌舞伎と仏像ものまね/役者のものまねの流行)/拡張していくものまね(落語とものまね/ものまねの大流行/声色本の流行/百面相の流行/ものまね興行と流しの声色遣い)/ものまねの近代化(新しいメディアとものまね/現代のものまねの先駆/現在のものまねの源流)/変化と伝統―エピローグ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
6
古代から現代までカバーしており、来迎の阿弥陀如来コスプレから、タモリのイグアナまで言及あり。仏像のものまねってのはあんまし考えたことなかったなぁ。江戸時代には歌舞伎役者のまねがメジャー。明治以降はメディアが拡大してゆき、浪曲やらラジオ番組やらになってゆく。「百面相」っては、紙で作った目だけお面を使ったものまね芸らしい。2017/07/17
スプリント
3
能や狂言・歌舞伎・落語など古典芸能から発生したものまねの歴史だけでなく仏教でのものまねについても取り上げられており知見を深められました。2017/07/08
河村祐介
2
本の内容としては説話とセットな仏教芸能としての猿楽や狂言、能のなかでの表現としてのモノマネが主なところ。でもやっぱり、大衆芸能のなかで一気に花開く江戸以降のモノマネが面白い。2017/08/26
あっちー
1
先日受講した先生の著作。講座の時に話してらしたご自身のメインの研究テーマ、仏教と芸能について。 ものまねはお笑いや番組でも人気だが、それがどこから発生して今に至るか、を分かりやすく解説されている。 テレビもネットもない時代は、人気の役者や演目を実際に見られるのは本当に一握りの人だけ。ものまねは最も身近な娯楽だったろう。2019/07/06
-
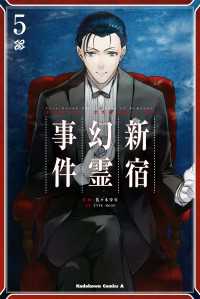
- 電子書籍
- Fate/Grand Order ‐E…
-

- 電子書籍
- 月下美人 ブラックショコラ







