内容説明
古来、楽器には神威が宿り、王権を象徴する道具と認識されてきた。前近代の天皇は幼少より管絃の習得を積み、どの楽器を演奏するかは、時には皇統の在り方をも左右した。宮廷内での権力闘争や武家との覇権争いを有利に導くための楽器選択など、音楽と天皇の権威との関わりや帝器の変遷を、古代・中世の天皇の音楽事績を紹介しつつ明らかにする。
目次
帝王学としての音楽―プロローグ/古墳時代から奈良時代〈大王によるコトの演奏/日本古来の歌舞/大陸からの楽舞の伝来/雅楽の成立〉/平安時代(琴の時代〈桓武天皇とその子孫/仁明天皇とその子孫/宇多天皇/醍醐天皇/村上天皇/宮廷音楽の広がり〉以下細目略/笛の時代)/鎌倉時代(琵琶の時代/両統迭立期の帝器)/室町時代(皇統分立と帝器/笙の時代/笙と箏の時代)/その後の天皇と音楽―エピローグ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白隠禅師ファン
20
数日前に豊永聡美『天皇の音楽史』を読了した。天皇と楽器の関わりの変遷から、各々の天皇の権威のありかたを見ていく、両統迭立期に、持明院統は琵琶、大覚寺統は笛を帝器をそれぞれ重んじており、後醍醐天皇は笛、謡物だけでなく持明院統の帝器の琵琶も用い、さらに数々の秘曲を演奏するという多芸多才さをみせ、琵琶「啄木」の奥秘事の伝受の際、後伏見院が、とうとう琵琶道も後醍醐に支配されたかと日記に記しているのが面白い。こうした後醍醐天皇の帝器の執着は、倒幕の成就の祈願のためであったという。良い読書体験でした。2025/10/13
秋色の服(旧カットマン)
4
長い歴史の中で、天皇には色々な顔(役割)がある。祭祀の長、武人、歌人、そしてこの本に紹介されている楽人としての顔。我々は明治維新以後の天皇像で天皇制のことを考えすぎていないだろうか。まぁ歌人としての顔は新年の歌会始とかで周知されているだろう。だが、かつては雅楽の楽器のみならず、琵琶など最新の楽器を帝王学の一環としてたしなむミュージシャンだったのだ。2018/07/24
はちめ
3
どんな内容かと思ったらタイトル通り歴代天皇がどのように楽器に関わったかということが延々書いてあります。ただし室町時代までですが。そもそもほぼ全ての天皇が特定の楽器を弾いていたことがかなりの驚きであるし、時には楽器の選択が歴史に大きな意味をもたらしたということもびっくりした。専門家の仕事のありがたさを感じる1冊です。2017/02/19
読書記録(2018/10~)
0
帝器といえば琴・箏や琵琶などの弦楽器の印象だが、笛(やはり龍笛に限る!)も一時代を築いており、また笙もそうであったのは驚いた。特に詳細なうえに政治的な思惑の絡んだ南北朝~室町時代が面白く読めた。笙の登場には深い事情があり、本来傍系のはずの後光厳天皇から始まるなど。琵琶は本来の正統になるはずであった、伏見宮家に伝えられていく。琵琶への対抗として採り入れられた箏を加え、そこからなんと孝明天皇まで笙と箏は続いていく。2025/08/05
-

- 電子書籍
- 三栄ムック 自衛隊新戦力図鑑2025
-
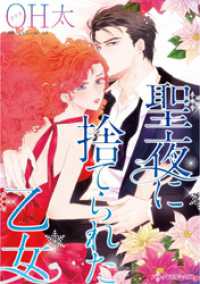
- 電子書籍
- 聖夜に捨てられた乙女【分冊】 11巻 …
-
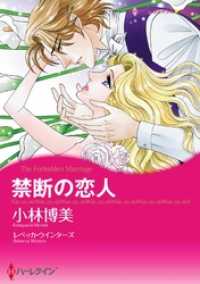
- 電子書籍
- 禁断の恋人【分冊】 10巻 ハーレクイ…
-
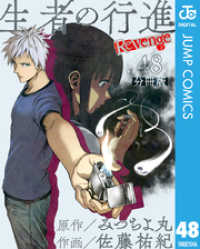
- 電子書籍
- 生者の行進 Revenge 分冊版 第…
-

- 電子書籍
- 高橋和巳・高橋たか子 電子全集 第5巻…




