内容説明
福祉制度が実動しないタンザニアで、「ふつう」に働けない障害者たちは、いかに生計を立ててきたのか。植民地期から現在までの彼らの姿を追う。障害学、都市下層研究、地域研究の枠組を越え、路上に「居る」障害者たちの生活世界を描く。
目次
はしがき
序章 「当たり前」に目を向ける――現代アフリカ都市における不揃いな身体
第一部 植民地主義と「障害者」の構築
第1章 「障害者」と近代、世界
第2章 イギリス領タンガニーカ行政にとっての「障害」概念
第3章 「肢体障害者」と「アルビノ」の出現
第二部 都市的生活――移住し、稼ぎ、人と繋がる
第4章 ダルエスサラームでの対人調査概要
第5章 都市移住、家族関係、ケアへのアクセス
第6章 親族に頼らない、頼れない移住
第7章 物乞いに支えられる家計と従事者の葛藤
第8章 他人を身内に――持続的関係を創る相互行為としての物乞い
終章 「彼ら」と「私たち」の境界はどこにあるか
注
あとがき
引用文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
52
一元的にシステム化された公共福祉支援が行き渡っていなく、第一次産業が中心のアフリカ。だからこそ、不揃いな体を持つ人々は社会に隠されることなく、様々な形で身を立てる。家族の助けがあって街に出て生計を立てる人もいれば、家族とは断絶して自立のために街に飛び出た人もいる。「職を紹介しても物乞い業に戻るのは何故か」への獲得金額データの補完に対し、物乞いをする人はその事実を隠したがっているという心理的葛藤に胸打たれる。また、注釈は多いですが、出来事の背景・根幹にある歴史や法、アフリカの文化などの説明なので助かります。2022/08/21
かやは
8
学術的に正確を期すためか、かなり丁寧かつ具体的に説明してくれるので、私のような一般的な読者には読みづらい。でも著者の真摯さが伝わったので通読できた。タンザニアの最大都市、ダルエスサラームで暮らす身体障害者の生活を綴った一冊。国の福祉が不十分なので、周りと助け合うことが前提となった生活。物乞いも仕事の一つとして成立していて、その収入で一般家庭と同じような支出だということもあるのは驚いた。ただ物乞いを恥すべきものとする感覚はある。物乞いは、「願わくは人生時間からカッコでくくり出したい時間」だという。2024/06/09
takao
3
ふむ2022/10/25
のりえ
1
🔻脚注?注意書き?補足説明?が文中に多用されておりメンドクサイ。読みにくい。 本書の試みは『アフリカで生きる「五体不満足」な人々という「特殊な」「他者」の生活ぶりを描くことである、と同時に、それを見ることを通して、私たちがかけている色眼鏡の存在を浮かび上がらせること』だそうです。2022/07/29
鮭
0
何故か勝手にアフリカの障碍者の方とのインタビューや交流を描いたルポ的な本をイメージしていたけど、論文に加筆修正したもので、少し私には堅く感じてしまった…。しかし紹介されている障碍者の"物乞い"の人の生活や、彼らに友人のように接する街の人々の様子は興味深く読めた。一方、半身不随になった田舎の子どもが這って通学していた等、辛いエピソードも沢山あり、良くも悪くも日本との違いが衝撃だった。2023/01/31
-
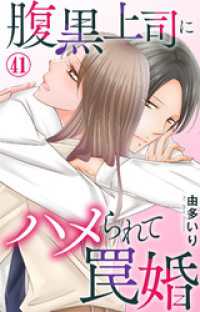
- 電子書籍
- 腹黒上司にハメられて罠婚 41 素敵な…
-
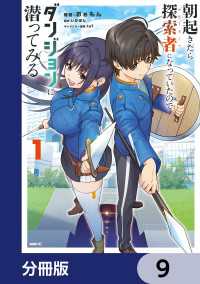
- 電子書籍
- 朝起きたら探索者になっていたのでダンジ…







