内容説明
人づきあいが苦手な「コミュ障」(コミュニケーション障害)。この呼び名で、あなたは自虐的に振る舞っていますか? それとも知人をからかっていますか? 悩みを抱える読者は自分自身のメンタルを掘り下げる心理学に関心があるかもしれません。しかし、本書は「社会学」という道具を使って、自分の視野を広げて「壁」を取り払うためのポイントを紹介します。私たちは、なんらかの情報や知識、あるいは年齢や職種といった属性から、異なる「メガネ」をかけています。このメガネの存在に気づかせてくれるのが社会学の諸理論というわけです。また、著者自身が他者と分かち合えなかった具体的なエピソードを絡めながら、少しずつ自分の見方を広げていく知の旅を提供します。著者は「岩本先生の授業が一番人気の理由がわかった」と内田樹氏からもお墨付きをもらった人気講師。面白くてためになる白熱教室へようこそ!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たかこ
43
面白かったし、本当に勉強になりました。コミュ障をどうやって改善するのか、というようなハウツー本ではなくて、コミュ障の正体を社会学の知見をもとに明らかにしたもの。「同じものを見ていても、自分とは違った風景を眺めている人たちに思いを馳せる」。本当に、私たちは目の前で生じる出来事に対して色眼鏡で見ている。自分の視野を広げることによって、異なる信条や考えの人の存在を理解していくことが、自らの心の壁が外につながっていき、コミュニケーションが取れることにつながるのだと思う。社会学的思考で自分の心を豊かにしていく。2023/03/08
Mc6ρ助
11
社内に対しても感情労働が要求される今の日本、単にコミュニケーション能力というよりは著者のいうコミュニケーション資本(p62)の方が目減りや枯渇などと理解しやすい。『・・ファストフード店ではマニュアルに沿った対応・・本来は労働の対価が生じない笑みや、「ご注文は以上でよろしかったでしょうか」などと・・終始微笑みを浮かべて対応するキャビンアテンダント(CA) を例に・・「感情労働」という感情表現の労働が大きなウエイトを占める時代になったことを社会学者のアーリー・R・ホックシールドも指摘しています。(p61)』2022/08/10
四葉
3
「コミュ障」克服の本ではなくて、コミュ障でも社会学的に物事を別の角度から見てみる習慣を得れば、社会と面白く関わっていけるよ、みたいなちょっと変わった本でした。コミュ障に関係なく「社会学に見る」とはどうゆうことかを、とても親しみやすい文章で書いてあります。ただ内容を深く理解するにはあと2回ぐらい深く読みこまないと難しいなと感じました。芸術家のスキャンダルによって、素晴らしい作品がお蔵入りしてしまう昨今、もう一度これまでの歴史を紐解きながら考え直すときが来ているかもと思いました。2023/07/25
rakuda
2
社会学という学問か何なのかほとんど知らないまま読んだのですが、とてもわかりやすく興味深く読めた。社会学的な見方も少し理解できた(と思う)。2022/09/04
のりえ
2
🔻同じものを見ていても自分とは違った風景を眺めている人たちに思いを馳せることをベースに、コミュニケーションの「壁」を取り払うことを目指す。 …思っていたのと違いました。2022/08/03
-

- 電子書籍
- 全スキル複製能力で残業時間999→ゼロ…
-
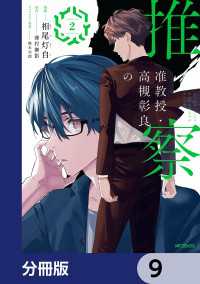
- 電子書籍
- 准教授・高槻彰良の推察【分冊版】 9 …
-

- 電子書籍
- カノジョに浮気されていた俺が、小悪魔な…
-

- 電子書籍
- 正義の学園【単話】(14) マンガワン…
-

- 電子書籍
- お女ヤン!! イケメン☆ヤンキー☆パラ…




