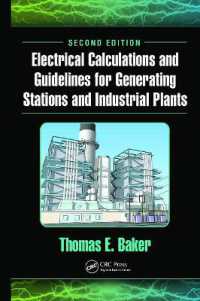内容説明
長い戦乱をへて平和がもたらされた近世とは,世代から世代へと〈知〉を文字によって学び伝えてゆく時代の到来であり,そうした「教育社会」こそが,個性豊かな思想家を生みだした.朱子学から,山崎闇斎,伊藤仁斎,荻生徂徠,貝原益軒,心学,そして国学まで,〈学び〉と〈メディア〉の視点から広くみわたす江戸思想史入門.
目次
序章 知のつくられかた┴「型の喪失」/素読世代/近代学校の始まり/学校教育の知/学校教育と教養派知識人/知の身体性/アジアの思想伝統の不在/メディアの視点から┴第一章 「教育社会」の成立と儒学の学び┴1 文字の普及と文字文化┴文字社会の成立/江戸時代の文字使用/都市の発展と商業/手習塾の登場/「書礼」の学習/御家流/文字文化の共通化┴2 商業出版の登場┴一七世紀日本のメディア革命/声と文字の交錯/学びのテキスト/和刻本┴3 儒学の学び┴科挙のない社会/民衆の学問志向/素読 漢文で考える/テキストの身体化/訓読体漢文の言語/儒学の学習法/日本近世の〈知のつくられかた〉┴4 「教育社会」の成立┴「教育社会」とは/手習塾と学問塾/郷学/近世教育の豊かさ┴第二章 明代朱子学と山崎闇斎 四書学の受容から体認自得へ┴1 四書学の受容 江戸前期の朱子学者たち┴読めない漢籍をいかに読むか/明代の四書学/四書学本の受容/訓読テキストへの変換┴2 山崎闇斎 文字を超えた「講釈」の学┴末疏の書の排斥/『闢異』 排仏論/朱子学とは/闇斎の朱子学/「心」の確立を求めて/幕藩領主や武士層への浸透/闇斎の語り口/思想の方法としての「講釈」┴第三章 伊藤仁斎と荻生徂徠 読書・看書・会読┴1 伊藤仁斎 独習と会読┴闇斎と仁斎/町衆文化の中心圏/儒学への志/「敬」との決別 「仁斎」の誕生/否定的媒介としての闇斎学/同志会での学び┴2 「論語空間」の発見┴「人倫日用」の学/「最上至極宇宙第一論語」/仁斎の『論語』解釈の方法/浅見絅斎の仁斎批判/仁斎学のメディア┴3 荻生徂徠 学問の方法をめぐって┴闇斎学と仁斎学に対抗して/荻生徂徠という人/講釈十害論 闇斎学への違和感/読めない漢文をどう読むか/読書法/看書という方法/徂徠学の成立 「安天下の道」/「道」のパラダイム転換/古文辞学との出会い/「習熟」/知の発信メディア┴第四章 貝原益軒のメディア戦略 商業出版と読者┴1 益軒の学びと学問┴貝原益軒とはだれか/独学自習の体験/知のネットワーク/「民生日用」┴2 「天地につかえる」思想┴「事天地」の説/「民生日用」と「術」の学/「礼」という身体技法┴3 益軒本の読者┴益軒本/読者にとっての益軒本/読書する民衆/読者とメディア┴第五章 石田梅岩と石門心学 声の復権┴メディア革命のなかで┴1 石田梅岩の学び┴梅岩の志/梅岩の学び┴2 開悟からの語り出し┴開悟体験/開悟体験を拠り所に/文字への不信/「声の復権」を誘引したもの/著作の出版と「学問」の意味転換┴3 石門心学の創出┴梅岩の講釈/後継者・手島堵庵/石門心学の組織化/会輔 心学者の学び/教化方法の革新 前訓と出版┴4 「道話」の発明┴心学道話 マス・ローグの語り/道話の語り/語りの技法/石門心学へのまなざし┴5 石門心学の歴史的位置┴儒学の教説化とそのメディア/寛政改革と石門心学/政治のメディア┴第六章 本居宣長と平田篤胤 国学における文字と声┴漢学に抗して┴1 儒学の学問圏からの脱出┴京都への遊学/漢文から和文へ/儒学的思考からの脱却/和歌詠歌と音声言語/『古事記』の発見/〈やまとことば〉の復元作業┴2 声の共同性┴歌の力/二つの歌会 和歌に託したもの┴3 宣長の知のメディア┴書斎の知識人/声と文字の相克┴4 平田国学における声と文字┴平田篤胤 宣長没後の門人/『霊能真柱』 霊の行方と「安定」/篤胤の危機認識/欧米列強の接近┴5 講釈講説家・篤胤の登場┴神職支配をめぐる吉田家と白川家/講釈家・篤胤/講釈聞書本/篤胤にとっての出版 『古史成文』がめざしたこと/門弟たちにとっての出版/メディアの駆動力┴終 章 江戸の学びとその行方 幕末から明治へ┴江戸の学びの視点から┴1 明六社 漢学世代の洋学受容┴明六社の創設/明六社というメディア┴2 中村敬宇┴ロンドンでの素読/漢学廃すべからず┴3 中江兆民┴漢学の学び直し/『民約訳解』の漢文翻訳┴4 「型」と自己形成┴自己形成の拠り所/地球環境危機のなかで┴5 メディア革命と知の変容┴近代の知のメディア/二一世紀のメディア革命/近代の終焉と知の行方┴あとがき┴主要参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
肉尊
ころこ
崩紫サロメ
おおにし