内容説明
現代の色彩豊かな視覚環境の下ではほとんど意識されないが,私たちが認識する「自然な(あるべき)」色の多くは,経済・政治・社会の複雑な絡み合いの中で歴史的に構築されたものである.食べ物の色に焦点を当て,資本主義の発展とともに色の持つ意味や価値がどのように変化してきたのかを,感覚史研究の実践によりひもとく.
目次
まえがき┴第一部 近代視覚文化の誕生┴第一章 感覚の帝国┴味と色の瞑想/大量生産時代の到来/感覚産業複合体┴第二章 色と科学とモダニティ┴消費資本主義の台頭と色彩革命/色彩科学と色の客体化/色のプロフェッショナルの誕生/複製技術と味覚の表象/文字から絵,モノクロからカラーへ/「自然」な色の再現┴第三章 産業と政府が作り出す色 食品着色ビジネスの誕生┴合成着色料の誕生/産業化する食品着色ビジネス/食品規制が作り出す市場/「おいしそう」は安全か?/赤色の恐怖┴【コラム】食品サンプル┴第二部 食品の色が作られる「場」┴第四章 農場の工場化┴「自然な」色の構築/オレンジ産業にみる色と競争優位/オレンジは何色か?/自然と人工の境界┴第五章 フェイク・フード┴黄色いバターと白いバター/人造バターが脅かす酪農産業/自然の黄色は誰のもの?/偽物を真似る本物/マーガリンの「自然な」色/カラー・ポリティクス┴第六章 近代消費主義が彩る食卓┴料理本が教えるおいしい色/美しい料理と良妻賢母イデオロギー/色が映す人種と階級/パッケージ化される女性像/便利すぎる商品/インスタント食材とクリエイティビティ┴【コラム】和菓子の美学┴第七章 視覚装置としてのスーパーマーケット┴セルフサービス黎明期の魅せる陳列/スペクタクル化する食品/スーパーマーケットの技術革命/透明性が隠すもの/個人化する買い物と視覚性┴第三部 視覚優位の崩壊?┴第八章 大量消費社会と揺らぐ自然観┴戦後の豊かさと綻び/アースカラーの対抗文化/新しい「自然」の発見/「自然」回帰┴【コラム】教育からエンタメへ┴第九章 ヴァーチャルな視覚┴ネットスーパー/記号化する食/SNSの誕生/揺らぐプロとアマの境界/コンシューマーからプロシューマーへ/「盛る」ための写真/情動を引き出す食┴あとがき 感覚論的転回┴注
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Porco
Urmnaf
oooともろー
May
おっきぃ
-

- 電子書籍
- 週刊プロレス 2020年 12/16号…
-

- 電子書籍
- 幽霊の見える公爵夫人【タテヨミ】第89…
-

- 電子書籍
- 鉄道ファン2023年11月号
-
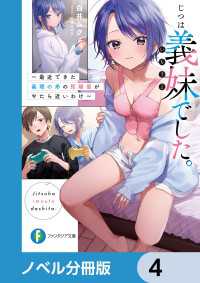
- 電子書籍
- じつは義妹でした。【ノベル分冊版】 4…
-

- 電子書籍
- 老後の誤算 日本とドイツ




