- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
誰にも訪れる「死」。しかし、実際にどのようにして死んでいくのかを知っている人は少ない。人がどのような末期を知らないと、虐待に等しい終末期医療に苦しみ、悲惨な死を迎えることになりかねない。肉親が迎えたとき、そして自ら死を覚悟したとき、どのような死に方を選べばいいのか。在宅診療医として数々の死を看取った、作家の久坂部羊氏が、人がどのような死を迎えるのかをリアルに描き、安らかな死を迎えるために、私たちが知っておくべきことを解説する。その日に備えて、読んでおきたい「死の教科書」
はじめに
第一章 死の実際を見る、心にゆとりを持って
第二章 さまざまな死のパターン
第三章 海外の「死」見聞録
第四章 死の恐怖とは何か
第五章 死に目に会うことの意味
第六章 不愉快な事実は伝えないメディア
第七章 がんに関する世間の誤解
第八章 安楽死と尊厳死の是々非々
第九章 上手な最期を迎えるには
目次
はじめに
第一章 死の実際を見る、心にゆとりを持って
死を見る機会 死の判定とは 死のポイント・オブ・ノーリターン 看取りの作法 死に際して行う「儀式」 死には三つの種類がある 脳死のダブルスタンダード
第二章 さまざまな死のパターン
はじめての看取り 悲惨な延命治療 延命治療はいらないと言う人へ 延命治療で助かることも 江戸時代のような看取り 在宅での看取りの失敗例 望ましい看取り 在宅での看取りに不安とハードル 死を受け入れることの効用
第三章 海外の「死」見聞録
人生における偶然 外務省に医務官に転職 サウジアラビア人外科部長との対話 イエメンの死の悼み方 ウィーン「死の肖像展」 死に親しむ街ウィーン オーストリアのがん告知 後進性故に進んでいたハンガリーの終末期医療 「死を受け入れやすい国民性」パプアニューギニア 進んだ医療がもたらす不安 呪術医が知る死に時
第四章 死の恐怖とは何か
人はどんなことにも慣れる 15歳男子の悩み 死ねないことの恐怖 それでも怖いものは怖い 死の恐怖は幻影 死戦期の苦しみは
第五章 死に目に会うことの意味
死に目に間に合わせるための非道 非道な蘇生処置の理由 「先生、遅かったぁ」という叫び 「エンゼルケア」という欺瞞 看取りのときの誤解 死に目に会わせてあげたかったことも 死に目より大事なもの 死に目を重視することの弊害
第六章 不愉快な事実は伝えないメディア
ウソは報じないけれど、都合の悪いことは伝えない 人生百年時代の意味 「ピンピンコロリ」を実践するには 達人の最期富士正晴氏の場合 人気の死因、一位はがん がんで死ぬことの効用 私の希望する死因
第七章 がんに関する世間の誤解
余命の意味 新戦略=がんとの共存 がんの治癒判定の誤解 日本でがんの告知ができるようになった理由 誤解を与えるがんの用語 否定しにくい「がんもどき理論」 がんの診断は人相判断? タブーの疑問
第八章 安楽死と尊厳死の是々非々
安楽死と尊厳死のちがい 賛成派と反対派の言い分 安楽死・尊厳死に潜む弊害 海外の安楽死事情 ウィーンの病院で起きた慈悲殺人事件 日本での安楽死・尊厳死事件 タマムシ色の四要件 安楽死法は安楽死禁止法にもなり得る 安楽死ならぬ苦悶死の現実 思いがけないことが起こる本番の死 人間関係による発覚 画期的だったNHKのドキュメンタリー 番組には強い反発が
第九章 上手な最期を迎えるには
上手な最期とは何か 病院死より在宅死 メメント・モリの効用 ACP=最期に向けての事前準備 「人生会議」ポスターの失敗 救急車を呼ぶべきか否か 胃ろうの是非「新・老人力」のすすめ コロナ禍で露呈した安心への渇望 求めない力 最後は自己肯定と感謝の気持ち
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
starbro
いつでも母さん
trazom
mukimi
hiace9000
-

- 電子書籍
- 悪役に正体がバレてしまった【タテヨミ】…
-

- 電子書籍
- 皇女様は安らかに死にたい!【タテヨミ】…
-

- 電子書籍
- 姉プチデジタル【電子版特典付き】 20…
-
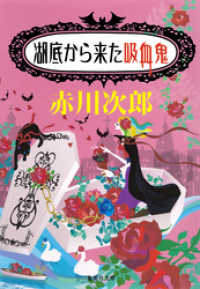
- 電子書籍
- 湖底から来た吸血鬼(吸血鬼はお年ごろシ…





