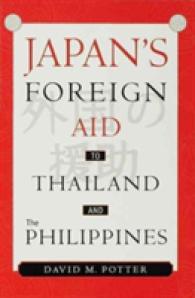内容説明
上司はわかってくれない。部下は話が通じない。夫とは一緒にいるだけでイラつくし、二人でいるのに孤独……。これらはすべて「共感障害」が原因だ。脳の認識が違うため、他人が「普通にやっていること」が理解できず、結果周囲から誤解され、軋轢を生んでしまう人たちが存在するのだ。このような共感障害者と柔らかな人間関係を築くためにすべきこととは。脳科学から解き明かす驚きの真相。(解説・尾木直樹)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
にいたけ
52
自分と他人とは認識フレームが異なる。前提をそこに置いてどう対応すべきか脳科学の視点で語っている。著者自身と自閉症スペクトラムで隠れ左利きだったことに気付く😳それくらい人は自分を普通だと思っている。今のメジャな考え方は新しい考え方が増えればマイナになる。当たり前だけど相手の立場になって考えるって言ってこの基本外してる人多いな。自戒を込めて。若い人との関係性で困ってる人は読む価値がある本です。2023/02/08
活字スキー
28
言葉は通じるはずなのに「話が通じない」「話をするだけムダ」という残念な事例は少なくない。それは各人の脳の特性や認識フレームの使い方の違いによるものだ……という本書の主張は、常日頃コミュニケーションの難しさというか不全性のようなものを感じることが多い自分にとっても非常に納得感のあるものだった。こういう認識がもっと広まると、社会全体における人間関係のトラブルや不満はかなり改善され得ると思う。つまるところ、これもまた多様性の問題なのだろう。2022/03/23
ばんだねいっぺい
27
世代との断絶が取沙汰されているが、老いも若きも人が違えば、脳のタイプが違うということ。繰り返し出てきている認識フレームというものを擦り合わせるか、特性を理解して取捨選択するかだが、議論の起点にはなるが、実用性は、もすこし煮詰めてもらったら、うれしい。2022/03/06
akiᵕ̈
21
脳の認識の違いで起こるコミュニケーション障害。そこに違いがあれば、どちらも自分のフレームで判断しているのだから相手の言動に疑問を抱くのは当然のこと。それを理解しているかいないかで、自己肯定感が低かったり、センシティブな心の持ち主は、世の中生き抜いていくのにかなり疲弊してしまうだろう。著者自体がこの障害の疑いがあって還暦を前にして判明したという〈自閉症スペクトラム〉に纏わる話が中心となっている。脳の認識の違いをどの場でどの様に生かせるか、それを自分自身が知ることがとても大切なんだと思う。2025/03/16
テツ
21
ぼく自身にそうした能力に欠けているという訳ではない(と信じている)が、何故だか良いこと、必要なこととして「察する文化」「察して文化」が蔓延する社会があまり好きではない。人と人は真の意味で理解し合うなんて絶対にできる筈はないのに自らの意思を言語化することを諦め、ふんわりとした「共感」などというやりとりを行うのは怠惰の極みではないだろうかと感じてしまう。自分にできることはまず他人に察してもらおうとするという怠惰さからの卒業。その上で言葉を尽くし何をどうしたいのか明確に伝えること。それだけでトラブルは激減する。2022/12/06
-

- 電子書籍
- 53ヶ所の旅先で 旨い菓子見つけた(小…