内容説明
永仁の徳政令――日本史上、飛びぬけて有名なこの法の本質を「「もとへもどる」という現象」と喝破し、躍動する13世紀の社会を深く鮮やかに描き出した不朽の名著、待望の文庫化!
日本人は「所有すること」をどのように捉えていたのか。サブスクリプション制やフリマアプリの登場によって、所有の概念がかつてないほど揺らいでいる今こそ読みたい、中世人の法と慣習を解き明かす一冊。(原本:岩波新書、1983年)
「今国家の債務を消すために、その他一切の債権債務を破棄する、つまり天下一同の徳政を実行すれば、日本経済は収拾のつかない混乱におちいるかもしれないし、意外にも大したことなくすぎてしまうかもしれない。いずれにせよ、少なくとも現時点ではそれが「夢のような話」にすぎないことはいうまでもない。
だが、中世社会ではそれは夢ではなかった。永仁徳政令B‐3条のように、あるいは室町幕府の徳政令がもっぱらそれを主張していたように、債権債務破棄の徳政令を発布するという現実的な道があったからである」(第一〇章「新しい中世法の誕生」より)。
日本の歴史のなかでも、単行法としてずば抜けて有名な法「永仁の徳政令」。永仁五(1297)年に出されたこの法は、21世紀の日本のみならず、制定された13世紀当時から有名な法であった。現在からは想像もつかないが、法の実在さえ法廷でまじめに争われた時代にあって、ある法の存在を同時代の人々が短時日のうちに共有したということ自体が、極めて異例のことであった。実際に、永仁の徳政令の立法からわずか二週間後には、この法に基づいた訴訟が起こされて、土地が返却されている。その後も、この法に基づいて多くの土地が売り主のもとに戻ることになった。
新幹線もSNSもない時代に、なぜこのようなことが可能だったのか。そしてなぜ徳政令は、現在もなお異色の有名法であり続けているのか。そもそも幕府自身は当初そう言っていなかったにもかかわらず、この法はなぜ「徳政」と呼ばれたのか。
永仁の徳政令にまつわる数々の謎を解き明かし、売買や贈与から浮かび上がる所有に対する意識や、「天下の大法」と呼ばれる社会規範の存在、幻の政治改革「弘安徳政」、さらにその背後にある合理主義的な政治的思潮の登場に至るまで、この不思議な法を軸に中世社会の本質に迫る。著者のエッセンスがふんだんに盛り込まれた日本中世社会史の金字塔!
【主な内容】
一 無名の法、有名の法
二 徳政令の出現
三 なぜ徳政なのか
四 天下の大法
五 贈与と譲与
六 消された法令
七 前代未聞の御徳政
八 人の煩い、国の利
九 徳政の思想
一〇 新しい中世法の誕生
あとがき
解 説(小瀬玄士)
目次
一 無名の法、有名の法
民衆にとっての法
史料としての鎌倉幕府法
書きのこされた徳政令
二 徳政令の出現
中世法の世界
すでに幕はあがっていた
永仁徳政令を読む
今さら改変に及ばず
三 なぜ徳政なのか
徳政令の評判
徳政の起源
四 天下の大法
仏物・僧物・人物
仏陀、人に帰らず
寄進の物、悔返すべからず
五 贈与と譲与
他人和与の物
タダほど高いものはない
本主へもどす
六 消された法令
徳政の風聞
安達泰盛の改革
甲乙人とは何か
七 前代未聞の御徳政
理屈から事実へ
所領もどし政策の法理
永代の職、遷代の職
弘安礼節
八 人の煩い、国の利
実基奏状の精神
沙汰を寄せる者、請取る者
弘安徳政の目ざしたもの
九 徳政の思想
田舎の習
起請文の法
彗星あらわる
一〇 新しい中世法の誕生
実際の効力
法への参加
あとがき
解 説(小瀬玄士)
-
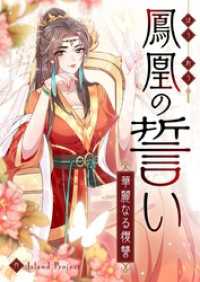
- 電子書籍
- 鳳凰の誓い~華麗なる復讐~【タテヨミ】…
-
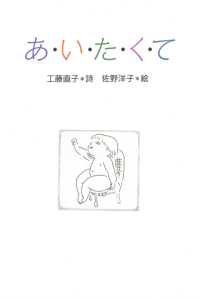
- 和書
- あいたくて 小さい詩集






