内容説明
「美術」とは何かが問い直される時代にあって、日本の美術家たちは、どのような思想のもとにいかなる創作活動を展開してきたか。具体、ハイレッド・センター、もの派、美共闘、ポストもの派……。戦後40年の日本美術の流れを跡付け、欧米の模倣でもなく、伝統への回帰でもないその逸脱の軌跡の中に、日本固有の「美術」の萌芽を読み取っていく。作品や展覧会をもとに論じるだけでなく、針生一郎、宮川淳らの批評や、李禹煥ら作家の思想も追った。「類としての美術」を提唱した鮮烈な批評にして画期的通史、およそ100頁の増補を加えた決定版。
目次
序
第一章 「具体」─アンフォルメル─「反芸術」
はじめに
Ⅰ 批評の推移
「具体」の等閑視
アンフォルメル・ショック
東野芳明
針生一郎
宮川淳
Ⅱ 「具体」とは何か
運動としての「具体」
表現過程の自己目的化
アンフォルメルへの移行
Ⅲ アンフォルメル
Ⅳ 「反芸術」のとらえなおし
「反芸術」論争
九州派
読売アンデパンダン展とネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ
「反芸術」の意味
第二章 一九六〇年代
はじめに
Ⅰ ハイレッド・センターから「環境芸術」へ
高松次郎・赤瀬川原平・中西夏之──結成
「作品」はどこにあるか
日本ポップ・アートと境界領域の美術
「環境芸術」とは何か
Ⅱ 日本概念派
美術状況の極限化
松澤宥・高松次郎・柏原えつとむ
グループ「位」
第三章 「もの派」
Ⅰ 「もの」の位相の展開
「もの派」の背景
李禹煥の役割
「もの派」の成立
「真正もの派」から「もの派」の拡大へ
Ⅱ 世界とのかかわりの思想
李禹煥
菅木志雄
「もの派」の達成と限界
第四章 一九七〇年代
Ⅰ 美術学生の反乱
「美共闘REVOLUTION委員会」
美術の根源的な制度性
美術の喪失
Ⅱ 類としての美術
西欧の論理
日本の現実
歴史的検証
プラークシスへ
Ⅲ 美術の現在
絵画・彫刻への回帰
ニュー・ペインティング現象
終りなき現在
増補 この先へ
増補へ
『現代美術逸脱史』から『未生の日本美術史』へ
状況
空白の時代を生きる
振り返って
Ⅰ 「もの派」の展開と変容
関根伸夫──突破口
李禹煥──点と線の先の絵画へ
吉田克朗──身体の絵画へ
小清水漸──ものの実体を見せること
菅木志雄──空間=時間のたて・よこ
Ⅱ 「ポストもの派」の展開 1
戸谷成雄──見えない彫刻を捉える視線
遠藤利克──空洞を求めて
堀浩哉──絵画の底に触れたい
辰野登恵子──心の闇の中から
真島直子──いのちの広がり
Ⅲ 「ポストもの派」の展開 2
「ポストもの派」に続いて
川俣正──場力本願
中村一美──ある〈A〉の絵画
小林正人──それはさ、やっぱり光なんだ
Ⅳ 「いま」のあとさき
「ポストもの派」以降の新世代──下天の内をくらぶれば
新しい世代
福岡道雄──力を抜いてさり気なく
註
あとがき
文庫版あとがき
文庫版解説にかえて(光田由里)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
阿部義彦
kana0202
十文字
-
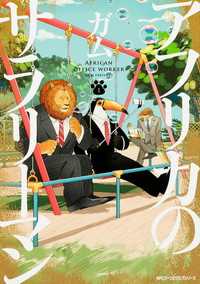
- 電子書籍
- アフリカのサラリーマン【タテスク】 C…
-
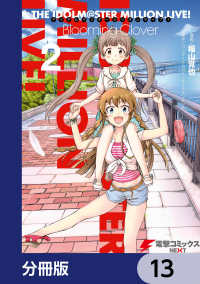
- 電子書籍
- アイドルマスター ミリオンライブ! B…
-
![自分を変える![1日5分トレーニング]1 SPA!BOOKS](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0520745.jpg)
- 電子書籍
- 自分を変える![1日5分トレーニング]…
-

- 電子書籍
- 一般相対性理論を一歩一歩数式で理解する





