内容説明
AIの存在感が増し,便利な暮らしへの期待や憧れが高まる一方で,仕事を奪われる不安に揺れる現代人.人とAIの未来はどうあるべきなのか.多様な学術的背景をもつ著者が,AIの歴史,その仕組みを解説しつつ,両者にとってよりよい社会のつくり方,さらには一人一人ができることを,「創造力と共感力」をキーワードに語ります.
目次
はじめに┴1章 AIの時代がやってきた ここまで来ている「未来」/まだまだこれからどんどん/チェスの世界チャンピオンに勝つ/AIが料理に挑戦/社会課題の解決のための技術/二〇年後の家を想像する/スマートホーム実現のための技術/スマートホーム実現に向けた三つの技術/未来の都市? 理想の都市? スマートシティ/まちづくりの新しい視点┴2章 AIってなに?┴コンピュータってなに?/記号を扱うコンピュータ/AIの歴史を概観する/生物の神経回路網をまねる/身近になりつつある深層学習/機械をかしこくする仕組み/学び方に問題はあるか/人間のようにふるまうAI/東ロボくんの挑戦から/特選「25のデジタル技術」┴3章 人間とAI┴変化する日本,変化する社会/AIで変わる私たちの仕事/AIで変わる私たちの生活/人間にしかできないこと/異なる世界を知ることからはじめよう/コロナ禍で見えてきた技術と人間の新たな関係/病気になって見えること/AIの仕組みを理解し,活用するために/AIの過去,現在,未来を学ぶ/未来を考える手がかり,共感を意識する手法┴4章 「共感」とAI┴共感を求められる仕事とAI/デジタル技術で共感をつなぐ/共感の生まれるところに発見がある/ケアを共にする社会のAIへ/ケアの倫理という視点/AIにケアの倫理を取り入れる/変わるAIエンジニアの役割/創造的共感知性と集団的知性┴5章 何を学ぶか,どうやって学ぶか┴望ましい未来とは/みんなが幸せと感じるには/サンフランシスコの学校で/OECDのキーコンピテンシー/読む,見る,聞くことから学ぶ/コンピテンシーに関する誤解/何を学ぶか,学ぶべきか/モノづくりを通した学習とPBL/アトリエ的学習環境とオンライン/「共感性」に着目した新たな知性の側面/新たなデザインプロセス「共感デザイン」┴6章 よりよい未来をデザインするために┴バックキャスティングとフォアキャスティング/スマート○○/すべては関わり合っている/生物多様性と食料生産の両立/便利な社会と不便益/本質とデジタル/教科「家庭科」の可能性/未来を考える二〇の問い┴おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シロクマとーちゃん
ありんこ
Go Extreme
Hachi_bee
みくじら
-

- 電子書籍
- DOG SIGNAL【分冊版】 22 …
-
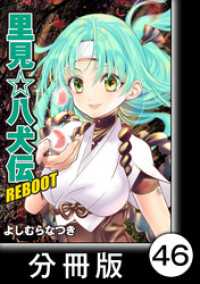
- 電子書籍
- 里見☆八犬伝REBOOT【分冊版】(4…
-
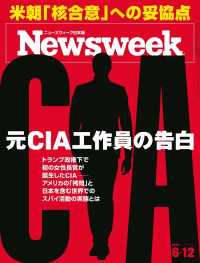
- 電子書籍
- ニューズウィーク日本版 2018年 6…
-

- 電子書籍
- 哀国戦争~猪野矢一郎のスペイン~4巻
-
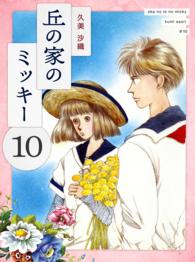
- 電子書籍
- 丘の家のミッキー10




