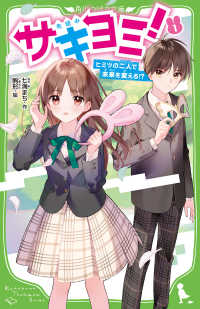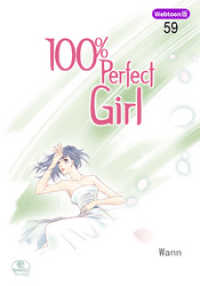- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
採集狩猟を中心とした縄文時代から、農耕を営み文明化や国家の形成が進む弥生時代へ。一般に日本の歴史の大きな分水嶺がここにあるとされてきた。では、この対照的な二つの時代は実際にはどのようなものだったのか。縄文と弥生の文化を専門とする第一人者が、最新の研究成果に基づき、農耕、漁撈、狩猟、通過儀礼、祖先祭祀、格差、ジェンダー、動物表現、土器という九つの視点から当時の生活を描き出す。さらに現代社会が抱える問題の起源を検証する。
目次
はじめに
「縄文vs.弥生」という視点
本書の構成
Ⅰ 経済活動の基本原理
第1章 縄文農耕と弥生農耕──レプリカ法で探る
1 縄文時代の農耕を求めて
一本の電話から
レプリカ法とは
縄文農耕論とはなにか
縄文農耕論への批判と期待
学際研究がもたらした発展段階論
穀物の証拠を求めて
教科書の記述によると
2 新たな分析による縄文農耕論の現在
14C年代測定とレプリカ調査の進展
日本列島の穀物栽培の起源
ヒエとオオムギの問題
エビデンスを求めて
教科書の書き換え
3 縄文農耕と弥生農耕の違い
縄文農耕の実態
植物資源利用の複雑化
遠賀川式と長原式の穀物利用
東日本の穀物利用
農耕文化複合としての弥生農耕
網羅型生業と選別型生業
縄文と弥生の植物利用の違い
第2章 二つの漁撈と海人集団の役割
1 攻める漁撈
燕形銛頭とはなにか
燕形銛頭の成立
燕形銛頭と縄文時代の漁撈
弥生時代の海蝕洞穴
海洋民的な漁撈集団
農耕民と漁撈民
2 待つ漁撈
農耕民的な漁撈
農耕民的漁撈の系譜
3 海人集団の役割
玄界灘の漁撈集団
海人集団の軌跡と組織力
海人集団と農耕集団の関係
従属する漁撈集団
縄文vs.弥生の漁撈
第3章 山と里の狩猟民
1 里での狩猟
狩猟民へのアプローチ
石鍬の大型化と石鏃の小型化
大きな罠と小さな罠
2 山人論と狩猟民
ミネルヴァ論争とはなにか
柳田國男とミネルヴァ論争
山人論の今日的意義
3 洞窟の狩猟民
奥山の洞窟遺跡
洞窟を基地にした狩猟民
狩猟民と農耕民
海・里・山の集団の関係
Ⅱ ライフヒストリーと社会
第4章 通過儀礼の変容──耳飾り・抜歯・イレズミ
1 耳飾りの役割
通過儀礼の研究を通じて
縄文耳飾りの研究
様々な文様と形
部族表示として
出自表示とステイタスシンボルとして
通過儀礼として
弥生時代の耳飾り
2 抜歯研究の変転
抜歯の意義
出自批判と双分組織
ストロンチウム同位体の分析から
14C年代測定の結果
東海系抜歯の終わり
弥生時代抜歯の二つの系譜
文化の複合的性格
3 イレズミの歴史
難しいイレズミの証明
記紀と埴輪の黥面の共通性
さかのぼる黥面表現
通過儀礼の意義と土偶大人仮説
戦争とイレズミ
通過儀礼と社会統制の強化
第5章 祖先祭祀の三つの形──縄文と弥生の死生観
1 祖先祭祀を探るには
位牌分けの習慣
文化人類学からみた祖先祭祀
祖先祭祀発生のメカニズム
祖先祭祀の普遍性
2 縄文文化の祖先祭祀
祖先祭祀の萌芽
墓地をどこに設けるか
集落を分割する意味
再葬と複葬
権現原貝塚と双分制社会
気候変動と再葬
再葬墓の役割
3 東日本弥生文化の祖先祭祀
イースター島の石棺墓
人骨の加工と変形
再葬のプロセスとシステム
弥生再葬墓の成立と系譜
最古の弥生再葬墓
祖先祭祀と通過儀礼
4 大陸由来の祖先祭祀とその影響
吉野ヶ里遺跡の墓地の構造
中国由来の祖先祭祀
漢代の祖先祭祀の影響
近畿地方の大型建物
居住域での祖先祭祀
祖先祭祀の三つの形
第6章 不平等と政治の起源
1 複雑採集狩猟民の社会
本章のあらまし
世界のなかの縄文文化
生活技術の高度化
縄文社会の仕組み
複雑採集狩猟民とはなにか
縄文文化の東西差
2 トランスエガリタリアン社会と縄文社会
縄文時代の階層差
トランスエガリタリアン社会とは
性別による偏り
有力な家系
呪術者か族長か
装身具の差異が示すもの
ヒエラルキーとヘテラルキー
3 弥生時代の不平等と政治
前方後円墳の特質
弥生時代の墓の変遷
弥生時代の不平等の由来
男性と戦争
同心円状の階層構造
世襲をめぐって
部族社会から首長制社会へ
Ⅲ 文化の根源・こころの問題
第7章 土偶が映す先史のジェンダー──男女別分業と共同参画の起源
1 縄文時代の男女──採集狩猟民の性分担
本章のあらまし
藤森栄一と座産土偶
お産姿の持続力
土偶と石棒にみる男女二元的世界観
クイア考古学
縄文社会の男女
男女二元的世界観の由来と生業
2 弥生時代の男女──農耕民の性分担と協業
西日本の男女像
東日本の男女像
農耕文化が土偶を変えた
銅鐸絵画は語る
男女のパワーバランス
分銅形土製品とはなにか
3 三つの論点──持続する縄文文化の伝統とその革新
縄文社会のジェンダー
大陸文化の影響力
持続する伝統
第8章 立体と平面──動物表現にみる世界観
1 縄文人の立体画
思想への接近
立体画と平面画
再生とアニミズム的信仰
イノシシの造形が意味するもの
狩猟儀礼としての動物表現
2 弥生人の平面画
イノシシからシカへ
地霊としてのシカ
イノシシはどうなったか
鳥形木製品と鳥装の人物絵画
弥生絵画と農事暦
3 大地から空と空想の世界へ
もう一つの立体画
弥生時代の猿蟹合戦
龍の意匠の意味
動物儀礼と複雑採集狩猟民
立体画から平面画へ
天的宗儀と神話のあけぼの
第9章 縄文土器と弥生土器
1 縄文土器の文様と形
土器の文様と形
縄文の出現と展開
縄文のない縄文土器
用途に応じた器種のバリエーション
亀ヶ岡式土器と突帯文土器
波状口縁の出現と展開
2 弥生土器の文様と形
赤く塗った土器
近畿地方の弥生土器文様
縄文の伝統と多様性の意味
弥生土器の形と象徴性
3 弥生土器の成立をめぐって
一片の土器から
壺形土器の成立をめぐって
再度、一片の土器から
弥生文化における縄文文化の役割
4 壺形土器と穀物栽培
壺形土器増加の第一の画期
第一の画期と第二の画期の意義
雑穀と壺形土器
中部高地地方の土器と農耕
東北地方北部の土器と農耕
穀物栽培と農耕文化複合
終章 弥生のなかの縄文
縄文系弥生文化再考
システムとしての農耕文化複合
遠賀川文化の農耕システム
条痕文系文化の農耕システム
複雑採集狩猟民社会の規範
砂沢文化形成の背景と評価
二元論批判に対して
時代区分論からみた縄文・弥生
民衆史の視点
革新と保守
あとがき
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
月をみるもの
活字スキー
鯖
jackbdc