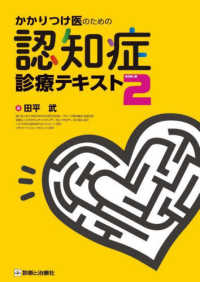- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「日本社会の食糧生産係」の役割をふられた戦後の農業界では、「豊作貧乏」が常態化していた。どんなに需要が多くても、生産物の質を上げても、生まれた「価値」は農家の手元に残らなかった。しかし、いまや食余りの時代である。単なる「食糧生産係」から脱し、農家が農業の主導権を取り戻すためには何をすればいいのか。民俗学者にして現役農家の二刀流論客が、日本農業の成長戦略を考え抜く。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
64
農作物は、自然相手であること。手間がかかること。必ずしも、思い通りにならないこと。自家菜園をやっているので、痛いほどよくわかる。モノの考えるスパンも年単位になる。この、基本的なところが、隠されているのが、今の現状につながっていると思う。2022/09/06
さきん
35
無農薬野菜や有機農業が商売として袋小路に入った印象は、消費者も自家用野菜作ったりするようになったし、手間に気づいたり、必ずしも無農薬だから安全ではないことに気づいたり、味もおいしくなるわけではなかったり。産地のブランド化も一巡してきた。著者の提案としては、ちょっとびっくりする値段をつけて、何で高いのと聞いて来る消費者にこの技術力があってのこの野菜ですと、今まで消費者が知らなかった生産での気配りを価値として認めてもらい、単なる記号としてのトマトやナスに留まらせないこと。消費者は野菜+情報を消費している。2022/03/03
もえたく
18
『1本5000円のレンコンがバカ売れする理由』に続く第2弾。従来の主張に、有機農業の歴史や植物工場への取材など加えられており興味深く読みました。有機農業と「成田三里塚闘争」の関わりや、福岡県で起きた減農薬運動を始めたのが福岡県農業改良普及員だった宇野豊氏だったことなど色々と学びに繋がりました。2022/03/12
はやたろう
15
多くの部分に共感した。農産物って、これだけいろいろなものの価格が上がってるのに、価格は安定している。いろいろな加工食品がなんやかんや理由をつけて値上げしているけど、農産物には価格転嫁できない。「柳蓮田」の取り組みは、ちょっと持続可能性が疑問だけど、これからもっと発展してほしい。 それにしても日本の農業の未来はキツイな。2024/03/26
さとちゃん
10
本書の発刊は2022年1月。コロナ禍の最中に書かれたのだと思う。その後、勃発したウクライナ侵攻。今なら野口氏はどのような切り口で書かれるのだろうか。食料の多くを輸入に頼り、肥料や種子の多くも輸入に頼っており、それがうまく回っていた(ように見えていた)時と今とではお考えも異なるのではないかと。2023/03/23
-
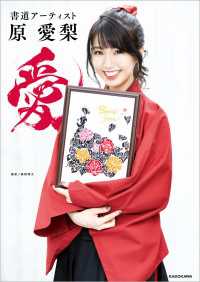
- 電子書籍
- 書道アーティスト 原 愛梨 愛【電子特…
-
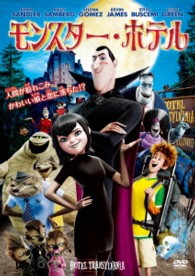
- DVD
- モンスター・ホテル