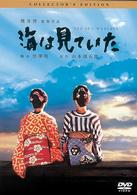- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
砂糖や小麦粉など身近な食べものから「資本主義」を解き明かす! 産業革命,世界恐慌,戦争,そしてグローバリゼーションと「金融化」まで,食べものを「商品」に変えた経済の歴史を紹介.気候危機とパンデミックを生き延びる「経世済民」を考え直すために.
目次
はじめに┴序章●食べものから資本主義を学ぶとは┴食と農の現実┴食べるための働き方も変わった┴資本主義とは┴食べものから世界経済の成り立ちを学ぶ┴1章●農耕の始まりから近代世界システムの形成まで┴農耕の「神話」と穀物の役割┴大航海時代と重商主義┴資本主義と産業革命の始まり┴砂糖の世界史┴小麦粉も世界商品に┴英国中心の第1次フードレジーム┴2章●山積み小麦と失業者たち(世界恐慌から米国中心世界の成立まで)┴自由放任主義による競争と過剰生産┴作りすぎて「恐慌」に┴戦争特需と景気の過熱から世界恐慌へ┴大恐慌への新しい政策対応┴3章●食べ過ぎの「デブの帝国」へ(戦後~1970年代までの「資本主義の黄金時代」)┴大きな政府の下で「資本主義の黄金時代」┴農業・食料でも大量生産+大量消費┴「デブの帝国」:安くした穀物で糖分・油・肉・乳製品を┴米国中心の第2次フードレジーム┴4章●世界の半分が飢えるのはなぜ?(植民地支配~1970年代「南」の途上国では)┴「飢餓」:その現状┴「南」における食と資本主義の歴史┴「緑の革命」:工業的農業モデルを途上国に輸出┴まとめ┴5章●日本における食と資本主義の歴史(19世紀の開国~1970年代)┴近代前の「糧飯(かてめし)」┴開国と近代国家建設プロジェクト┴近代的な日本食品産業の誕生┴第一次世界大戦~第二次世界大戦(1914~1945年)┴戦後日本の食と経済┴日米政府と業界による消費増進キャンペーン┴小麦粉や油を多用する食品産業の発展┴まとめ┴6章●中国のブタとグローバリゼーション(1970年代~現在)┴1970年代初めのショック┴新自由主義とグローバリゼーション┴中国のブタが世界を動かす?┴日系総合商社のグローバル戦略┴日本政府も日系企業のグローバル展開を後押し┴第3次フードレジーム?┴おわりに 気候危機とパンデミックの時代に経済の仕組みを考え直す┴お金では計れない「大切なモノ」を見直す┴主な参考文献┴あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
けんとまん1007
ちゅんさん
わむう
タルシル📖ヨムノスキー
-
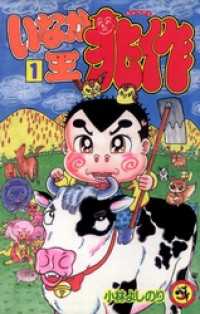
- 電子書籍
- いなか王兆作(1) てんとう虫コミックス
-
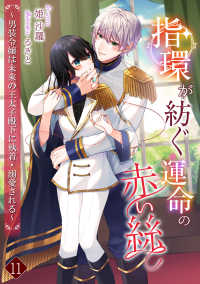
- 電子書籍
- 指環が紡ぐ運命の赤い絲 ~男装令嬢は未…