内容説明
「知識人社会の抜きがたい(…)仲間意識の源流を探りたいという現実的欲求が,本書の執筆を支えた,と言ったら,読者は笑うだろうか?」(「自歴略譜」より).律令国家解体のあとに生まれた王朝国家と,東国に新たに生まれた武家政権.中世国家の「二つの型」の構造と特質を,権力の二元性を軸に読み解く.(他一篇)
目次
日本の中世国家┴はしがき┴序章 律令国家について┴第一章 王朝国家┴第一節 令外の官┴蔵人所の成立と展開/検非違使┴第二節 官司請負制┴弁官局大少史の場合/外記局の場合/使庁の場合┴第三節 職と家業┴職の特質/家業/准用と折中/家業の論理┴第二章 鎌倉幕府┴第一節 成立過程と構造上の問題┴最勝親王の宣/寿永二年の宣旨/守護地頭の勅許/鎌倉幕府の構造┴第二節 執権制┴頼朝以後/法と衆議/将軍と執権┴第三節 得宗専制┴北条氏の権力集中/体制の矛盾と蒙古襲来/得宗政治┴第三章 王朝国家の反応┴第一節 王朝の復興┴関白と関東申次/院の評定制/官司請負制の展開┴第二節 建武新政┴国司制度の改革/中央官司の改革/八省の卿┴むすび┴注┴室町幕府開創期の官制体系┴一 政治機関の個別考察┴二 尊氏・直義の権限区分と官制┴三 官制体系の政治的背景 むすびにかえて┴注┴解説(五味文彦)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MrO
4
詳細な史料の読み込みを伴いながら、論理が一貫していて読みやすい。2020/03/01
れぽれろ
3
鎌倉時代を中心とした中世の王朝と幕府の変化を詳述する実証本。律令制が崩れた王朝国家は院政と家業世襲体制に到り、鎌倉幕府も得宗の世襲と専制に至る。システムが時を経て世襲・専制化するのは世の常か。一読書人として面白く読みました。2022/06/30
R
2
丹念に史料を読み込んでいき,そこから得られた情報をもとに鎌倉幕府の成立の過程や王朝国家の変容を明らかにしていく。歴史学の成果から想像される過去の世界は躍動感にあふれ,多くの人々を魅了するが,歴史学自体は非常に骨が折れて目に見える成果は少ない。誰も読まないような史料を探し出し,比較検討し,史料群の中に位置づけていく。必要な史料探し出すだけでも一苦労で,見つからないかもしれない。しかし,細かい作業を重ねて積み上げられたものはゆるぎがなく,説得力がある。2022/02/07
spanasu
2
王朝国家は、検非違使や蔵人所といった令外の官のもとで既存の機構を含めて再編され、小槻氏のような卑姓氏族がそこの官職を独占し付属する所領を私領のように扱い、官司請負が進むとする。もう1つの中世国家の型が東国の武士政権であるとする。非権門体制論の総本山たる東大系の中世国家像が描かれる。2020/08/15
ナハナハ
0
大河ドラマの時代が気になったので鎌倉時代初期までの部分を読んだ。律令制が崩れていく様子には人の欲には建前は勝てないんだな、と感じた。でも律令が撤回されないで解釈論で運用されるのは現代の憲法にも通じるようで面白かった。律令制の問題点を請負制で対処する様子は改革よりも現場に丸投げする現代の組織のようだ。頼朝と後白河院の交渉は勝者と敗者という一面的な見方でなく相互が抱える欠点を補完し合うようで興味深かった。2022/11/11
-

- 電子書籍
- 妖怪一家 九十九さん1 妖怪一家 九十…
-

- 電子書籍
- ベタ惚れの婚約者が悪役令嬢にされそうな…
-

- 電子書籍
- 最強ハンター ムゲン【タテヨミ】第14…
-
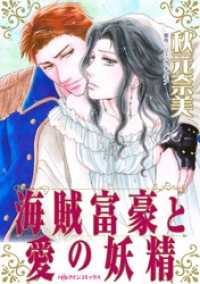
- 電子書籍
- 海賊富豪と愛の妖精【分冊】 1巻 ハー…
-
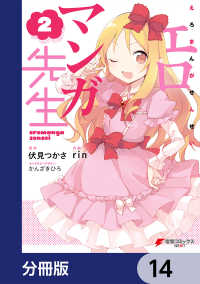
- 電子書籍
- エロマンガ先生【分冊版】 14 電撃コ…




