内容説明
アメリカの世界覇権が翳りを見せるなか、欧州で主導権を握り、存在感を増すドイツ。だが英仏など周辺国からの反撥は根強い。そこには歴史的経緯や、経済をはじめとする国力の強大化への警戒感だけでなく、放漫財政を指弾し、難民引き受けや環境保護を迫るなど、西欧的=「普遍」的価値観に照らした「正しさ」を他国にも求める姿勢がある。二千年にわたる歴史を繙き、ドイツはいかにして「ドイツ」となったのかをさぐる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
102
東西統一後のベルリンで旧東ドイツ共和国宮殿を訪れたが、粗末な外観と入居するスーパーだけが明るい内部に驚いた。その建物も撤去され復元された帝国時代の王宮に象徴されるように、事実上欧州を率いるドイツが明確な意見を表明するようになった。ナチスの過去から低姿勢外交を貫いてきたのが、なぜナショナリズム的な態度を隠さなくなったか。グローバル化による経済困難と移民難民の急増でリベラル一辺倒な歴史認識と政治が通用しなくなり、過去が新しい普遍として受け入れられたのだ。時代の変化の激しさにドイツ自身も立ち尽くしているようだ。2023/02/28
skunk_c
67
サブタイトルにあるように、「普遍」に対する「固有」の挑戦をナショナリズムと捉えてドイツの歴史を概観する。神聖ローマ帝国のような「普遍」に対するプロイセンなどの「固有」の領邦、カトリックという文字通りの「普遍」に対するルターのドイツ的な「固有」の聖書主義。そんな中で異質なのはヒトラーのドイツ的「固有」を「普遍」化しようとする思想かもしれない。フランス(ナポレオン)~英米の民主主義的「普遍」から劣等者扱いされていたドイツが、その構図をそのまま東欧~ロシアに当てはめていたという見方は確かに上手い説明と思う。2023/04/10
HANA
65
世界的「普遍」と地域的「固有」、この二つの対立、もしくはアンビバレンツな感情を元にドイツのナショナリズムを紐解いていく一冊。この二つの対立は西洋米国以外どこでもありそうだが。前半はドイツの通史でこれが最後まで続くなら「普遍」対「固有」というタイトルにする必要無いのではと思ったが、本書の眼目は後半の第二次世界大戦が終わってから。西洋的な普遍的価値に対するドイツ人の動きで、なるほどこれはタイトル通りと膝を打つ。面白いのはドイツの戦後の動きが我が国と軌を一にする部分もある事か。他人事でない気がしつつ読み終える。2021/11/08
BLACK無糖好き
23
ドイツ・ナショナリズムが古代から二千年の歴史において、西洋的「普遍」とドイツ「固有」のせめぎ合いの中でどのような変遷を辿ったかのマクロ分析。古代や中世にナショナリズムとしての概念が存在したのかはわからないが、なんらかの共同体的概念(原初主義?)はあったのだろう。何れにしてもスケールの大きな試みでもあり、このテーマを新書のフォーマット内に収めきった著者の研究者としての凄みは感じられた。◇ドイツが「普遍」を担った中世・近世の歴史を鑑みれば、ドイツが現在EUの中心的存在に君臨するのも何かの必然なのだろうか。2021/11/23
にしがき
16
👍👍👍 超充実した内容。ドイツという国の成り立ちから始まり、第二次世界大戦を経て、欧州を牽引する立場になった現代(本書はメルケル政権終わるまえの2021年発行)までのドイツの歴史とそのナショナリティーが詳しく述べられている。/仕事でドイツ人と接する機会があるが、出身地域の違いは話題にのぼるし、「東」時代の話しもよく聞く。今は移民/移民にルーツを持つ人も多い。本書は彼らの話しをより深く理解するのに役立つ。ただ、自分には新規よ情報が多すぎたので、またいつかドイツ知識が増えたら再読したい。2022/10/31
-

- 電子書籍
- 才能無しと嗤われた男爵令嬢は魔王の腕の…
-
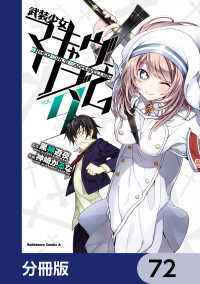
- 電子書籍
- 武装少女マキャヴェリズム【分冊版】 7…
-
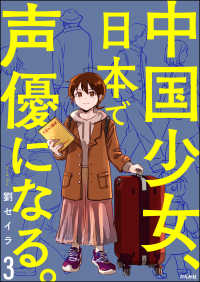
- 電子書籍
- 中国少女、日本で声優になる。(分冊版)…
-
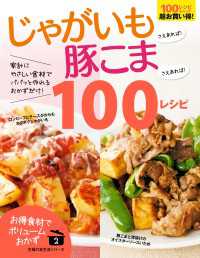
- 電子書籍
- じゃがいもさえあれば!豚こまさえあれば…
-
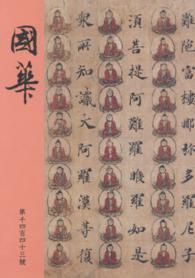
- 和書
- 國華 〈1443号〉




