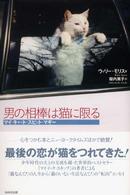内容説明
中国・南宋の朱熹の思想、朱子学は江戸時代においていかなる機能を果たしたのか――。受容とともに新たな思考が生まれてゆくさまは、従来の体制教学という理解を一面的なものとせずにはいない。とりわけ、朱子学と反朱子学の応酬は結果としてこの時代の思想表現を豊かなものにし、日本の近代化への足掛かりをも作った。本書では、朱子学の骨格から江戸時代における展開、近代化に及ぼした作用までを論じ、日本近世の知的状況を眺望する。
目次
第一章 東アジアにおける朱子学の登場
朱子学とは何か
朱子学の思想Ⅰ──「気」とは何か
朱子学の思想Ⅱ──「理」とは何か
朱子学の思想Ⅲ──人における「理」と「気」
朱子学の思想Ⅳ──学問と修養
朱子学のリゴリズム
朱子学についての通念──大義名分と尊王攘夷
朱子学の登場Ⅰ──唐宋変革論
朱子学の登場Ⅱ──北宋南宋区分論
朱子学と陽明学
第二章 江戸朱子学への道
朱子学の日本渡来
中国儒学典籍の受容のしかた
「太極」の引用
『神皇正統記』と朱子学
室町禅僧の朱子学理解の深化
仏教からの脱却Ⅰ──藤原惺窩の場合
仏教からの脱却Ⅱ──山崎闇斎の場合
構造論から修養論へ
伊藤仁斎と山崎闇斎における方向性の共有
江戸朱子学への諸ルート
朝鮮朱子学の影響
第三章 江戸朱子学の流れ
江戸朱子学の概観
朱子学と徳川政権
林家という存在
崎門という存在
第四章 丸山真男の朱子学観
丸山真男の図式
丸山図式に対する批判
伊藤仁斎と朱子学
荻生徂徠と朱子学・仁斎学
第五章 朱子学がもたらしたもの
朱子学を受け入れるということ
朱子学が導き出したもの
一、自然と規範
二、内心と外界
三、善と悪
四、個人と社会
五、道徳と欲望
六、主観と客観
第六章 朱子学と反朱子学
仁斎の「性」
朱子学と仁斎学の対立
仁斎学と闇斎学の対立
仁斎学の継承と朱子学
荻生徂徠の登場
第七章 朱子学の教理の波及
朱子学の基礎教養化
朱子学の正統論
皇統論
『詩経』観の展開
『易経』観の展開
『春秋』観の展開
朱熹の経書解釈の方法
仁斎における意味と血脈
孔子の位置づけ
第八章 朱子学の日本的展開──神道との結合
神道との結合
朱子学の鬼神論
祭祀
理と神
闇斎の場合
朱子学者と神道家
妙契
第九章 江戸後期の朱子学
幕末へ
寛政三博士と佐藤一斎
幕末の朱子学者たち
陽明学の問題
儒教の庶民への浸透と心の思想
第十章 朱子学と近代化
朱子学の理の拘束Ⅰ──価値観の問題
朱子学の理の拘束Ⅱ──自然学の問題
日本における学派並列の意味
教育の促進
近代の朱子学
近代化論との関係
朱子学のその後
おわりに
注
あとがき
人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
shimashimaon
isao_key
ゆうきなかもと
ゆうきなかもと
-

- 電子書籍
- 999種の異能使い【タテヨミ】 137話
-
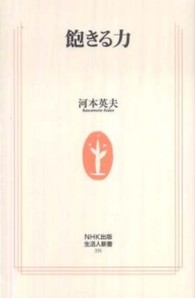
- 和書
- 飽きる力 生活人新書