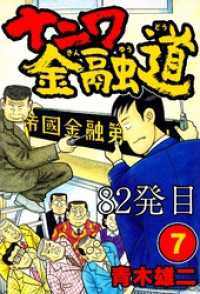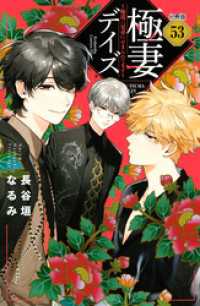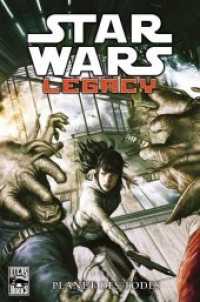- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
人間が言語に規定された存在であることは二〇世紀の哲学の前提だった。二一世紀に入って二〇年が過ぎたいま、コミュニケーションにおける言葉の価値は低下し、〈言語を使う存在〉という人間の定義も有効性を失いつつある。確かに人間は言語というくびきから解き放たれた。だが、それは「人間らしさ」の喪失ではなかろうか?――情動・ポピュリズム・エビデンス中心主義の台頭、右・左ではない新たな分断。コロナ禍で加速した世界の根本変化について、いま最も注目される二人の哲学者が、深く自由に精緻に語り合う。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
94
かねてより哲学は、日々の営みの中にあると思っている。さらに、今の状況を考えると言語化することへの危機感がある。言葉が軽んじられ、意味の無い情動的なものだけが跋扈しているからだ。そんな思いを、整理し勇気を貰った。ここ数年の世情が明確に分析されているのが素晴らしい。文字・画像・動画・・いろいろあるが、最後は、やはり言葉だと思っている。「人倫」という2文字が心に残る。ここを忘れてしまった人の姿。また、エビデンスに頼る・・実は、そこに逃げているという指摘も納得。自分の頭を絞ろうと思う。2022/03/05
うえぽん
46
2017〜2021年にかけて5度に亘る2人の第一線哲学者の対話を収録。シリーズものではないが、言語の力の衰退が通底認識。重要な問いとして受け止めた議論としては、崩壊しつつある「権威主義なき権威」をどう再生させるかと、エビデンス主義や法務的発想は民主主義的側面もあるが責任回避が過剰であり、重層的時間の中での正義を目指すべきというもの。「中動態の世界」と「勉強の哲学」という各々の著書の紹介も語学を含めた「勉強」欲を刺激する。ネオ民主主義論やデータ万能論に欠落している言葉や話し方の重要性に気付かされる対話集。2024/04/30
ころこ
45
超絶にベタな組み合わせの対談ですが、集英社新書やNHK出版新書ではなく幻冬舎新書であることに、ふたりのそれこそ中動態的なバランス感覚が健在なのを確認します。2017年から断続的に行われた対談が5回分収録されており、前半の2回でふたりの最近の代表的な仕事である『中動態の世界』『勉強の哲学』が論じられています。哲学は議論が回りくどいので、ふたつの著作で迷子になってしまった読者は本書を見取り図として使用してみるのが良いかと思いました。國分は『中動態』に依存症の問題から入ったことを強調しています。コロナで生活リズ2021/11/26
里愛乍
32
おふたりの対話が読んでいてとても楽しい。何よりお互いで相手の言葉を聞き取れて、しっかり的確な応対をされているのがいい。専門用語も交え時には補足しつつ、更なる展開で発展させ、突き詰める、もうこの読み手置いてきぼり感すら心地よい。千葉さんの言う〈詩は物質〉ってすごく腑に落ちた気がする。自分にとって言葉って単なるコミュニケーションツールじゃないから。こういう使い方をされるのがすごく好きなんですよね。そういう発見が読む度に見つけられそうで、再読は必至です。2025/06/13
よしどん
22
自分にはちょっと難しいがなかなか興味深い本だった。対談の内容が知識の沼の中を彷徨っているようで、たまに浅瀬にきたときに、自分の環境や考えにピタッと来るようなフックがあり、そこからグイグイ深みに誘い込まれるが、いつの間にか窒息気味で朦朧としてしまう、そんな読書体験だった。もっと理解が深まったら、ここに返って自分のレベルを確認したいと思った。2025/10/16