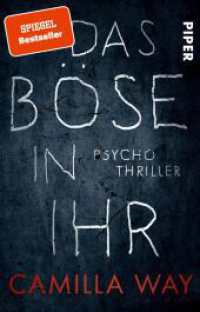- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
大和書房創業60周年・学びの杜プロジェクト「未来のわたしにタネをまこう」
シリーズ第1弾!
「食べる」という限りなく身近な行為と地球規模のさまざまな課題は、じつは密接につながっています。「食」が、私たち自身と世界にどんな影響を与えているのか、経済学の枠組みを使って、分かりやすく解説します!
私たちがどのような世界を残していきたいかを考え、さまざまな課題にどうチャレンジしていくのか、最新の研究や情報をもとに考える未来思考の経済学書です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
113
農業経済学の教科書というより、「食」の経済学的特殊性を気付かせてくれる一冊。農産物は、短期的な生産調整が難しく、所得弾力性や自己価格弾力性が小さいから、需要と供給による単純な経済学では処理しきれない。また、食品は、著者が「人間らしさ」と呼ぶ各種の認知バイアスが働きやすい商品であり、行動経済学的な分析も重要になる。更に、食料安全保障という政治的な問題も関わる(新型コロナの非常事態で、世界22カ国が食料の輸出規制を発動したとは…)。「食べる」と「経済学」をつなぐ数々の話題を提供してくれる楽しい読み物である。2022/01/25
ふじあつ
11
★★★☆☆ 全くfunではありません。とても興味深いです。食がこんなにいろいろなものと繋がっているとは驚きです。経済だけでなく,政治や心理学とも繋がっていて,とっても真面目な本でした。例えば,キャベツが豊作で20%収量が増えて,価格が50%下がったら売上が40%減っちゃう。逆に不作で20%供給量が減っても価格が50%上がったら売上が20%増える・・・なるほど,それで収穫した野菜を捨ててしまうことがあるのか・・・その他にも教養が深まる情報がたくさん。2022/05/15
セヱマ
11
食べる、と、食料生産、の視点から、環境問題や貧困問題に訴えかける農業経済学の本。読みやすい。食料の分配はまるで簡単ではない。培養肉の環境貢献の意味がよくわかった。健康的で持続可能な食生活を!EATランセット基準という概念。2022/01/05
PONSKE
9
本書は食料生産と消費に関する問題(例:肥満、資源の不足、地球温暖化など)を経済学によって分析する。市場では上手くいかない部分や、人間の不合理さに原因を見る。そのうえで、代替肉や昆虫食などの技術や、人が望ましい選択をできる食品ラベルなどの仕組みを紹介する。正直、食べることはあまりに日常的すぎて、現状維持ができなくなるとは想像し難い。だが日常が非日常になるカウントダウンはじわじわと進んでいるのかもしれない。2022/05/10
もけうに
7
とてもわかりやすく、現代社会で話題になっている問題が理解でき、大変面白かった。行動経済学の本は大体面白いが、「生きるために必要不可欠」「上限・下限がある」「体内に入れる」という点で食物は特殊。環境負荷というと工業等がまず浮かぶが、一見牧歌的なイメージの農業が、こんなにも地球資源を消費するとは。世界的にプラントベースが流行りになっているのは、単なるダイエットや宗教上の問題では無いんだな。健康的な食生活を送ることと持続可能な食料生産はまた別角度の問題だが、この本を読むと両方に意識が向く。2023/04/27
-
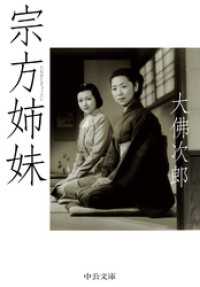
- 電子書籍
- 宗方姉妹 中公文庫