内容説明
コロナ禍で出生数が急減、このまま我々は手をこまねき「小国」への途を受容するのか。
人口は国力の源である。国際関係の基本構造は「大国」が定め、「小国」はその中で生き残る方策を考えるしかない。人口急減に直面する日本は、一億人国家の維持すら危うい状況にある。このままでよいのか。
本書は、介護保険の立案から施行まで関わり「ミスター介護保険」と呼ばれた著者が、豊富なデータと学識、政策現場での深い経験をベースに、危機的な日本の人口問題を正面から論じた超大作。
人口問題は、社会経済に深く関係し、国家存亡にも影響を与える重要テーマ。それだけに我々の価値観に関わる根深い意見対立も存在する。そこで様々な登場人物が異なる視点から語る小説形式をとっている。
政府、政党、国会がどのように関わりながら政策・法案が練られ、諮られていくのか、超リアルなストーリーに沿って、人口問題の深刻さを知り、解決策の手がかりが得られるまったく新しいタイプの書籍である。
※本書はフィクションである。登場人物は著者による創作で、モデルは存在しない。しかし、登場人物が語り、取り組む人口減少問題の内容は、すべて公開資料に基づく事実である。
目次
プロローグ 衝撃の海外レポート
第1章 一億人国家シナリオの行方
第2章 高出生率国と低出生率国の違い
第3章 出生率向上のための「3本柱」
第4章 「地方創生」と「移民政策」
第5章 議論百出の人口戦略法案
第6章 波乱の「人口戦略国会」
エピローグ 「始まり」の終わりか、「終わり」の始まりか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひこうき雲
53
お金の問題が多く論じられてるけど、そもそも今どき富裕層でも、子どもそんな多く無いよね。子どもは欲しい(自分の時間や楽しみが削られなければ)っていう人も多くなったんじゃないかな。つまり少子化は、社会全体では問題だけれども、自分にとっては正しいという。2023/02/05
HMax
28
未来への投資をしよう!!人口減少は坂を転がり落ちるように進む。大都市圏に住んでいると減った方が通勤が楽になると思っていたが、全力で人口増に取り組んで、やっとその程度が維持できる。放っておくと「老人ばかりの小国」となる。豊富なデータに裏付けられた施策の数々、子供が欲しいのに持てない状況を無くす施策は即実行してい欲しい。老人ばかりの小国となってもAI、ロボットで対応可能かもしれないが、小国となってしまっては自国で開発することが出来ず衰退が進む。BCPとして小国になることを前提にした国家戦略を考える必要がある。2023/08/05
rosetta
27
作者は元厚労省で介護保険の成立を手掛けたりした人。現役の時に少子化への対策に手をつけられなかった悔いとしてこの本を書いた。グラフや表が多用され注も沢山。小説の体をしているが内容はレポート或いは提言。500頁を超える本だが少子化対策は多方面からのアプローチが必要なためこれでも素人にわかる様な新書の内容だと思う。まず何より子供保険だろう。介護保険なんか払いたくもないが次世代の子育ての為の保険を払うことに独身未婚として吝かではない。というか今の子育て支援は雇用保険適用で非正規や無職に適用がないことに驚き2024/01/12
Mc6ρ助
20
官製少子化対策「三年間抱っこし放題」への心配は杞憂、さすがは元厚生官僚、これだけのものをイメージしてくれてるのは頼もしい。でも男性稼ぎ頭モデルやワンオペ育児に対して育児に専任するための子供保険という発想では、女性が曲がりなりにも一人で生きられ結婚や育児がリスクとなる今のこの世の中それを選択するのは難しいと斬って捨てたい(いわんやシングルマザーとなるリスク、いや、爺さまの推測だけど)。もっと労働条件等のジェンダー平等や若者の日本の未来への不安に踏み込めと思うけれども、それでも、これはこれで間違いなく良書。2023/03/16
まさおか つる
19
人口減少はこれからも続きます。いや、もっと深刻になります。将来世代は、その困難に立ち向かわなければなりません。そして、その世代が結果を残せなかったとすれば、その次の世代が、この長期にわたる挑戦を引き継いでいかなければなりません。/そのことを思うと、私たちが決してあきらめず、逃げずに苦闘した姿は、彼らをどれほど勇気づけることでしょうか。そして、それが、現在を生きる私たち世代と将来世代との間の「共感と連帯」を、どれほど強めることでしょうか。2023/05/13
-

- 電子書籍
- かたわれ令嬢が男装する理由(コミック)…
-
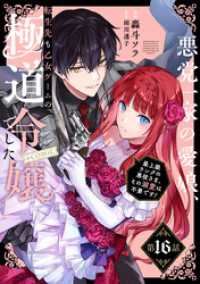
- 電子書籍
- 【単話版】悪党一家の愛娘、転生先も乙女…
-
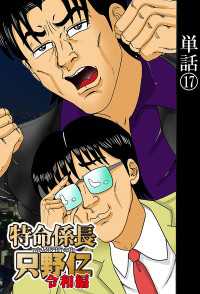
- 電子書籍
- 【単話】特命係長 只野仁令和編 17
-
![君がトクベツ 分冊版 SIDE [E] 12 マーガレットコミックスDIGITAL](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1271819.jpg)
- 電子書籍
- 君がトクベツ 分冊版 SIDE [E]…
-
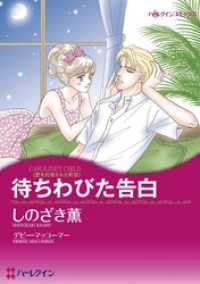
- 電子書籍
- 待ちわびた告白〈愛を約束された町Ⅲ〉【…




