内容説明
著者は立命館大学の哲学講師。2006年4月、自死を遂げるが、そこには一冊分の完成原稿が残されていた。自殺の意味と理由、方法、哲学的背景、そして決行日に向けての心理分析と行動録……淡々と描かれる「積極的な死の受容」の記録がここに。
※2008年に刊行された本書は、「人生観を試される衝撃の書」として話題になりました。
65歳の春。晴朗で健全で、そして平常心で決行されたひとつの自死。
「人生の果実は充分味わった。」そう感じた著者の遺稿『新葉隠 死の積極的受容と消極的受容』に、評論家・浅羽通明氏による解説と御子息による巻末文を加え、『自死という生き方 覚悟して逝った哲学者』と改題して出版したものです。
電子書籍化した本書を読むことで、様々に変容する世の中を生きる我々もまた「老いと死」に向き合えるかも知れません。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こばまり
55
結局、己の美学を貫いた生き方に他ならないと思う。となると、本書で繰り返し代弁されるソクラテス、三島由紀夫、伊丹十三の死も納得がゆく。自らの哲学的事業を完遂した筆者は天晴れだが、身勝手と言えば身勝手。私にはまだそのような恬淡とした度胸はない。2022/02/13
どんぐり
46
須原一秀、享年65歳。この本を遺して「老化」と「自然死」を嫌って自死した。人生を肯定したまま、しかも非常にわかりやすい理由によって決行。この本で、著者は「現代人にとって、死にたくなったときや、死なねばならなくなったとき読みたくなる本を書きたかった」と記している。僕は読みたい本がまだまだいっぱいあるので、当分は死にたくないし、死を決意する理由や実行する勇気も持ち合わせていない。故に、この本を読んでも何ら益になるものはなかった。自死の本を書いて決行する人がいたと記憶にとどめておこう。2014/07/15
nbhd
21
もう楽しく生きたから、これよりもっと生き続けても、あとは身体も衰えるだけだし、苦しくなる病気もあるし、辛いことしかないわけだから、いまこの時点で、きれいさっぱり元気なままで死んでしまったほうが、それはそれで正しいんじゃないか、たとえば、ソクラテスもあの時点で毒を飲んだわけだし、三島由紀夫もテンション高いままああいうふうになれたわけだし、伊丹十三もそういえばそうだったよね、で、たいせつなのは、私がいまこういうふうに考えているっていうことの密度だね、この密度、だからこれを書き終わったら死のうと思うんだ的な本。2015/03/16
kera1019
14
「日常的常識と日常的感覚を持っている人々に日常的立場から日常言葉で訴える凡庸なメッセージである。」という最初の言葉通り、重々しくもなく、感情に訴える訳でもなく、眈々と語られる「自分らしさと自尊心と主体性」の維持の為の死の訴えと著者の自死決行とが一つの哲学的プロジェクトとして死の受容について考えさせられました。自らの主張を証明する為に死んでいく必要があったのか?もし死なずに残された時間はどうやったんか?肯定も否定も出来ません。ホンマ、難しいと思う…2014/06/21
犬養三千代
11
疲れる本。さらりと書いてるのだけど「死」に向かっている心情が辛い。あとがきで息子さんが書いている内容でほっとしたかなぁ。2022/12/01
-

- 電子書籍
- 第24話 秘めた想い、告白…/ 違う、…
-

- 電子書籍
- 好きにさせないで、樹くん【単話版】(2…
-

- 電子書籍
- ポイントサバイバー~貯めたポイントは戦…
-
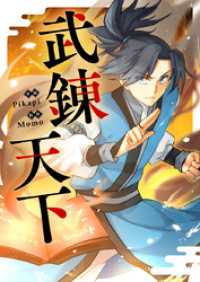
- 電子書籍
- 武錬天下【タテヨミ】第70話 picc…
-
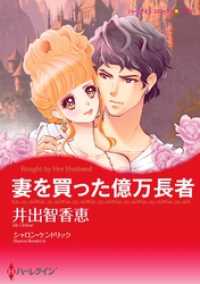
- 電子書籍
- 妻を買った億万長者【分冊】 11巻 ハ…




