- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
現在も世界で大きくなり続ける所得格差。富める者は富み、そうではないものは貧しくなっていく。どうしてそんな社会になってしまったのか? 本書は、ヨーロッパとアメリカを中心に近世から現在に至る歴史を見なおし、大衆消費社会から金融社会への変化と所得格差拡大の関連を見ていく。大衆消費社会により縮まった格差は、社会の「金融化」により拡大し、現在の構造ができあがった。大航海時代からタックスヘイヴン、GAFAの時代までを見通す一冊。
目次
はじめに
第1章 格差社会の誕生
1 格差とピケティ
格差をどうとらえるべきか
トマ・ピケティとの出会い
拡大する格差
ピケティの議論を補足するなら
世界経済の変化を取り入れない分析手法
2 イギリス──大衆消費社会から金融社会へ
イギリスの綿織物輸出
イギリスのヘゲモニーの特徴
大衆消費社会と経済成長
金融社会の形成
GDPの計算は正しいのか
富の集中
第2章 消費社会から大衆消費社会へ
1 消費社会の誕生
はじめに
消費は美徳へ
大航海時代の影響
イギリス産業革命(第一次産業革命)
第二次産業革命──化学繊維の登場
消費の拡大とその影響
グローバル化と消費社会
2 大衆消費社会の誕生
大衆消費社会とは何か
T型フォード──大量生産の実現
GMのアルフレッド・スローン──大衆消費社会を具現化した人物
耐久消費財の購入──アメリカの優位
西欧のモータリゼーション──高速道路の発展
アメリカに追いついたヨーロッパの大衆消費社会
社会主義諸国と消費
3 日本の高度経済成長
日本の場合
消費の拡大
おわりに
第3章 戦後世界の変化
1 ブレトンウッズ体制の変化
はじめに
戦後の世界経済はどう変化したか
ブレトンウッズ会議
ブレトンウッズ体制とは
ブレトンウッズ体制の崩壊
変貌する世界経済
2 ネオリベラリズムの台頭
ネオリベラリズムとは何か
サッチャー内閣
イギリス版金融ビッグバン
金融規制緩和──アメリカの場合
ヨーロッパの金融自由化
日本の金融ビッグバン
ニュージーランドとオーストラリアの金融自由化
金融社会になじまない経済思想──ケインズ政策とネオリベラリズム
3 金融化と不平等社会
不平等はいつはじまったのか
オフショアの役割
タックスヘイヴンの増加
おわりに
第4章 砂糖の王国からタックスヘイヴンへ──カリブ海域の変質
1 租税回避の方法
はじめに
租税回避行動とは何か
密輸と税金
スウェーデン東インド会社と茶の密輸
フランスからイギリスへの密輸
茶の密輸と租税回避
現代のタックスヘイヴンへ
2 大英帝国と西インド諸島
イギリスと西インド諸島産の砂糖
イギリス産業革命と西インド諸島
3 金融化する大英帝国
砂糖からタックスヘイヴンへ
産業革命から金融社会へ
4 カリブ海域の変質
関係国の変化
カリブ海域からの砂糖輸出
カリブ海域の貿易
二〇・二一世紀のカリブ海域経済
カリブ海諸国の経済転換
ケイマン諸島の事例
イギリス領ヴァージン諸島(BVI)の事例
おわりに
第5章 金融化する社会
1 世界の金融化
はじめに
OECD諸国の金融化
銀行業務の多様化
利子率のない分野の収入(手数料収入)の増加
2 EUの銀行のタックスヘイヴン
タックスヘイヴンとEUトップ二〇の銀行
EUの銀行のトップ二〇はタックスヘイヴンでどれほど儲けているのか
タックスヘイヴンの利益率
3 アイルランドとルクセンブルク
アイルランドはどうやってタックスヘイヴンになったのか
ルクセンブルク
4 アメリカの金融化
金融収入の増大
金融化がもたらす不安点
ゼネラルエレクトリック(GE)の事例
タックスヘイヴンとの関係
5 IT企業とタックスヘイヴン
GAFA
おわりに──顧客第一主義と労働者
第6章 GDPは正しいか?
1 成長するGDP?
GDPは信頼のおける指標なのか
GDPの計測は正しいか──過大評価される金融部門
2 さらに肥大化するGDP
R&DがGDPに組み込まれる
FISIMの導入
3 正確な付加価値の計算
最終的(Final)GDP=FGDP
金融をどうとらえるのか
おわりに
あとがき
主要参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
Francis
fseigojp
じゅんぺい
転天堂
-
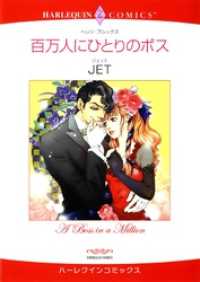
- 電子書籍
- 百万人にひとりのボス【分冊】 11巻 …
-
![月刊少年マガジン 2022年7月号 [2022年6月6日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1210455.jpg)
- 電子書籍
- 月刊少年マガジン 2022年7月号 […
-

- 電子書籍
- 頭をつかう新習慣! ナゾときタイム3
-
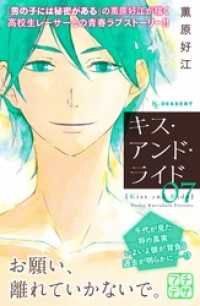
- 電子書籍
- キス・アンド・ライド プチデザ(7)
-
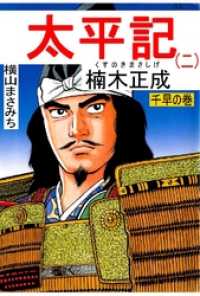
- 電子書籍
- 太平記 第2巻 千早巻




