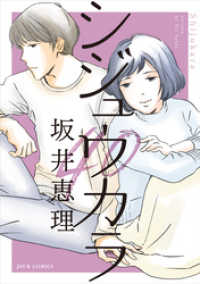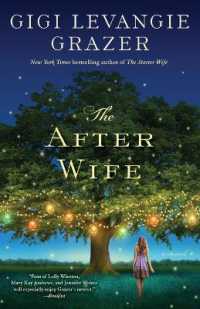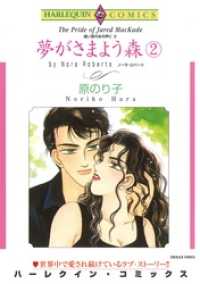内容説明
半世紀近くにわたって読み継がれた、至高の現代文教本がここによみがえる! 「文章を読む」とは、書かれた言葉の何を拾い上げ、それらをどう関係づけることなのか――。数々の小説や評論を題材に、重要な箇所をどのように見分けるかを、実演を織り交ぜながら徹底的に解説する。本書は、「文学的な文章」「論理的な文章」の2パートに分かれ、高校教科書の定番教材も多数収録。読者は、目の前にある文章について、内容や表現だけでなく、その表現を選んだ書き手の感性や想像力までも、つかめるようになるだろう。
目次
文学的な文章
Ⅰ 解釈の基本
1 主人公の輪郭―主人公はどのような人物であるか―
2 主人公をめぐる人間関係―お互いに相手をどのように意識しているか―
3 構成を調べる―事件の中で最も大きく変化したものは何か―
4 全体の主題―全体から訴えてくるもの―
Ⅱ 登場人物について
1 人物の性格―登場人物の発言や行動から性格を読む―
2 人物の心理―登場人物の心理の起伏を追求する―
3 人物の思想―登場人物の思想を知る―
Ⅲ 構成・表現について
1 主題をつかむ―「どんなことが」書かれているか―
2 意図を解釈する―「どのようなものとして」書かれているか―
3 文体を解釈する―「どのように」表現されているか―
Ⅳ 作者について
1 発想―作者が書くときにとった根本的な態度―
2 想像力―作者の想像力のはたらき―
3 感覚―作者の感覚のはたらき―
〈付〉近代・現代の詩について
論理的な文章
Ⅰ 解釈の基本
1 一語一語の内容―難解な語を理解する―
2 一文一文の内容―一文一文の内容をおさえていく―
3 段落の要旨―段落の要旨を一つ一つおさえていく―
4 全体の論旨―全体としてどういうことが論じられているか―
Ⅱ 論の重点について
1 指示詞の実質内容―コソアドの指し示すものの内容を正しくつかむ―
2 具体的事例と抽象的見解―引き合いに出された実例―
3 語句の照応―繰り返されているもの・対比されているもの―
Ⅲ 論の構成について
1 段落の設定―接続詞をつかまえるだけでは不十分―
2 判断の論拠(一)帰納を中心に―わかりきったこととして書かれていない判断に注意―
3 判断の論拠(二)演繹を中心に―前提から結論が導き出されるときの法則を知る―
Ⅳ 論者について
1 価値の置き方―論者がどういうものに価値を置こうとしているか―
2 考え方―論者の根本的な考え方を理解する―
3 物の見方―論者の世界観・人生観を探る―
索引
練習問題〈考え方〉・解答
解説(読書猿)