内容説明
こどもの哲学は、思考や議論の訓練ではなく、ケア的な哲学対話である。自分で表現することを学び、他人と語り合い、ともに考えるという経験から、自己や他者についての信頼、言葉やコミュニティへの信頼を育み、困難や挫折を他人とともに乗り越える力をつける。筆者らが見出したこどもの哲学、哲学の姿を、国内外の対話の紹介や「こどもとは?」「哲学するとは?」「教育とは?」という問いへの考察から提示する。
目次
第1部 “こどもの哲学”との出会いと展開(学校での臨床哲学
こどものケアと幸せのための対話)
第2部 世界の“こどもの哲学”を旅して(こどもの哲学探訪記―ヨーロッパやメキシコ、ハワイ、ブラジルの実践者たち
自律と自治のための/としての“こどもの哲学”―メキシコにおける「こどものための哲学」国際会議に参加して ほか)
第3部 日本での“こどもの哲学”の実践(兵庫県西宮市の小学校での「こどもの哲学」の試み
美術館で対話する ほか)
第4部 ケアと幸せのための対話(フィロ、ソファ、イエス!
こどもから「哲学するとはどういうことか」を学ぶ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Yuka
5
最近実践の機会が増えたので改めて読んでみた。場数が増えたからか今では読んでみるとなるほどなと思うところも多いし、実践と参考になるポイントとも多い。 ケアの観点はまだ自分の中で言語化できないけど‥実践を通して思うのは、学校に哲学対話を導入させるよりも、街の中の開かれた場にたくさんある方がいいのではないかなぁと思う。 著者も学校現場での実践には、開催に至るまでも、継続することも課題が多そうで、学校という仕組みの中での難しさはあると思うから、学校以外に救いになる場ができたらいいなと思う。2023/10/25
aof
4
話すこと、聞くことのおもしろさ。それは根源的な面白さで、そこにこどもも大人もない気がする。こどもも当然おもしろいって思うんだろう。 でも、なんでか学校からは「対話」が排除されている気がする。、、、いや、日本の社会から排除されているのかも。だって、会社にも対話ってないもん。少なくとも、わたしの会社には。 その貧しさと、ここに対話が流入してきたらどうなるんだろうという未来への可能性を思ってどきどきしながら読んだ。 ハワイ行きたい。2020/05/03
じゃむ
0
これから子どもと向き合っていく仕事をする身としても、大切にしていきたい言葉にたくさん出会えた。「哲学対話」、自分はこれまでこれを自然にやってきていたと感じた。これから出会う人達ともしていく。簡単ではないけれど2019/02/01
-

- 電子書籍
- ユウリ~彼女が復讐する理由~【ページ版…
-

- 電子書籍
- 夜のベランダ【タテヨミ】第68話 pi…
-

- 電子書籍
- 真心が届く ~スターと堅物弁護士の恋!…
-
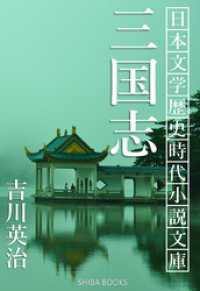
- 電子書籍
- 三国志 SHIBA BOOKS
-
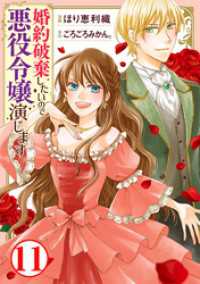
- 電子書籍
- 婚約破棄したいので悪役令嬢演じます11…




