内容説明
■「段差に注意」 →「 学力格差に気をつけろ」
ロンドンの地下鉄駅でのアナウンス“Mind the gap, please”を耳にしたとき、著者は日本の子どもたちの学力の現状を連想した。3時点(1989年・2001年・2013年)にわたる組織的な調査をもとに、家庭環境に根ざした格差の実態や格差克服の筋道を多面的に明らかにする。前著『「力のある学校」の探究』をさらに深め展開。
目次
はじめに
目次
第Ⅰ部 学力格差の構造
第1 章2013年大阪学力調査*
1.調査の背景
2.調査のアウトライン
3.学力のトレンド― 3 時点比較
4.子どもたちの生活・学習状況の変化― アンケート項目に見られる変化から
5.2001年から2013年への変化をもたらしたもの
第2 章家族の教育戦略と子どもの学力―投資と期待のジェンダー差―
1.はじめに
2.データの概要
3.家庭背景からみる学力のジェンダー差
4.投資と期待
5.投資と期待が学力に与える影響はジェンダーによって異なるのか
6.おわりに
第3 章社会関係資本と学力の関係―地域背景の観点より―
1.はじめに
2.データの概要
3.社会関係資本のアクセス可能性と分布
4.地域背景別にみた社会関係資本が学力に与える影響
5.おわりに
第Ⅱ部 教育実践と学力格差
第4 章授業改革は学力格差を縮小したか
1.はじめに
2.使用データおよび指標について
3.授業スタイルにもたらされた変化
4.授業スタイルと学力の関係
5.授業で子どもの水準・格差は変わるのか
6.おわりに
第5 章「学びあい」や「人間関係づくり」は学力格差を縮小するか
1.問題設定
2.先行研究と分析の視点
3.学びあい・人間関係と学力
4.学びあいに積極的に取り組み、人間関係が豊かなのは、どのような学級か
5.まとめと今後の展望
第6 章「集団づくり」は公正な社会観を育むか?―学力形成に付随する社会関係の社会化機能―
1.問題設定
2.基本的な分布の確認
3.公正な社会観の規定要因分析
4.学習における社会関係の規定要因分析
5.結論
第Ⅲ部 学力格差の克服
第7 章「効果のある学校」の特徴―3時点の経年比較より―
1.問題設定
2.学校の効果と児童・生徒の生活背景
3.通塾・非通塾グループの学力格差
4.家庭学習習慣・基本的生活習慣・持ち物
5.自尊感情
6.まとめと今後の研究課題― 生活の変化とその背景
第8 章「効果のある学校」を持続させている要因の検討―継承される「思い」と「仕組み」―
1.問題設定
2.継続して「効果のある学校」となったA小学校とB中学校
3.「効果のある学校」を持続させている要因の検討
4.拡がる「思い」と「仕組み」
5.まとめ
第9 章「効果」が現れにくい学校の課題―子どものウェルビーイングの観点から―
1.問題設定
2.D小学校― 急速な小規模化への対応
3.E中学校―「地域の学校」としての使命
4.まとめと今後の課題―「効果のある学校」から「ウェルビーイングのための学校」へ
第10章調査から実践へ
はじめに
1.各章の要約
2.学力の経年変化― 回復をもたらしたもの
3.学力の規定要因― 社会関係資本の可能性
4.教育活動との関係― 学力と社会性との相乗効果を生む
5.学校運営との関係―「効果のある学校」論の再検討
6.今後の課題
補論学力分析のための方法的革新
第11章項目反応理論による「学力低下・学力格差」の実態の再検討
1.はじめに
2.日本で実施されている学力調査の欠陥
3.古典的テスト理論と項目反応理論
4.IRT(項目反応理論)による分析
5.データの概要/分析結果
6.まとめ
おわりに
執筆者紹介
-

- 電子書籍
- 女子高生の無駄づかい(12) 角川コミ…
-

- 電子書籍
- のんべんだらりな転生者~貧乏農家を満喫…
-

- 電子書籍
- あまりものでも恋は甘い【単話】(3) …
-
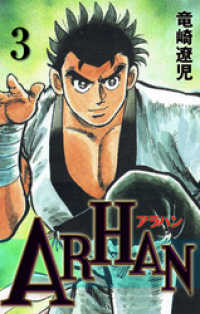
- 電子書籍
- ARHAN 3
-

- 電子書籍
- 紙の爆弾 - 2019年3月号



