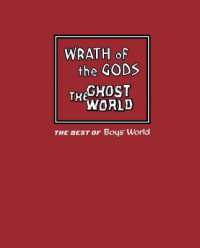内容説明
日本史の教科書で最初に出てくる、旧石器・縄文・弥生・古墳時代。三万六〇〇〇年に及ぶ先史の時代区分は、明治から戦後にかけて定着していった。しかし近年、考古学の発展や新資料の発掘に伴い、それぞれの時代の捉え方は大きく塗りかえられている。本書では、各時代の「移行期」に焦点を当て、先史の実像を描き出す。人びとの定住、農耕の開始、祭祀、「都市」の出現、前方後円墳の成立――。研究の最前線を一望する決定版。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
77
炭素14による年代測定によって、弥生時代の始まりが数百年さかのぼった衝撃は記憶に新しいが、何をもって時代の境界とみなすのか、結局は定義に左右される。土器か稲作かと、簡単に二分できるような実態ですらなかった。稲作の伝搬だけで700年。さらには、歴史時代がそのまますっぽり収まって、まだ数倍の余裕があるほど長い旧石器・縄文時代。その長さを近い時代と比べて初めて実感できたように思う。文献のない時代でも、ここまで詳細に年表が書けるほど解明が進んでいるのであれば、「先史時代の歴史」(形容矛盾っぽい表現)と言えそうだ。2022/01/30
やいっち
73
古代史の本を読むのは吾輩の読書の一環。当然ながら先史時代の本も。というより、有史以前の時間の厚みが恐らくは有史の形へも土壌になって影響していると思えるからだ。 研究者らの地道な発掘や研究の積み重ね。その積み重なりが本書の題名のように、『日本の先史時代 旧石器・縄文・弥生・古墳時代を読みなおす』ことに繋がるのだ。2022/07/03
tamami
59
本書の旧石器~縄文~弥生~古墳と、各時代の移行期の説明は、最新の研究動向を踏まえ遺跡名や研究者+学説が大きな部分を占めるも、遺物や遺跡をして文字以上に語らせるためには必要不可欠のものか。土器形式と稲作の有無ですっぱりと時代を分けていた昔からすれば「すっきりしない結論だが、これが文献のない先史時代研究の宿命」(245ページ)と記され、そこに研究の本当の面白さがあるのではと思われる。各研究者の個性もほの窺えて面白い。いわゆる概説を望む向きには、終章「先史時代を生きた人々の文化」が分かりやすくまとまっている。2021/08/31
ひろし
51
都市の始まりとは、日本ではどういうものだったんだろうと前々から思っていたので、考古学分野でそこを取り上げているので読んでみた。 全体として文字のない先史時代を対象に、特に移行期の解釈について話が展開するので、素養のない私には難しかったが、断片的に縄文時代、弥生時代、古墳時代の特徴を知ることができた。都市と考えられるものが2000年以上前に存在していたことにもびっくりした。最後に各時代の衣服や装束が載っていてこれも興味深い。2021/11/09
loanmeadime
20
時代を区切る、というのではなく、ある文化から次の文化への移行に着目して、地域的な変遷に配慮しながら、日本の古代史を概説しています。考古学の素養に乏しく、遺跡の名前と、その考古学的意味を繋げられない私は、1ページに何か所も検索が必要になり、なかなか前に進まない読書になりました。でも、変わり目、変わり方に沿って説明をしてくれているので、縄文から古墳時代まで、どのようなことが起こったのかイメージすることができました。よく利用する図書館併設のミュージアムも一度真面目に覗いてみようと思います。2022/02/20