内容説明
詩とは何か,詩が生まれ死ぬとはどういうことか――.言語以前の詩について,刻々の詩を感じる人間の瞬間の意識について,あるいは七五調の呪縛力についてなど,詩をめぐる万古不易のトピックに,現代詩に大きな足跡を残すふたりが果敢に切りこむ,白熱の対話による詩論.日本的感受性,日本語,日本文化を根源から探る.
目次
Ⅰ┴詩が死んでいく瞬間┴詩の社会的な生き死に┴言語以前の〈詩〉┴詩的原体験 谷川俊太郎の〈朝〉┴詩的原体験 大岡信の〈夜〉┴詩意識 世界の奥行の深まり┴詩における言葉と現実┴和歌 和する歌┴言語化された詩の出発┴詩人の発生 普通人以上と以下と┴現代世界の詩人の位置について┴日本語の世界の豊かさ┴散文脈を根にして 日本語の散文性評価┴散文脈を対立物として 日本語の多様性発掘┴Ⅱ┴言葉に自分がひっかけられてくる┴言葉の富をアノニムに自分のものにする┴さくらより桃にしたしき小家かな┴マザー・グースの唄┴七五調的なものにやっぱり深く縛られている┴「コップへの不可能な接近」(谷川)/115「壜とコップのある」(大岡)┴一つの「有」もなく一つの「非有」もなかった┴妖精のように跳びまわっていたいのだよ┴Ⅲ┴一人・相手・読者┴古今集・歌合・連句┴結社・同人雑誌・添削┴言葉・現実認識・一対一┴芭蕉・後白河院・スナイダー┴日本的感受性・個性・想像力┴連詩・同世代読者・戦後教育┴挨拶・暗誦・現実感覚・言葉┴あとがき(高田宏)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
113
むかしはそれこそメセナということで、企業が文化の後押しをしていくということでこのような本が出されたことがありました。エッソの広報部は雑誌も出していてそこに書かれている評論などは結構水準の高いものがありました。これもその一環で出版されたものですが岩波文庫で復刊になりました。大岡信さんと谷川俊太郎さん、聞き手が高田宏という豪華な顔ぶれでした。というか当時は若手のバリバリだったのでしょうね。詩についての3つの対談があって原論的なものからマザーグースの話まで出てきたりで楽しめます。2018/07/25
chantal(シャンタール)
85
谷川俊太郎さんと大岡信さんとによる対話。詩の歴史と言うよりも、お二人の詩の特徴や日本と西洋詩との違いや古今集、俳句と言ったものまで、幅広く、興味深く語られている。大岡さんの詩は読んだ事がないが、谷川さんの詩的原体験は「朝」で、大岡さんは「夜」、お二人の詩のイメージもこのように全く違うと言うのも面白い。詩は言葉を生み出すのではなく「選ぶ」のだ。その選び方が絶妙なわけね。「言葉と言うものは、努力しなくてもはじめから相手に伝わるものである」と言う前提は間違い。本当に自分の想いを伝える為には言葉はとても大切。2020/03/30
nobi
67
真剣勝負の熱気ある対談。このテーマを創案し編集者として同席した高田宏氏も「二人の詩人の言葉の往復に勁い緊迫と、次第に深く降りてゆく螺旋運動を聞きとっていた私…」と興奮冷めやらぬあとがき。何事も二人は正反対。原体験が朝か夜か、ものかことか、外界か内面か、誕生か死か、明か昏か、…。言葉があって初めてものが見えてくるといった固定観念をまずは揺すぶられる。「言葉よりも先に詩が先」なんて見方まで。そんな根源の議論から二人が詩を書く場面、詩歌の変遷、現代詩の社会的意義。狭く思えた隙間から現代社会の姿も見えてくるよう。2020/11/09
かふ
19
谷川俊太郎は普段はボケ担当の印象だが、この対談ではツッコミ担当。気心知れた詩人同士の対談で歴史的なことについては大岡信の話は面白い(批評家肌)。和歌は「うたげ」の詩でそうしたものが発展していく。俳句の連歌とかもそうした場の中で個人よりも全体の場(座)の空気を詠む。短歌はもともと和する歌だからね。もともと祝詞や相聞歌のような個人を歌うのではなかった。それでも左遷させられて個人の寂しさを歌う「孤立」の歌が出てきた。七五調というのはそうした日本人の場のリズムなわけだった。2019/02/08
風に吹かれて
17
ベートーヴェンの第九、第一楽章冒頭は宇宙に散らばっている音が集まってきてドドーンと始まるイメージがある。優れた音楽は、作曲されたのではなく、バッハやベートーヴェンらがすでにあるものを掬って届けてくれたように思える。 詩も同じで、大岡なら大岡が、谷川なら谷川が、生んだのではなくどこかで生まれるところを捉えて差し出したもののように本書を読んで思った。もちろん誰もが捉えられるのではなく、捉えるための教養や感性があってこそ、である。 →2023/12/25
-

- 電子書籍
- 人生後半からの住まいと暮らしを豊かに …
-
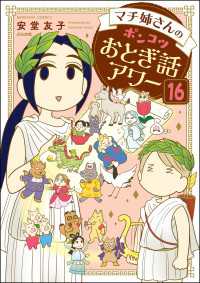
- 電子書籍
- マチ姉さんのポンコツおとぎ話アワー(分…
-
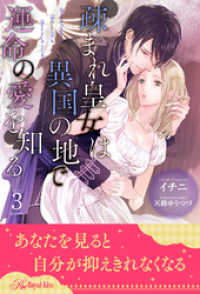
- 電子書籍
- 疎まれ皇女は異国の地で運命の愛を知る【…
-

- 電子書籍
- 女は武器でできている~社内調査員あかり…
-
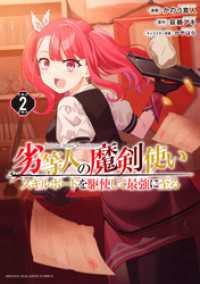
- 電子書籍
- 劣等人の魔剣使い スキルボードを駆使し…




