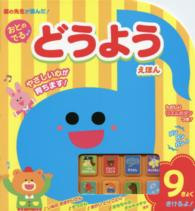内容説明
公共図書館は、そもそも何館あるのか。
47都道府県立が約60館、市区立が2,600館、町村立が620館で、全国に合計約3,300館ある。
市区町村の約77%が公共図書館を設置しているが、町村部の設置率はかなり低く57.6%でしかなく、これが全体の数字を押し下げているのが現状だ。
これを人口比でみると、日本は4万人に1館、アメリカはその倍の4万人に2館もある。
2005年には人口の48%が図書館を使っていたが、14年には34%にまで下降している。
こうした現状を踏まえ、公共図書館を増やすにはどうしたらいいのか、利用者の縮減を押し止めて図書館を使いやすくするためにはどういう施策があるのか――、を具体的に検討して提言する。
解決策の一部としてAIを使った図書館資料の管理や利用者誘導、さらに経営規模のあり方を検討し、身近な公共図書館が十分な情報資源を提供できるようになっているのかどうか、コミュニティとつながるだけのサービスポイントになっているのではないか、も指摘する。
さらに、財政難を逆手に取った岩手県の成功例や図書館が変わることで地域を変えた栃木県の実例、図書館蔵書検索サイトを使った横の連携を当事者が語る。
加えて、市民の意向を踏まえて専門的なリーダーシップを発揮した新たな図書館、心地よい空間として世界的にも有名なデンマークとフィンランドの2つの図書館を紹介して、大きなヒントを示している。
目次
まえがき
第1章 未来の図書館のエコシステム
1 公共図書館が抱える問題
2 アラップ社のレポート「未来の図書館」
3 未来の図書館のエコシステム
4 問題整理と未来の図書館への指針
第2章 これからの公共図書館を考えるために
1 法人(財団)立図書館という公共図書館
2 デンマークのオープンライブラリー
3 オランダの公共図書館の課金制
第3章 日本の公共図書館をどう育てるか――システム規模を考える
1 公共図書館は十分にあるのか
2 公共図書館はどれくらいの住民に浸透しているか
3 住民は、公共図書館サービスをどのように受け止めているのだろうか
4 人々が頼りにできるコレクションが確保されているのか
5 二つの都市の図書館システム比較
6 システム規模の見直し
第4章 図書館とコミュニティ――イギリス公共図書館の展開
1 「市民的」公共図書館の展開
2 コミュニティの亀裂と新しいコミュニティ・アプローチ
3 二十一世紀を迎えたイギリス公共図書館
第5章 図書館での技術動向・予測――「ホライズン・レポート図書館版」
1 図書館の技術動向・予測
2 「ホライズン・レポート」の立場
3 科学技術の採用を加速する動き
4 科学技術の採用を妨げる課題
5 科学技術の重要な進展
6 「図書館版」のテーマの交替
第6章 未来の図書館に関する提言
1 第一回:図書館のゆくえ――今をとらえ、未来につなげる(二〇一六年十月十七日開催)
2 第二回:図書館とソーシャルイノベーション――二〇一七年十月十一日開催
3 第三回:図書館とサステナビリティ――二〇一八年十一月二日開催
第7章 オーフス公共図書館からヘルシンキ市新中央図書館へ――公共図書館の新しい表情
1 図書館のルネサンスと都市間競争
2 二つの公共図書館への訪問
3 オーフス公共図書館
4 ヘルシンキ市新中央図書館
資料 「図書館のインパクト評価の方法と手順 ISO 16439:2014」
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さぜん
Moca
takao
火
研修屋:城築学(きづきまなぶ)
-
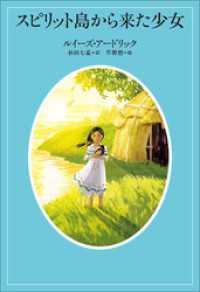
- 電子書籍
- 小学館世界J文学館 スピリット島から来…
-
![大森徹の入試生物の講義[生物基礎・生物]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1318589.jpg)
- 電子書籍
- 大森徹の入試生物の講義[生物基礎・生物]