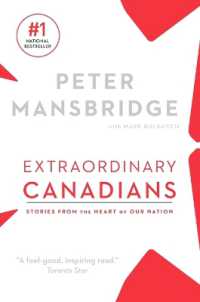内容説明
ベントン彫刻機と三省堂がなければ、日本の活字デザインの歴史は変わっていた!? かつて、活字のデザインは、ごく限られた天才=「種字彫刻師」の頭の中にのみあるものだった。現代の「書体デザイン」につながる手法を伝えたのは、辞書の「三省堂」とベントン彫刻機だったのだ。これは、「書体」が生まれるその舞台裏で奔走したひとびとの記録である。
【本書推薦の言葉】
日本の印刷界近代化の貴重な記録。それもタイポグラフィの原点にスポットを当てた内容は、我が国では初めてではないだろうか。まさに“渾身の作品”だ。
小塚昌彦(タイプデザインディレクター)
目次
目次<page:20>
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
104
先人は文字を作ることに苦労した。海外のようにアルファベットのある国ならある程度の大きさを揃えればよいが漢字はそうはいかない。活字の母型をつくるのに職人が小さいきの某に左右反転で掘らなければならない。その字が揃っていなければならない。そこで三省堂がベントン彫刻機を使って書体のバリエーションを増やしてゆく。書体を作る人のことは別の本やテレビで見たことがあるが、とても忍耐のいる仕事だと思う。パソコンが普及したといえ大元は人が作るのだろうから。様々なフォントの陰には多くの苦労がる。図書館本2022/08/11
gorgeanalogue
15
資料を駆使した労作。ぼんやりとしか知らなかったことばかりだし、歴史の記録というばかりではなく、活字彫刻がべントン彫刻機によって「機械化」されたことが、「書体デザイン」という概念を生み出したという著者の主張はいっそう興味深い。一方で、書道史上の書体の変遷は、速写など、社会的・宗教的な動機が大きく関係しているが、明朝体活字の「書体」の概念が「機械化」によって完成した、という点も興味深い。またそれに強く関わったのが辞書の出版社・三省堂であるというのも面白い。つまり、言葉=文字のマトリックス化が同時に完成された。2021/10/03
doji
1
さすがの取材力に感嘆しながら、歴史として書体デザインが生まれた軌跡だけじゃなく、概念として生まれた過程について書かれていくのがおもしろかった。自然と文字の形から「生き生きとした感じ」のような抽象的な感覚が生まれ、そこから書家による文字を参照していくあたりに、造形的なもの以外の感覚が文字に宿っているのがわかる。2023/01/02
takao
1
ふむ2022/04/18
nadami30
1
ベントン彫刻機を日本で最初に使いこなした三省堂の奮闘を描いた記録。 印刷の仕組み、金属活字の専門知識に焦点を当てるのではなく、夢を持ってアメリカから新しい技術を取り入れた人々のドラマが見どころ。 三省堂の成り立ち、書店と出版社の関係を改めて知ることができた。 「種字彫刻師」の神わざにもドラマがありそうだ。そちらも気になる。2022/03/10
-

- DVD
- クリティカル・ブロンド