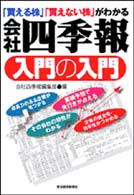内容説明
系統農会とは、農業者の間で生産、流通、販売に関する知識と技術を共有するための団体である。法制上は帝国農会、府県農会、都市農会、町村農会が存在し、それぞれの下級農会が上級農会の会員となって、系統的に議決機関を構成する。戦前期、「農業」を経営する地方と国家は系統農会を通じていかなる関係を切り結んでいったのか、政治の中で「農業」「農村」はいかなる位置を占めたのか、こうした問いに系統農会研究を通じて答えることが本書の目的である。
目次
まえがき
序章 近代日本における系統農会の位置
1 農会を研究する意義
2 農会研究の現状
3 農会史をとりまく史料状況
4 本書の構成
第一章 系統農会の設立
はじめに
1 農業諸施設の設立目的
2 明治農政で想定される「担い手」あるいはターゲット
3 一八九九年農会法の成立
おわりに
第二章 一九二二年農会法改正と郡制廃止
はじめに
1 米投売防止運動と系統農会
2 農会法改正に関する帝国議会での議論
3 郡制廃止と系統農会
おわりに
第三章 「石黒農政」と農家経営改善指導事業
はじめに
1 「石黒農政」再考
2 各種農事関連施設への人材投入と農会指導網の整備
3 「生産指導」から「経営指導」へ
4 地方制度改革と系統農会
おわりに
第四章 政党内閣期における農政運動再編――帝国農会と府県農会の動き
はじめに
1 富山県農政倶楽部の設立
2 帝国農政協会設立へ
3 富山県農政倶楽部の再活性化
おわりに
第五章 新農会法の在地的受容――千葉県山武郡源村の事例より
はじめに
1 「模範村」源村の成立
2 「模範村」源村の動揺
3 源村産米改良会と系統農会
おわりに
第六章 「農業経営改善事業」推進派の成立――一九二〇年代農政における「経営」問題の浮上の視点から
はじめに
1 第三回ILO総会と駒場講農会
2 那須皓の小作問題理解と「公正なる小作料」
3 系統農会改革論争――農会構成員をめぐって
おわりに
第七章 帝国農会への販売斡旋事業統合――販売斡旋事業統合から「農会革新案」まで
はじめに
1 販売斡旋事業統合の意義
2 養蚕業「統制」の目的をめぐる対立
3 「農会革新案」の作成
おわりに
第八章 二・二六事件と農政運動の組織化――帝国農会の変容と関西府県農会聯合・大日本農道会
はじめに
1 恐慌期から二・二六事件に至るまでの農政運動
2 二・二六事件と帝国農会機構改革
おわりに
第九章 戦時への対応・農業団体統合
はじめに
1 一九四〇年農会法改正
2 調査事業の再編
3 農業団体統合
おわりに
終章 系統農会と近代日本
1 近代日本における系統農会の位置
2 近現代日本研究における本書の含意
あとがき
事項索引
人名索引
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- スキルポイントが俺をレベルアップさせた…
-
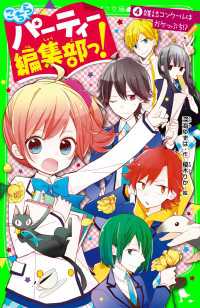
- 電子書籍
- こちらパーティー編集部っ!(4) 雑誌…