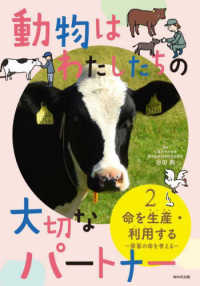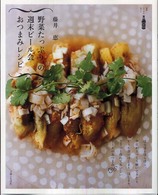内容説明
超高齢社会を生き抜く、ご近所ネットワークの可能性の選択肢とは!?
「ご近所」とは、イコール「町内会」ではなく、
すべての日本人に共通する最も身近なコミュニティ。
家庭や仕事、学校以外のコミュニティに属することで、
人生の楽しみを増やし、生き方を考え直すことにつながる。
超高齢社会の問題(老老介護、孤独死など)に向き合い、
共に生き抜く、ご近所相互扶助のパワーと今後の展望。
地域共生社会への第一歩として、「ご近所」の可能性を考える。
地域ネットワーク事業に携わる人に具体的な活動方法を教示し、手引きとなる本にする。
これから一冊をかけて、地域共生社会に向かう具体的なアプローチとなる、
ご近所起点の新しい地域ネットワーク、
つまり、ご近所の未来づくりについてお話ししていきたいと思います。
ご近所が、セーフティネット(安全網)として機能し、
私たちの日々の生活を豊かにできる。
ご近所の犯幅広い可能性(希望)の選択肢を描くことのできる本になればと思っています。
■目次
●第1章 「現状」と「ありたい姿」を共有する
・ご近所に光を当てる理由
・「ご近所づきあい格差」が広がっている
・根強く残る右肩上がりの価値観モンスター
ほか
●第2章 地域共生社会をイメージする
・後期高齢者が見ている景色
・母子家庭で育った男性がご近所の大人たちから学んだこと
・40代引きこもり男性の言葉
ほか
●第3章 ご近所の共助を「自分ごと化」する
・2030年に需要の高いスキルは学校では教えてくれない
・教育界で話題の非認知能力が育まれる
・子供から家庭へ、子供から地域へ
ほか
●第4章 変化を起こす「考え方」「心構え」に向き合う
・人づきあいは「ゆるくかるく」で大丈夫
・孤独と孤立の本質を理解する
・複数のコミュニティに属するメリット
ほか
●第5章 最大の壁「メンタルモデル」に向き合う
●第6章 日本人について考える
●第7章 行政の限界と住民主体について考える
●第8章 地域の活動に共通する難問を解決する
●第9章 ご近所の共助が日本の未来をひらく
■著者 伊藤幹夫(イトウミキオ)
1964年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。
りそな銀行(旧大和銀行)、ディップ、アニコム損害保険に勤務後、2019年に起業。
2015年から2年間多摩大学大学院での学び直しと同時に地域社会にどっぷり浸かる。
現在は、多摩大学医療・介護ソリューション研究所に席を置きながら、町内会会長、
成田ニュータウン自治会連合会事務局長、自主防災組織会長、指定避難所運営委員会委員長に加え、
多くの地域支援活動に向き合っている。公益財団法人さわやか福祉財団のさわやかパートナー。
一般社団法人若草プロジェクトの賛助会員。公益財団法人丸和育志会の会員(優秀プロジェクト賞受賞者)
(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
naka
jackbdc
Go Extreme
おさと
-

- 洋書
- ETRE SOLEIL
-
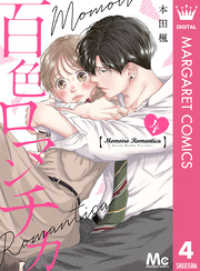
- 電子書籍
- 百色ロマンチカ 分冊版 4 マーガレッ…