内容説明
はなれ猿に送り狼,狐の飛脚,化ける猫.「この事実を,まことこの世の中に存在するものと,見なければ気が済まぬという所に歴史があるのである」.動物たちは人間の生活と感情のなかでどんな位置を占めてきたのか.伝承・物語・記録を織り交ぜながら,飼い犬や庭のどら猫一族まで,「小さな真実」の考察は自由に架橋する.(解説=室井光広)
目次
孤猿随筆┴自序┴猿の皮┴松島の狐┴狐飛脚の話┴坂川彦左衛門┴サン・セバスチャン┴対州の猪┴猫の島┴どら猫観察記┴旅二題┴モリの実験┴狼のゆくえ┴狼史雑話┴初出一覧┴解説 室井光広
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
T. Tokunaga
3
柳田國男の生態学的な視点には感服するところがかなりあり、むしろ『遠野物語』よりこちらに惹かれる。ここで書かれるように、狼は、人家の家畜という食料の充溢から個体数増加を招き、食料の一時的な減少が集住を不可能にしてつがいができづらくなり、孤狼ばかりがウロウロした末に激減した、ということを考えたとき、たとえばわたしが考えるのは、「減少している」と書かれていた「イエネコ」の末路である。要するに、現在、大体のペットのイエネコは、子孫を残せない、食料ばかり豊富な「孤猫」として1日の大半を過ごす。推して知るべしである。2025/04/02
Jonec
2
柳田国男といえば民俗学者、『遠野物語』で有名だが、唱歌「椰子の実」の元ネタを提供したように、元来ロマンチストでもあったと思うのだが、改めてこの本を読んでそう思った。彼が昔話や飼い犬の話しなどもとに話しが展開していく様は心地よい。当然読み手に求められる知識というものが存在する。本を読む面白さの一端はこういう所にもあると思う。個人的には旅のスケッチの掌編、犬を見つめる著者のまなざしがとても良かった。2012/02/25
ダージリン
1
かなり肩の力が抜けた自由な書き方という印象が強い。飼い犬のモリの話なんかのタッチも面白い。孤猿と孤狼への見方は柳田国男らしい気がする。群れを離れるところに何かストーリー性を見ているかのように思える。やはりロマンチストなのだろう。2018/05/27
Hiroshi Tanimoto
1
きつねネタで4割くらい占められてる本なのに「あ、ちなみに野生のきつねは1回しか見たことないっす。」という衝撃のカミングアウトにびびる。2012/06/05
てれまこし
0
民俗学の圏外にあるものであるが、動物にも歴史があるという主張が、歴史の持たないとされた常民の歴史を掘り起こそうという柳田民俗学と重なり、柳田の思想を理解しようとする者には意外に示唆に富む一冊。自然史の歴史化というべきか、人間同様、動物も環境の変化に適応して生活文化を変えてきたという動物版歴史主義。さらに狼生存説(山人の動物版?)、愛犬モリの古代性への愛着やその放任主義の教育方針に、ロマン主義やルソーやニーチェに通ずる現代批判も読みとれる。鎖に繋がれるようになった犬は現代人の姿でもある?2017/08/23
-

- 電子書籍
- FLASHデジタル写真集 天羽希純 A…
-

- 電子書籍
- ポプテピピック SEASON SEVE…
-
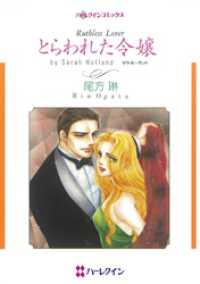
- 電子書籍
- とらわれた令嬢【分冊】 3巻 ハーレク…
-
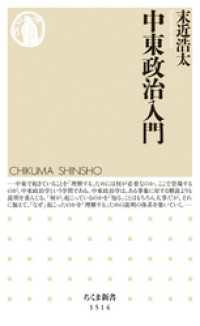
- 電子書籍
- 中東政治入門 ちくま新書
-

- 電子書籍
- ラブコメのバカ 分冊版(13)




