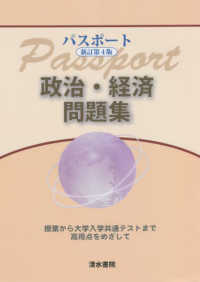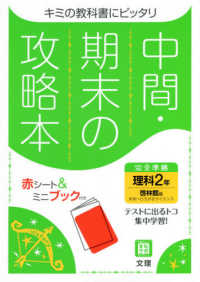- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
ちょっとした子どもの絵、データをもとにしたグラフ、美術館に展示される数々のアート作品。世の中には、言葉以外の形で表現されているものが無数に存在する。しかし、それらから何を読み取り、言葉にすればよいかはあまり教わる機会がない。そこで、様々な実例を挙げながら、特徴の み方、解釈の方法、言語化する術、社会での論じ方を段階的に解説する。アートと思考と言語が結びつけば、新たな知の興奮が生まれてくる。
目次
はじめに
Ⅰ 基礎編
第1章 ヴィジュアル情報の見方と語り方
ヴィジュアルの見方は「人それぞれ」か?
感じ方にはルールがある
文学にも「正しい」読み方がある
背景理解から妥当な推察へ
正確な理解から可能な解釈へ
理解する手順を整理する
サッカーとの類似性
ヴィジュアルの読みにもルールがある
ヴィジュアルの見方のルール
第2章 ヴィジュアル・メディアの特徴は何か?
時間が存在しないメディア
ミロの絵画を見る
言語とヴィジュアルの違い
ヴィジュアルは実数のシステム
ヴィジュアル情報はデータ量が多い
データ量が少ないことのメリット
メディア変換の必要性
ヴィジュアル情報を読む!
設問の曖昧さ
「死を想い出せ」という構造
メッセージを解釈する
さらに想像を広げる
思考を重ねる
抽象的に展開する
見ることの権力と自由
問題・矛盾の大切さ
見て考える喜び
描き方に注目する
要素の描かれ方を比較する
全体を表す言葉は何か?
対比の構造で表現する
客観的とはどういうことか?
第3章 解釈という段階
絵の社会背景を考える
「脳化社会」への懸念など
解釈に特有の言葉
内と外の対話
要素間の関係を考えて解釈する
仮説を立てる、ストーリーを想像する
対比も考える
多様性の前に基本をおさえる
相性の良い仮説を考える
ヴィジュアル情報を語る基本プロセス
言語化する重要性
言葉の機能は何か?
第4章 グラフ・データの読み取り方
グラフ形式と言語表現
グラフの読み取りとコメントの仕方
各国をグループ分けしてみる
どのくらいの内容を入れ込むか?
仮説を立てる
時間を読み取る
説明とグラフの対応
仮説と乖離するグラフ
グラフをめぐっての対話
テンションに気づいて議論する
仮説はあくまで仮説だが……
陳腐な主張に陥らない
介入の基本姿勢
介入の仕方を決める
方法は今までと同じ
グラフのどこに注目するか?
ジョブグレードのメカニズム
メカニズムを推測する
グラフの読み取りに続ける解釈
対策を考える
「何を」と「どうすれば」の違い
データの影響する範囲
第5章 ヴィジュアルの見方──絵を解釈する
陳腐な常套句から離れる
タイトル(画題)から要素へ
なぜ、このタイトルがついているのか?
「要素」を吟味する
描く対象とのかかわり
視点を変える、全体を表す
美術史からの補助線1──キュビズムの影響?
美術史からの補助線2──子供の絵の影響?
想像力を刺激する仕掛け
「童心」を方法化する
絵を見ることは考えさせられること
ヴィジュアルを見る体験とは?
Ⅱ 応用編
第6章 「カワイイ」絵は本当にカワイイだけか?──キース・ヘリング
キース・ヘリングと社会
落書きの社会的意味
抵抗の意識と行為
有効な反抗の仕方は?
ヘゲモニーの奪還
落書きの政治性
公共的空間のイメージ
政治性は右派左派で分けられない
美術制作は政治闘争でもある
落書きでありさえすればいいのか?
アートと社会
第7章 ポルノとアートの境目──エデュアール・マネの挑発
芸術のネットワーク
ヌードとは何か?
裸体は崇高か?
ヌード絵画のあり方
憤激を呼ぶメカニズム
「視線の地獄」の理論
羞恥心はどちらに感じられるか?
マネの意義
社会の中のエロティシズム
歴史的な比較の意味
森村泰昌のパロディ
画面の外との関わり
第8章 同じ問題への違う解決──ブランクーシ『レダ』
テンションを探し出す
神話との関連
ブランクーシのエクスタシー表現
だまし絵の技法
「天才」とは何か?
第9章 社会背景を当てはめる──マーク・ロスコと色面構成
カラー・フィールド・ペインティング
言葉ではなく思考する絵
「難民」という仮説
ナショナリズムとは何か?
「想像の共同体」論を適用する
ロスコの社会的地位
ナショナリズムと絵画
自殺についての伝説
芸術という共同体の仁義
解釈の多様性に向けて
第10章 比較しつつ対立を乗り越える──藤田嗣治『アッツ島の玉砕』
まず描き方を見る
比較してテンションを見つける──反戦画か戦意高揚か?
なぜ違うのか?──「画家冥利に尽きる」の検討
社会との適応の問題
帰国して環境が変わる
日本社会の観衆にどう到達するか?
自国への回帰という物語
藤田の回帰
裏切られたアイデンティティ
第11章 環境と個人の関係──ピエト・モンドリアン『ブロードウェイ・ブギウギ』
モンドリアンの変化
アメリカ移住後の作品
新大陸という環境
合理主義と民主主義の矛盾
住民運動の意味とは何か?
街の意味、公園の意味
住民コミュニティも都市インフラである
住民と地域の紐帯
卓越主義Perfectionismとは何か?
リベラリズムの原理と都市計画
ジェイコブズはリバタリアンか?
モンドリアンのポジティヴさ
リキテンスタインの色使い
おわりに