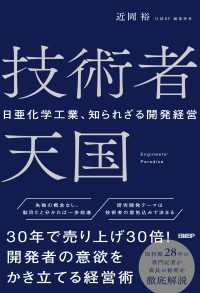内容説明
「花の○年組」「年一回の同期会」…日本は同期を重んじる文化が根強い。だが雇用が流動化した今、かつての「同じ釜の飯を食う」仲が変化している。本書は、官・司法・民間を題材に、同期の昨日・今日・明日を徹底ルポ。果たして同期の人脈ネットワークは、日本の強みか弱みか。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とみやん📖
2
著者の本で、前回読んだ、人事部を扱ったものよりは、印象は劣る。 同期の関係性を通じ、日本型雇用の功罪に迫っている。 最後のほうに書いてある、幹部選抜を早めにし、役割を分けていく、というのは、現在の日本企業が参考とすべき、一つの処方箋と思う。2016/08/27
Ryueno
2
キャリア官僚、法曹、民間企業における「同期」がどのようなものなのか、どのような役割を果たしているか、などを明らかにした本。大蔵官僚における同期は結束の象徴であったり、競争相手であったりするわけだが、同期で競い合って優秀なものが事務次官になってくれれば、あとは他の同期は彼の差配でうまいこと再就職先がみつかって退官後も安定した生活が送れるというような感じの話が書かれている。結束した同期の間でなんとなく次官候補が浮かび上がってくるというのは、次官人事を政党政治から守るためという話は初めて知った。2013/12/03
kyomi
0
同期によるヨコの人間関係は、結束と競争という矛盾する要素によって成り立ち、ホンネの人間関係がむき出しにもなるが、プラスに働けば同期の人脈と情報のネットワークがフル回転して組織を突き動かすという指摘はなるほど。グローバルな組織はともかく、多くの組織では有効な関係を実感。22017/01/14
ヒラマサ
0
文化人類学への憧れを叶えられなかったという、生涯一記者の著者による書籍。官僚、法曹、民間企業それぞれの構成員におけるインタビューからそれぞれの「同期観」を炙り出している。協調的競争関係たる同期の、協調・競争がそれぞれ色濃い事例の紹介や、日本的雇用慣行に根ざす資格と場、組織論について、前書きにある通りアカデミックではないものの、学術の知見を尊重し、ミクロなインタビューから洞察されたマクロな洞察は興味深い。2023/08/14