- ホーム
- > 電子書籍
- > 趣味・生活(健康/ダイエット)
内容説明
いま、IT化による目の酷使で、体は危機に瀕している。野口整体を学び、「快気法」「心道」などの技を編み出した著者が、体を解放する方法を伝授する。あくびの気持ちよさを体いっぱいに広げることで、緊張を解きほぐし、肩こり、腰痛などを取る方法ほか、不調を正す呼吸法、体操等満載! 人とのコミュニケーションにも生かせる。文庫化にあたり、新たな快気法を収録。
目次
文庫版まえがき
人体骨格図
はじめに
第1章 身体の危機──IT社会の多大な影響
パソコンと身体の不調
身体と精神へのパソコンの影響
コミュニケーションが壊れる
丹田に気を集め身体感覚を練る
逆流していく時代の波
骨盤を締める──中心軸の確立で健康に
中心軸を む
骨盤を締めると気配に敏感になる
日常生活に活かす──中心軸で歩けば疲れない
健康への応用──腰痛に効く!
腰帯は女性の生理痛にも効果的!
精神面への応用──勘や気づかいの重要さ
第1章のまとめ
コラム・自由人メソッド①「ジパングボディシステム」
コラム・自由人メソッド②整体武術「心道」
第2章 危機から身心を救う法
身体をゆるめる
眠っても疲れがとれない時に
積極的な寝返りで疲れを抜く快気法
腰椎一番の快気法
腰椎二番の快気法
腰椎三番の快気法
腰椎四番開型の快気法
腰椎四番閉型の快気法
腰椎五番の快気法
眼球の運動で頭の疲労回復
目と頭に効く! 眼球運動
目と生殖器の関係
みぞおちがゆるみ、丹田が満ちるはいい身体
首をゆるめるために──アキレス腱をゆるめる
ホットタオル法で目をゆるめる
ニコニコタッチを用いて──体を拡げる、縮める
腰を決めるワーク
丹田を充実させるワーク
コミュニケーションへの応用──本当の信頼感を得る
緊張を取るためのワーク
みぞおちをゆるめる
健康への応用──頭と目を休める
心の安定を取り戻す心瞑想
「虚」と「実」の活用
危険を回避する──みぞおちが虚になる方へ身を捌く
第2章のまとめ
コラム・自由人メソッド③「快気法」
コラム・自由人メソッド④「皮膚理論」=ニコニコタッチ
コラム・自由人メソッド⑤「動体学」
第3章 こころよさは強さを生み出す
1 気持ちよく動くとパワーが生まれる=快の力
気持ちよく動く──身体の原則「快・気・息」
気持ちよいことは力──「快の感覚」
身体を壊す快、整える快
「快」の感覚と生命──たとえば赤ん坊を考える
「苦痛=美徳」のあやまり
快気法はあくびを体系化したもの
快・不快を感じるワーク
ふたりで行なう相互快気法
2 「気」を練る
日本語における様々な「気」
日本における気の健康法の歴史
「気」を練る方法
正座の方法
気を練るワーク──合掌行気法
肚が決まると信頼される
3 息が入るということ
息が入ると直感がよくなる
息が入る時の身体の変化──みぞおち
まっすぐなのに息の詰まる姿勢
歪みを変えるのではなく、歪む原因を変えていく
自分の成長のために使う
背骨で息を吸う──脊髄行気法
背骨で息を吸うワーク
快気法は共鳴するボディワーク
日常生活に活かす
健康への応用──肩こり、パソコンによる疲労
精神面への応用──苦手な仕事、嫌いな人とのつきあい方
満員電車において
第3章のまとめ
第4章 心をひらく、身体をひらく
1 呼吸で変わる
路上に座り込む若者の呼吸
吸う息が多くなりすぎると?
寝相でわかる身体の状況
感覚を閉ざす都市の職場環境
男性は冷やし、女性は温める
自然とふれあうために
身体の知恵を活かすために
身体のふたつの作用を使う合気道
身体を開くと相手もほぐれる
健康への応用──身体を開く
身体を開くワーク
2 意識回路を開く
四方八方の気配を感じるために
能面は後方の意識を拡大させる
後ろの正面だあれ?
「お月様」「肝ちゃん」──言葉によって意識が変わる
手の指の意識を伸ばす
意識を伸ばすワーク
営業や躾に活かす──話す前にやるべきこと
3 コミュニケーションに役立てる
身体の「感応現象」
対立の構造──相手に身構えさせない方法
和合の構造──相手もゆるむ方法
日常生活に活かす──閉じた意識をよみがえらせる
ノイズダンスのワーク──騒音を利用する
意識で身体が変わる!
精神面への応用──「息が入る」ことの活かし方
第4章のまとめ
第5章 共鳴する身体
1 共鳴する身体
皮膚感覚で人は育つ
時間や空間の「間」の大切さ
気のコミュニケーション──野性を取り戻す
「息が合う」「ウマが合う」方法とは?
同調の方法──リズム、視線、立ち方
なぜ武蔵は小次郎に勝てたか
相手が思わずつられる「類は友を呼ぶ」
合気の技の三条件──角度、スピード、タイミング
日常生活への応用──共感を作り出し本音を語らせる
健康への応用1──身体が共鳴して背骨が整う「共鳴技法」
健康への応用2──痛みがとれる!
精神面への応用──人、動物、自然と共鳴する
2 「中庸の感覚」
押しては引くことで人間関係をスムーズに
けんかの仲裁の位置──空間における中心感覚
日常生活への活用──疲れの原因の姿勢をとって歩く方法
健康への応用──「中庸感覚」による手当て法──冷たい処と熱い処
精神面への応用──中庸の感覚を対人関係に活かす
自分の気持ちをコントロールする
3 「空間の中心感覚」──場をつかむ感覚
意固地な人の受け入れの角度
ここに座れば目立つ、ここだと目立たない──「集団の虚実感覚」
空間における「中心感覚」
健康への応用「中心感覚」──丹田に力を
精神面への応用「中心感覚」──重要な時期を む
日常生活への応用──いつも自分が座る位置は?
第5章のまとめ
あとがき
参考文献
解説──安田登
-
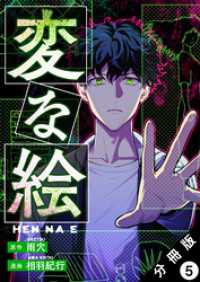
- 電子書籍
- 変な絵(コミック) 分冊版 5 アクシ…
-

- 電子書籍
- 冒険者パーティーを追放された回復士の少…
-

- 電子書籍
- 弟系淫魔くんにアラサーちゃんは夢中 8…
-
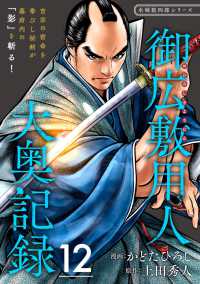
- 電子書籍
- 御広敷用人 大奥記録【分冊版】12
-

- 電子書籍
- KAMINOGE66




